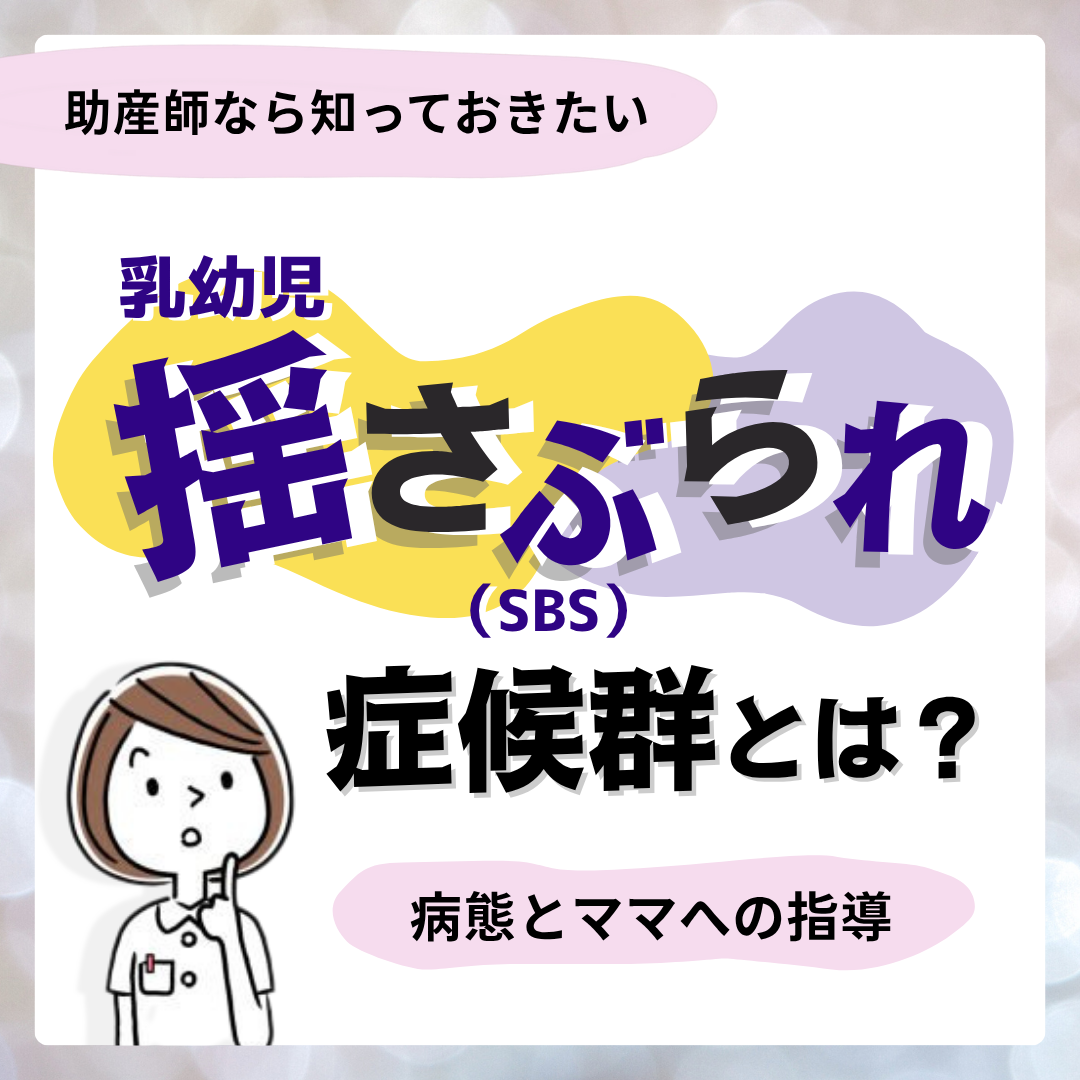
乳幼児揺さぶられ症候群(SBS)とは?助産師なら知っておきたいママへの指導
- 産後うつ
- ノイローゼ
- 退院指導
乳幼児揺さぶられ症候群とは、児の頭部が激しく揺さぶられた時に起こる重度の頭部外傷のことを言います。児は発達上、頭が重く首の筋肉が弱い状態にあるため自分の頭を一人で支えることができません。そのため、強く揺さぶられることで脳が頭蓋骨に強く打ち付けられて損傷を起こします。また、児はそのような状態になっても、泣くことや症状が起こることでしか自分の状態を周囲に伝えることができません。素早く適切な対処ができないことで後遺症が残ったり、最悪の場合命を落としたりすることにつながりかねません。外見上に目立った外傷は認めないことが多く、生後6か月までの乳幼児期に発生することが多いと言われています。
乳幼児ゆさぶられ症候群は児の頭が強く揺さぶられることで起こります。しかし、通常のお世話やあやす程度の揺さぶりで乳幼児揺さぶられ症候群が起こることはないと言われています。ではなぜこのようなことが起きるのかというと、児が泣き止まないことへのイライラやストレスから、児を強く揺さぶったり、強く叩いたりしてしまうことがあるからです。
症状
頭を強く打ち付けられるので、いわゆる脳震盪の状態です。
軽度の症状 | 重度の症状 |
・興奮して泣き止まない ・機嫌が悪くなる ・飲みが悪くなる ・嘔吐する ・ぐったりする ・眠りがちになる | ・意識消失 ・頭蓋内出血 ・硬膜外血腫 ・頭蓋骨骨折 ・失明 ・痙攣発作 ・無呼吸 ・死亡 |
また後遺症として、脳性麻痺や知的障害、発達障害、視力障害、けいれん発作が残る場合があります。
対処法
もし乳幼児揺さぶられ症候群を発症していた場合には、すぐに適切な処置が必要です。少しでも怪しいと思う場合には、すぐに救急車を要請するか、急患センターを受診しましょう。受診を迷う相談を受けた場合にもすぐに受診する必要があることを伝えてあげましょう。
治療法
児の症状に応じて、心肺蘇生や血腫除去術、脳減圧といった外科的な処置が行われます。また痙攣発作管理、循環動態や呼吸状態管理が必要となる場合には薬物や医療機器を用いた管理が行われます。後遺症が残る場合には、リハビリを行い今後の児の成長発達を促します。

予防法
児を乳幼児揺さぶられ症候群から守る一番の方法は、強く揺さぶられるような状況が起こらないようにすることです。そのためには、ママたちに児が泣いたときの対処法を伝え、実践してもらえるような指導が必要です。
赤ちゃんが泣いたときにすること
・おむつを替える
・授乳をする
・ゲップをさせる
・暑すぎないか、寒すぎないかを確認する(手足を触る、汗をかいていないか観察する)
・怪我や痛いところ、引っかかっているところがないかを確認する
・熱がないか、体調に気になるところはないかを確認する
・便秘や飲み過ぎで腹部膨満がないかを確認する
・抱っこやおんぶをしながら軽く揺れたり、歩いたりする
・お気に入りのおもちゃやタオルを渡してあげる
・一緒に遊ぶ
・お気に入りの音楽を聴かせてあげる
・抱っこやベビーカーで外に散歩したり、車でドライブにでかける
ママたちの生活環境やサポート状況を丁寧に聞きながら、具体的に説明しましょう。何か明確な理由があるときには、その原因が解消されることで泣き止むかもしれません。しかし、児が疲れていたり、眠すぎたりしていてぐずって泣き続けていることもあります。その場合にはいろいろ試してみてもすぐに泣き止まないことも多いです。上記の中から1つのことを選んで実践するのではなく、それぞれ1つずつ試してみて、それでも泣き止まないときには2周目、3周目と繰り返すことを伝えましょう。そのうち泣き疲れて眠ることが多いです。
それでも児が泣き止まずにイライラした気持ちや手を出そうになる時には、児の安全を確保した上で、心を落ち着かせることを最優先するように伝えておきましょう。
イライラしたときにすること
・深呼吸を繰り返す
・児を安全なところに仰向けで寝かせ、児から少し離れてみる
別の部屋で心を落ち着ける
(サポート者がいれば児の見守りやあやしをお願いし、1人の時には5分-10分ごとに呼吸
状態だけ確認する)
・サポート者や相談できる人に電話をかける
・かかりつけの産科や小児科に相談する
リラックス方法や気分転換ができるものがあればそれを実践したり、1人でどうしようもない時には周囲の人に遠慮なく助けを求めるように伝えます。家族や近しいサポート者がいなければ、病院や公的支援があることも情報提供しておきましょう。

助産師ができる指導のポイント
産後入院中から、異常がなくても児が泣くことや、なかなか泣き止まないことはよくあることだということを伝えておきましょう。また、乳幼児揺さぶられ症候群が起こる経緯や症状を説明し、どんなに泣き止まなくても決して揺さぶってはいけないことは伝えておきましょう。一方で、児を安全に支えた状態で「高い高い」など児の体を揺らして遊んだり、あやしたりする程度では揺さぶられ症候群は起こらないと言われています。日常生活の中で気付かないうちに発症することはほとんどないことを伝え、むやみに不安になる必要はないことも伝えておきましょう。
児が泣き止まないことについて、ママたちが何かできていないとか、悪いことをしたというわけではないことをしっかり説明しましょう。産後の寝不足や疲労の中で、児の泣き声を聞き続けると精神的に参ってしまうことや、イライラを感じることも決しておかしなことではありません。そのような時には児の安全を確保した上で、児から離れて心を落ち着かせることや周囲に頼ってよいことを予め伝えておきましょう。家族やサポート者だけで解決できない時には、外部からの支援サービスを遠慮なく活用するように指導しましょう。自治体によっては、独自のサポートサービスを行っているところもあります。退院後の生活環境やサポート状況を聞きながら、ママたちと一緒にその家族に合った公的支援を一緒に検討しましょう。地域の保健師と連携しておくことも一つの手段です。
産後に頼れる社会資源やサービス
・かかりつけの産科、小児科
・助産院
・地域の保健師
・産後ケア施設、訪問型産後ケア
・オンライン相談サービス
・ファミリーサポート
・児童館、児童センター、育児支援センター
・産後ドゥーラ
乳幼児揺さぶられ症候群は、児の命や人生に関わる重篤な外傷です。ママたちが児を傷つけるつもりはなくても、ほんのちょっとしたイライラの気持ちから、このような事態を招くことにつながってしまうかもしれません。このような悲しいことが起こらないように、私たち助産師ができることは、児が泣き止まない時やイライラした時の対処法を予め伝えておき、児を強く揺さぶってしまうという事態を起こさないことです。
児が泣き止まないことは普通のことで、ママ達がきちんとお世話を出来ていないわけではないこと、慌てたり焦ったりする必要はないことをしっかり伝えておきましょう。
そうは言っても寝不足で疲労困憊の中、何をしてあげても泣き止まない児を目の前にすると焦ったり、イライラしたりすることはあるかもしれません。その時にママたちが、冷静になれること、SOSを出せること、そしてそれを周囲がキャッチできるようにしておきたいものです。私たち助産師は、母子保健に関わる他のスタッフとともに、産前からママ達のサポート環境やサポート者との関係性を整える準備を手伝うことができます。正しい知識とママ達それぞれにあった必要な情報を提供して、ママと児を守っていきましょう。
【参考文献】
1.https://www.jpeds.or.jp/uploads/files/070815_shaken.pdf
2.Microsoft Word - (資料2)Q&A(指導室案レイアウト修正版)

【新人助産師と学生が押さえておきたい】CTG(NST)モニターの基礎知識|基線・基線細変動・一過性頻脈の見方をわかりやすく解説
- CTGモニター
- モニター判読
.png)
【助産師必見】超音波検査での胎児計測|基本項目と正しい計測方法を徹底解説
- 超音波検査
- 助産師によるエコー検査

“なんとなく”の指導はもう終わり。エビデデンスに基づく乳頭ケアの指導方法|妊婦さんの「やってみよう」を引き出す助産師の言葉は?
- 乳頭マッサージ
- 妊娠中

明日から使える!妊婦さんの不安を解消する「会陰マッサージ」指導のポイント|最新のエビデンスも解説
- 会陰部マッサージ
- 会陰部切開
- 経腟分娩
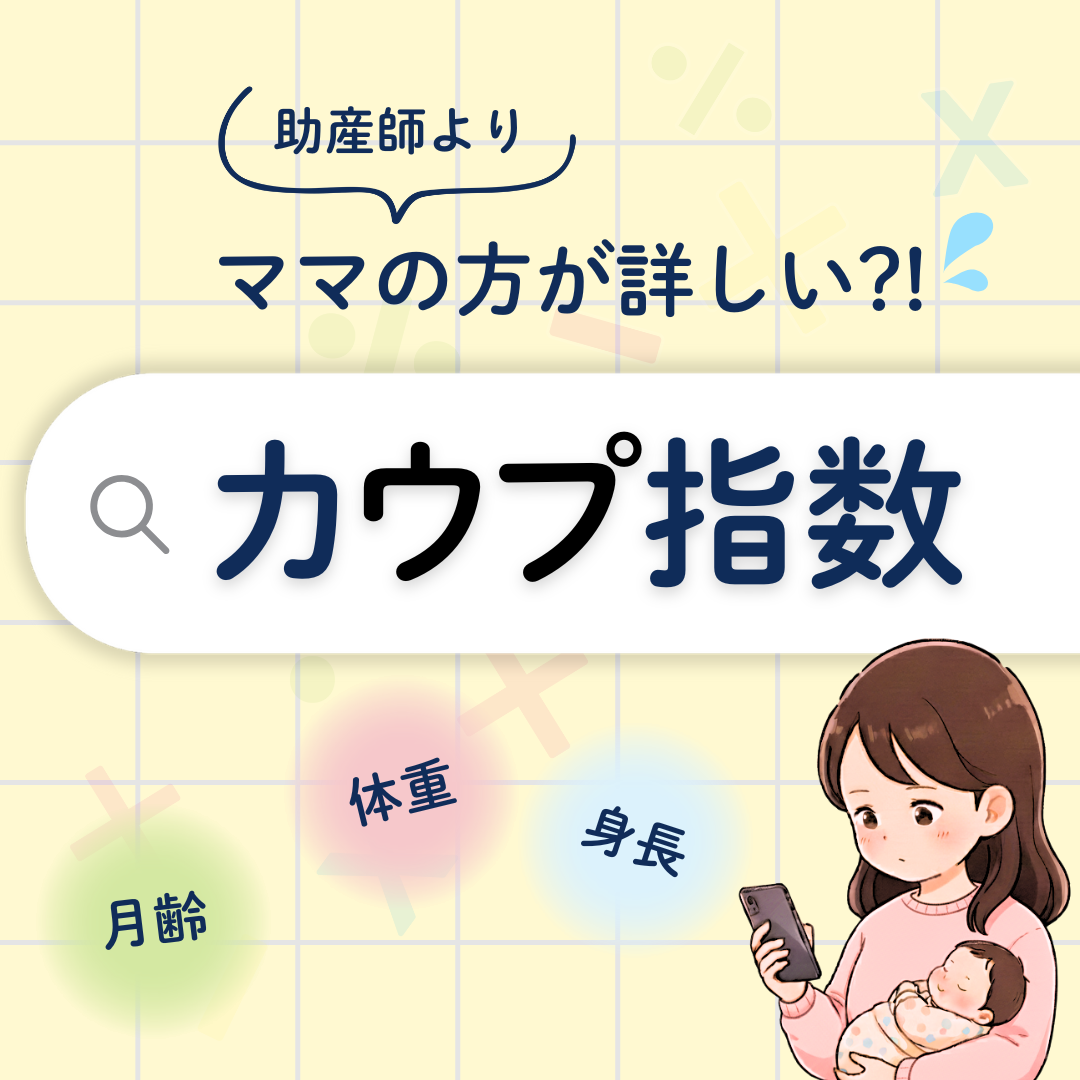
【月間3.8万検索の衝撃】ママの方が詳しいかも?助産師が知っておくべき“カウプ指数”の常識
- カウプ指数
- 月齢
- 乳幼児

Late Preterm児(後期早産児)とは?特徴・リスク・看護のポイントを徹底解説
- 早産
- Late Preterm児
- 後期早産児