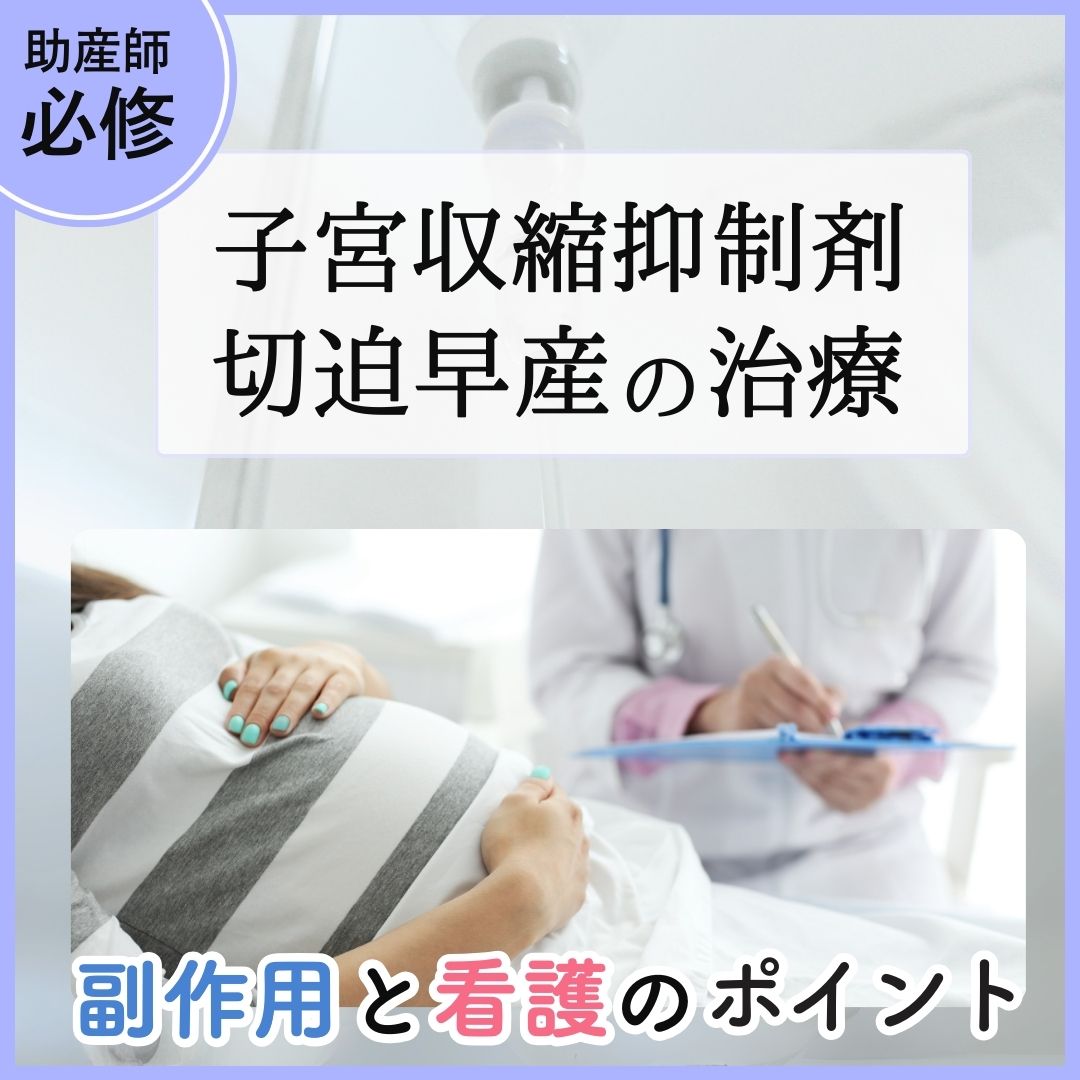.webp)
助産師必見!リトドリン点滴中の観察ポイントと注意すべき副作用とは
- 切迫早産
- 切迫流産
- リトドリン
はじめに
切迫流早産は産科医療において頻繁に遭遇する疾患であり、その治療には子宮収縮抑制剤であるリトドリン塩酸塩(商品名:ウテメリン、ルテオニンなど)が広く使用されています。リトドリンは子宮筋選択性のβ2刺激薬として、子宮の収縮を効果的に抑制する一方で、β受容体刺激による様々な副作用を引き起こす可能性があります。リトドリン投与中の観察は、薬剤の効果を確認するだけでなく、重篤な副作用を早期に発見し、母体と胎児の安全を確保することが最も重要です。中には「息苦しくて眠れない」「手が震えて不安」と精神的な負担を感じる方もいます。助産師がリトドリンの作用機序と副作用を正しく理解し、系統的な観察とアセスメントを行うことは、患者さんが安心して治療を受けるための鍵となります。今回は、リトドリンの基本的な薬理作用から、臨床現場で重要な観察ポイント、副作用への対応について解説します。

1. リトドリンの基本知識
1)薬理作用のメカニズム
リトドリンは子宮筋選択性のβ2刺激薬であり、子宮平滑筋細胞のβ2受容体に結合することで、細胞内の情報伝達物質(環状AMP)の濃度を上昇させます。β2刺激薬としての作用により子宮筋細胞の興奮を抑制し、子宮収縮を効果的に抑制することで、切迫流早産の治療に用いられます。
2)適応
・妊娠16週以降の切迫流早産
添付文書においては、妊娠35週又は推定胎児体重2500g未満の妊婦への使用が望ましいとされている。
3)投与方法と用量
<内服投与>
投与量:通常、1回1錠(リトドリン塩酸塩として5mg)を1日3回食後経口投与(15mg/日)。
調整方法:症状により適宜増減。1日用量30mgを越えて投与する場合、副作用発現の可能性が増大するとされています。
<点滴投与>
初期投与量: 通常50μg/分から開始(リトドリン2A 15ml/h〜)
調整方法: 1時間あたり25-50μg/分ずつ段階的に増減。
子宮収縮の状況を観察しながら15分~30分ごとに増量。
(例:リトドリン2Aであれば3ml/hずつ増量)
最大投与量: 200μg/分まで(リトドリン 4A:30ml/h、6A:20ml/hまで)。
突然のリトドリンの投与中止は子宮収縮の再開を招く可能性があるため、症状が安定した場合は段階的に減量し、50μg/分以下で安定していれば、内服薬への切り替えを検討します。
4)投与期間
投与期間は2通りです。
short term tocolysis(短期間投与):48時間以内の点滴投与を行う。
long term tocolysis(長期間投与):正期産まで長期に渡り点滴投与を行う。
*実際の投与量は患者の状態や副作用の程度によって調整されるため、必ず医師の指示、病院のプロトコールに沿って使用してください。
参考資料<知ってる?リトドリンの計算方法> ウテメリン1A(5ml)には50mg(50,000μg)が含まれています。 これを500mlで希釈すると、50000μg÷505ml=99μg/ml(約100μg/ml)となります。 <計算例> ・1分で50-200μg投与する場合:0.5〜2ml/分 ・1時間あたりでは:30〜120ml/h ・2Aの場合:15〜60ml/h 例:150μg/mlでリトドリン投与中の場合 1.5(ml/分)×60(分)÷6A=15ml/h ◯投与量調整時の計算方法 1時間あたり25-50μg/分での調整ですが、1時間で15ml/hずつ調整していくことはなく、15〜30分間隔で投与量を調整していくことが多いです。 <2アンプル希釈(200μg/mL)での計算> 25μg/分/時間の場合 15分毎の増量 ・25μg/分 ÷ 4回 = 6.25μg/分 ・6.25μg/分 ÷ 200μg/mL × 60分 = 1.9mL/時 20分毎の増量 ・25μg/分 ÷ 3回 = 8.33μg/分 ・8.33μg/分 ÷ 200μg/mL × 60分 = 2.5mL/時 30分毎の増量 ・25μg/分 ÷ 2回 = 12.5μg/分 ・12.5μg/分 ÷ 200μg/mL × 60分 = 3.75mL/時 <実用的な調整> ・15分毎:2-4mL/時ずつ ・20分毎:2.5-5mL/時ずつ ・30分毎:4-7.5mL/時ずつ 以上の計算より1時間あたり25-50μg/分の投与量で調整する場合は、15〜30分間隔で3ml/hずつの増量が推奨されている安全な投与量となります。リトドリンのアンプル数が増えれば濃度はくなるので、調整する投与速度は4Aなら2ml/hずつ、6Aなら1ml/hずつと減っていきます。 |
2. リトドリン投与中に起こりやすい副作用
1)副作用とその要因
リトドリンによる副作用は、以下の4つの主要な機序により発現します。
①β2受容体の刺激による心血管系への影響
リトドリンはβ2受容体を刺激することで子宮平滑筋を弛緩させますが、同時に心臓や血管系のβ2受容体にも作用し、血管拡張が起こることで副作用が出現します。
副作用
- 頻脈、動悸
- 血圧変動
- 顔面紅潮
- 頭痛
重大な副作用
- 肺水腫:心負荷増大、血管透過性亢進による肺毛細血管からの水分漏出
- 無顆粒球症:顆粒球産生の重篤な抑制
- 血小板減少:血小板産生抑制または破壊促進
- 汎血球減少:全血球系統の産生抑制
②β1受容体への交差反応による循環器系への負荷
本来はβ2受容体選択的に働く薬剤ですが、高用量では心臓にあるβ1受容体にも反応(交差反応)することがあり、心負荷が増大します。
副作用
- 心拍数増加
- 心収縮力増強
- 心筋酸素消費量増加
- 不整脈
重大な副作用
急性心不全:心筋への過度な負荷、心筋酸素消費量増加による心機能低下
③代謝系への作用
β2受容体刺激により、糖新生促進とインスリン分泌抑制が起こり、さらに細胞内へのカリウム移動が促進されるため、代謝・電解質バランスに影響を与えます。
副作用
- 血糖値上昇
- 低カリウム血症
- 代謝性アシドーシス
重大な副作用
- 低カリウム血症:細胞内カリウム移動促進による血清カリウム値の危険な低下
- 横紋筋融解症:代謝異常、電解質異常による筋細胞の破壊
- 肝機能障害:薬剤代謝による肝細胞への負荷、循環動態変化による肝血流低下
- 腎機能障害:循環動態の変化による腎血流低下、電解質異常による腎機能低下
④神経系および皮膚系への作用
骨格筋や皮膚のβ受容体刺激、および交感神経系全体の活性化により、神経系および皮膚症状が現れます。
副作用
- 手指振戦
- 不安感・興奮
- 皮膚発疹
- 皮膚掻痒感
2)ベタメタゾン(リンデロン)併用時の注意すべき副作用
妊娠24週以降〜34週未満で1週間以内に早産になる可能性が高い場合は、リトドリンによる子宮収縮抑制の治療と並行して、胎児の肺成熟を促したり、頭蓋内出血を予防するためにベタメタゾン(リンデロン)を投与されることがあります。しかし、リトドリンとベタメタゾンの併用により体内の体液貯留が促進され、リトドリンのβ1受容体への交差反応による心拍出量増加や、妊娠による生理的変化の相乗効果によって肺水腫を起こすリスクが高くなります。
また、心疾患、妊娠高血圧症候群の合併、多胎妊娠、副腎皮質ホルモン剤併用時にも肺水腫が発生しやすい報告があるため、リンデロンを使用する際にはさらなる注意が必要です。
3)胎児・新生児への影響
副作用
胎児頻脈、新生児低血糖、新生児高カリウム血症、心室中隔壁肥大
新生児高カリウム血症はリトドリンと硫酸マグネシウム水和物(マグセント)を併用した場合にリスクが高いことが報告されています。
国立成育医療研究センター(2017年)の研究では、妊娠中に子宮収縮抑制剤(塩酸リトドリン)を経静脈的に長期間使用すると児が5歳になったときの喘息有症率が高いことを示唆する結果が報告されており、長期投与による児の将来的な健康への影響についても注意が必要です。
リトドリンは切迫早産の治療において重要な薬剤ですが、様々な副作用があり、症状としても顕著に現れることが多い薬剤でもあります。欧米では肺水腫などの重篤な副作用を引き起こす恐れがあること、陣痛抑制の効果が48時間以内に限られるというエビデンスから、リトドリンの使用が48時間以内に制限されています。日本ではリトドリンの使用頻度は高く、再発予防目的に長期に渡って投与することが多いですが、長期投与の有用性のエビデンスはなく、日本でもshort term tocolysisの方針へ移行していく動きがあります。副作用の観点からも投与の必要性と期間については慎重な判断が求められています。

3. 助産師が押さえるべき観察項目
1)リトドリン点滴投与前
リトドリンを投与できる状態かバイタルサインと情報の確認を行い、点滴投与開始後にバイタルサインの変化がないか観察できるようにします。また、連続的なCTGモニタリングで胎児の状態変化を見逃さず評価します。
チェックポイント
- バイタルサイン測定(血圧、心拍数、体温、SpO2)
- 血液データ確認(血糖値、肝機能、電解質など)
- 基礎疾患・既往歴(特に糖尿病、心疾患)の確認
2)リトドリン点滴投与開始時〜
15〜30分毎の定期的なバイタルサイン測定を行い、副作用の早期発見に努めます。
子宮収縮の間隔があかずに投与量の調整が必要な時はバイタルサインと胎児の状態を確認し、点滴を増量できるか判断します。投与開始後は早期に母体の心拍数が110-120回/分程度まで上昇することがあります。過度の心拍数増加や血圧低下があらわれた場合には、投与量の減量について医師の指示を仰ぎましょう。
チェックポイント
- 血圧変動(収縮期血圧上昇、拡張期血圧低下、脈圧拡大)
- 心拍数(心拍数増加、不整脈)
- 呼吸状態(呼吸困難、胸苦しさの有無、呼吸数、SpO2低下)
- 肺水腫の早期発見(湿性ラ音、泡沫状痰)
- 動悸、呼吸苦、手指振戦、火照りなど自覚のある副作用の有無
- 子宮収縮の頻度
- 子宮収縮の自覚、下腹部痛の有無
- 胎児の状態(頻脈、基線細変動の増加)
- 点滴刺入部の状態(発赤、腫脹、疼痛、硬結)
3)リトドリン投与にて入院継続中
リトドリンにより切迫早産の症状がコントロールできていても、リトドリン投与開始時と同様に日々の観察は必要です。入院中は定期的な血液検査や尿検査で異常がないかも確認していきましょう。子宮収縮の頻度や状態によって、リトドリン投与量の変更が日常的に行われるため、投与量が合っているかも大切な観察項目です。また、リトドリンはブドウ糖液での希釈が推奨されていますが、長期の治療により点滴漏れなどを起こすことも多くなるので、刺入部もしっかり観察しましょう。
チェックポイント
- リトドリン開始時と同様
- アンプル数と速度
- 血液検査(血糖値[高血糖]、電解質[特に低カリウム血症]、肝機能[AST、ALT]、血球数[白血球、血小板]、乳酸値)
- 尿検査(尿糖、尿量、腎機能)
4)分娩後の注意点
リトドリンを投与していた母体から出生した新生児は上記で述べた副作用が出現することがあるので、症状の有無にかかわらず母体がリトドリンを使用していた場合は、ルーチンで新生児の血糖値のモニタリング、マグセント併用時は心電図または血清カリウム値のモニタリングを行い、異常があれば適切に対応できるようにします。
チェックポイント
- 母体の子宮復古状況
- 新生児バイタルサイン(心拍数、心雑音、呼吸状態)
- 新生児の血糖値
- 新生児の血液検査(カリウム値)
5)記録の内容
- 投与開始時刻と投与量
- 投与量の変更
- バイタルサイン
- 子宮収縮の状況、評価
- 副作用の有無と程度
- 患者の主観的症状

4. リトドリンの副作用への対応
1)副作用出現時の報告のタイミング
リトドリンの副作用が出現しても、治療上予測されたり、許容範囲の副作用(手指振戦、顔面紅潮、120回/分以下の心拍数の増加)については、すぐに報告する必要はありません。以下の状態の場合には、バイタルサインなどのデータと本人の自覚症状や子宮収縮頻度を合わせて医師へ報告します。
報告のタイミング
- 心拍数が120回/分を超えてくる
- 動悸が強い
- 胎児頻脈
- 呼吸苦、喘鳴、SpO2低下
- 皮膚の発疹
- 投与量を増量しても、子宮収縮が治らない
2)対応
上記の報告を行ったら、リトドリン点滴の投与中止や続行を相談・検討します。
中止、続行いずれの場合も副作用が憎悪していないか、軽快しているか観察していきます。
点滴の速度が30ml/hほどになると、点滴による体内の水分量も増えていきます。心負荷がかかりやすくなり、肺水腫などの重篤な副作用も起きやすくなりるので、心拍数が増加している時は点滴の濃度と速度の調整も必要な対応です。
肺水腫・心不全が疑われる時は、速やかに酸素や利尿剤を投与できるように準備します。
胸部X線撮影の確認も取れると良いでしょう。重篤な不整脈の所見がみられる時は心電図モニタリングをして、抗不整脈薬の準備をしましょう。
5.患者・家族への説明で伝えたいポイント
1)事前説明の重要性
- 薬剤の効果と治療の必要性を丁寧に説明する
- 起こりうる副作用について具体的に伝える
- 毎日24時間点滴を行うため、観察があることを強調する
- どんな小さな症状でも遠慮なく申し出てもらう
2)心理的サポート
- 「動悸が不安」「手が震えて心配」といった訴えに共感的に対応する
- 十分な休息がとれる環境を整える
- 家族との面会時間を調整し、精神的支えを確保する
- リラクゼーション技法や呼吸法を提供する
リトドリンは切迫流早産の治療において適切に使用すれば母児の安全を守る重要な薬剤です。しかし、動悸、頻脈、手指振戦などの軽度な副作用から、肺水腫や心不全といった重篤な合併症まで副作用も多岐に渡り、その使用には十分な注意が必要です。助産師として、薬剤の作用機序と副作用を正しく理解し、母体と胎児の状態を観察し、数値基準に基づいた客観的な評価をしながら、必要最小限の用量で効果を得ることが重要です。リトドリン点滴中の観察ポイントを押さえ、副作用の早期発見と適切な対応を行うことで、母児の安全を守ることができます。リトドリン投与中の母体へ高い質のケアを提供できるように、正しい知識を身につけ、安全で効果的な助産実践につなげていきましょう。
参考文献

【新人助産師と学生が押さえておきたい】CTG(NST)モニターの基礎知識|基線・基線細変動・一過性頻脈の見方をわかりやすく解説
- CTGモニター
- モニター判読
.png)
【助産師必見】超音波検査での胎児計測|基本項目と正しい計測方法を徹底解説
- 超音波検査
- 助産師によるエコー検査

“なんとなく”の指導はもう終わり。エビデデンスに基づく乳頭ケアの指導方法|妊婦さんの「やってみよう」を引き出す助産師の言葉は?
- 乳頭マッサージ
- 妊娠中

明日から使える!妊婦さんの不安を解消する「会陰マッサージ」指導のポイント|最新のエビデンスも解説
- 会陰部マッサージ
- 会陰部切開
- 経腟分娩
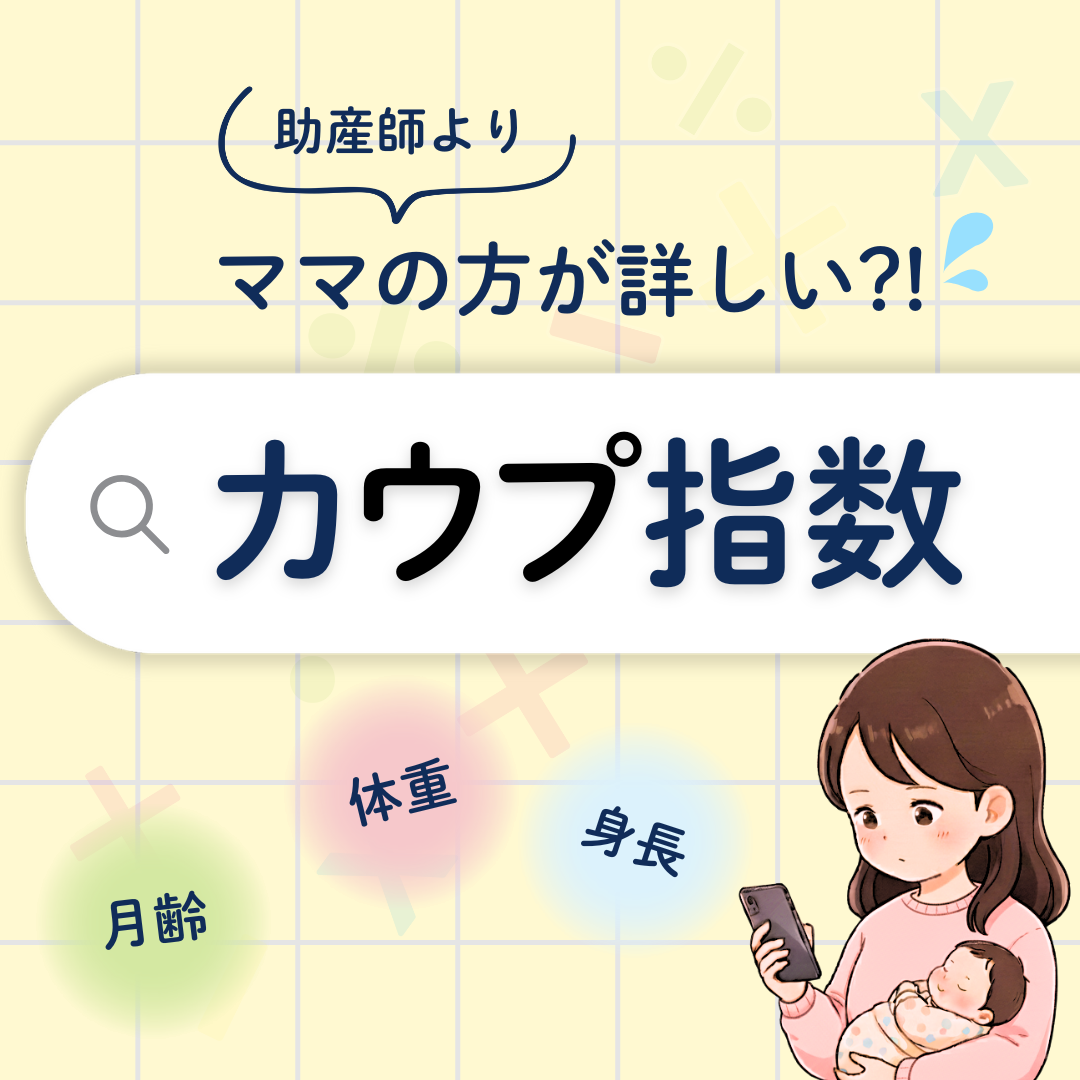
【月間3.8万検索の衝撃】ママの方が詳しいかも?助産師が知っておくべき“カウプ指数”の常識
- カウプ指数
- 月齢
- 乳幼児

Late Preterm児(後期早産児)とは?特徴・リスク・看護のポイントを徹底解説
- 早産
- Late Preterm児
- 後期早産児