
【永久保存版】妊娠中のマイナートラブルの原因と対策|助産師が知っておきたい保健指導のポイント
「マイナートラブル」とは、妊娠継続や胎児発育に影響しない妊娠中の不快症状をまとめた言い方です。
妊娠維持や胎児発育のため、また出産に備えて、妊婦の体内ではホルモンバランスが変化し、各臓器の生理機能が変化していきます。その変化によって身体の様々な部分に不快症状が現れやすくなります。
マイナートラブルの程度には個人差がありますが、稀に持病の増悪や新たな疾患による症状が隠れていることもあります。妊娠中だからといって「マイナートラブル」とひとまとめに片付けてはいけません。
妊婦の症状や生活背景を丁寧に傾聴し、正しい対策や対処法をお伝えしたり、母子健康連絡カードを活用したり、必要であれば専門機関に連携したりと、柔軟に対応できる力を身につけましょう。
浮腫(むくみ)
原因
浮腫が起こりやすくなる原因は大きく2つあります。
妊娠に伴い静脈系に蓄えられる血液量の増加、心拍出量の増加、平均血圧の低下、腎血流量の増加とそれに伴う糸球体濾過量の増加が起こるからです。
心拍出量の増加と血管拡張の程度のバランスがとれなくなり、浮腫につながります。 また、レニン・アンギオテンシン・アルドステロン系が活性化し、アルドステロンの増加により体液の増加、心拍出量の増加によって、腎臓でのナトリウムと水の貯留を上回るため浮腫になります。
妊娠末期には、細胞間質の膠質浸透圧の低下(体液が細胞外に漏れ出やすくなる)や、妊娠中の子宮による下大静脈の圧迫のため血流が悪くなり、浮腫が生じます。
対策
・下肢のマッサージ・運動
・下肢挙上・安静
・着圧ストッキングの装着
・塩分制限
静脈瘤
静脈の血流が停滞して血管が膨れてこぶのようになった状態を静脈瘤と言います。
自覚症状としては、下肢のだるさや痛み、むくみ、こむら返りがあります。
原因
静脈瘤の原因は大きく2つあります。
妊娠するとプロゲステロンの増加により血管壁の平滑筋細胞が弛緩し、静脈が拡張します。それに加えて妊娠に伴って循環血液量が増加し、増大した子宮に静脈が圧迫されることで下半身からの血液還流が障害されるためです。(①浮腫と同様の原理です)
対策
・座ったり動き回ったり休憩をとるなどこまめな体位変換
・下肢のマッサージ・運動
・着圧ストッキングの装着
・下肢挙上・安静
つわり
一言でつわりと言っても様々な症状があります。
いわゆる「吐きづわり」では悪心、嘔吐、食欲不振などがあり、「食べづわり」では何か口や胃に入っていないと気持ち悪くなるという場合もあります。
味覚や嗜好の好みが変わることもあります。
胎盤ができる妊娠15-16週を過ぎれば軽減、消失してくることが多いと言われていますが、個人差も大きいです。
この時期は、食事や水分がいつも通りに摂れなくても、母体に蓄えられている栄養で胎児は成長することができます。
原因
妊娠に伴うホルモン変化の影響で、消化管の蠕動運動の低下により食べ物が貯留するためと言われています。
また環境の変化への不適応も考えられています。
しかし、根本的な原因の詳細は未だに解明されていません。
つわりの増強因子として、不安や緊張などの精神的なストレスや換気不足、高温多湿、騒音といった環境要因が挙げられます。
対策
・こまめな水分摂取(ジュースや炭酸でもOK)
・食べたいときに食べたいものを食べられるだけ摂取
・空腹を避けるために、食べやすい小さなおにぎりやサンドイッチあるいはお菓子を携帯し て、お腹がすく前に摂取
・のどごしがよいものを摂取
・自分で無理してつくらず外食したり家族に作ってもらったり、宅食サービスなどを利用
・便秘対策として水分や食物繊維の摂取
・1日中嘔吐が続き食べられない、急激な体重減少、脱水症状などの体調不良時には受診
・環境や社会ストレスへの対処
・精神的なリラックスのために趣味や気分転換
・つわりに効くツボ(内関、足の三里)
口腔内の不快
口が粘つく、よだれ、歯が浮く感じがする、易出血、歯肉炎、う歯などのトラブルが起こりやすくなります。
原因
妊娠によるホルモン分泌の影響で口の中が粘ついたり、口内炎ができやすくなります。
また、つわりによって歯磨きが不十分だとう歯の原因にもなります。
妊娠初期のつわりの時期は、よだれの量が多くなる妊婦もいます。
さらに、妊娠するとリラキシンなどのホルモン作用によって骨盤をはじめ身体の各部分の骨と靱帯が緩むようになるため「歯が浮く」ような感覚になることがあります。
対策
・歯磨き粉をつけない歯ブラシでブラッシング
・うがい薬や殺菌作用のある緑茶で口腔洗浄
・ビタミンBを摂取(口内炎予防)
・歯科検診(つわりが落ち着いた時期がおすすめ)
胃食道逆流症状(胸やけ、げっぷ、胃もたれ)
原因
プロゲステロンによる食道下部の括約筋の弛緩と、増大した子宮によって胃内容物が停滞することが原因と考えられます。
また、つわりによって頻回に嘔吐することで胃食道逆流が起こるため胸やけが起こります。
対策
・こまめに少量ずつ摂取(分割食)
・食後すぐに横にならないようにすること
・就寝2時間前には食事を摂らないようにすること
・頭を少し高めにして休むこと
・高脂肪食やカフェイン、油ものを避けること
・消化によいものを摂取
便秘
原因
妊娠中のプロゲステロン増加による腸管蠕動運動が低下することや、増大した子宮による腸管圧迫、横隔膜の運動性の低下、内容物の消化管通過速度が低下し、胃内容物が停滞するために起こります。
腹筋の低下によって排便抑制がかかることも原因の一つとなります。
便秘が続くと、子宮収縮や腹部緊満感、腹痛の原因となるため、早めの予防や対処を心がける必要があります。
対策
・便意がなくても決まった時間にトイレへ行くこと
・便意を我慢しないこと
・排便時間の確保
・適度な運動
・起床時に水分や朝食をとること
・食物繊維・乳酸菌の摂取
・偏食を避けること
・下半身浴・シャワー浴で血行を促すこと
・緩下剤の検討
痔・脱肛
原因
循環血液量の増加や、増大した子宮の圧迫によって肛門周囲の静脈のうっ血が起こりやすく、痔を誘発・悪化させる原因になります。
また便秘により便が硬く出にくくなり、肛門が切れやすくなり、脱肛の原因となります。
対策
・水分や食物繊維、乳酸菌を十分に摂取し、便を硬くしない。
・香辛料・刺激物、アルコールは控える
・患部を清潔にして血液の循環をよくすること
・長時間の同じ姿勢を避けること
・脱肛は還納
動悸、息切れ
原因
妊娠中は循環血液量の増加、心拍出量の増加によって心臓への負荷がかかることや、貧血によって動悸が起こりやすくなります。
また、増大した子宮により横隔膜が挙上されるため、肺の体積が減少し、機能的残気量が減少します。
呼吸数を増加させたり、1回の換気量を増加させることによって補っていますが、その影響を受けて息切れしやすくなります。
どちらも運動や家事・仕事の作業、精神的なストレスによって増強することがあります。
ただし、妊娠中は心疾患や呼吸器疾患の増悪リスクが高まるため、他の疾患との鑑別も重要です。
対策
・息苦しくなった場合は立ち止まって深呼吸
・息が切れるような動きをせず休み休み動くこと
・ストレスをあまりためず神経質にならないこと
・貧血予防のために、鉄分やビタミンを摂取
頭痛
妊娠による身体や精神的な変化、環境や社会的役割の変化によって片頭痛や、緊張性頭痛が起こることがあります。
一方で、他の脳疾患などとの鑑別も必要です。妊娠に伴う生理的なもの、と片付けてしまうのではなく、頭痛に伴う症状や頭痛が起こるタイミングを問診することが大切です。
対策
・肩や首のマッサージ
・気分転換
・睡眠時間の確保
・適度な運動
・こまめな水分補給
・医師への相談
・鎮痛薬の検討
倦怠感(易疲労感、だるさ)
原因
妊娠に伴うプロゲステロンの増加、貧血によって、疲れやすくなります。
また精神面のストレスも疲労や倦怠感につながります。
対策
・休養をとり睡眠時間を確保
・一日の中でオンオフのメリハリをつけること
・規則正しい生活
頻尿・尿意切迫・尿失禁
頻尿の原因として、妊娠初期は子宮が大きくなることへの違和感や血液循環量、糸球体濾過量の増加による変化が影響します。
妊娠後期になるにつれて増大した子宮や胎児先進部が膀胱を圧迫したり、膀胱周辺がうっ血することで頻尿や尿意切迫感を感じます。
尿漏れの原因としては、骨盤底筋群の弛緩、増大した子宮による膀胱圧迫によって、くしゃみや咳の腹圧でも尿漏れを起こすことがあります。
対策
・時間をみてこまめにトイレに行くこと
・尿意を我慢しないこと
・骨盤底筋群体操
・尿漏れパッドの利用
手のしびれ
妊娠中の浮腫により、手根管や頸部を通る正中神経が圧迫されるためです。
正中神経が通っている骨で囲まれた小さなスペースに浮腫が出ると、神経が圧迫されて手指のしびれやピリピリした痛みが出現することがあります。
対策
・浮腫対策と同様
腰痛・背部痛
原因
腰痛や背部痛の原因は大きく分けると2つあります。
1つ目は、増加した体重や増大した子宮を保持するために腰背筋に過度の負担がかかるためです。
重心が前方に移動し、そのバランスをとるために腰椎の前弯が増強し(スウェイバック姿勢)同様に、腰背筋に負担がかかるため、腰や背部に痛みを生じます。
2つ目はエストロゲン、プロゲステロン、リラキシンなどのホルモンの増加によって骨盤内靱帯の弛緩が起こり、骨盤が不安定になるため、腰や背部に負担がかかり痛みが生じます。
対策
・急激な体重増加を避けること
・正しい姿勢
・長時間の立位を避けること
・適度な運動
・腰の保温、温案方
・骨盤支持ベルト
・前かがみになる作業を極力避けること
こむら返り
筋肉疲労によって起こる腓腹筋に起こる疼痛を伴う持続性のけいれんのことを「こむら返り」と言います。「つる」と表現されることも多いです。
原因
立位や歩行時に増大した子宮を保持するために腓腹筋に過度の負担がかかる(スウェイバック姿勢)ことや、下半身の血液循環が悪くなりうっ血状態になるため、こむら返りが起こりやすくなります。就寝時の腓腹筋は弛緩状態にあるため、夜寝ているときに起こることが多いです。
対策:
・下半身のマッサージ、ストレッチ
・下半身の保温
・カルシウム、ビタミンB1の摂取(筋肉疲労予防)
鼠径部痛・足の付け根が痛い・恥骨痛
原因
子宮が増大するにつれ、子宮円靱帯が引き伸ばされて、下腹部や鼠径部にチクチクとした痛みを感じることがあります。
児頭下降により恥骨や股関節が圧迫されることによっても痛みが生じます。
また分娩に向けてリラキシンなどのホルモンの影響で骨盤や関節が緩んでくることも痛みの原因となります。
対策
・股関節のストレッチ
・痛い方の足を下にして横向きに休むこと
・腰痛対策も参照
搔痒・かぶれ・乾燥・妊娠線
妊娠に伴う肝内胆汁うっ滞やプロゲステロンの影響によって掻痒感やかぶれ、乾燥が生じます。
また急激に腹部が増大することにより、皮膚が引っ張られ、皮下組織が断裂することで妊娠線ができやすくなります。
対策
・急激に体重を増加防止
・妊娠線予防クリーム(保湿クリーム)
・かゆみや乾燥部位をクーリング
帯下の増加
原因
エストロゲンの作用により、頸管粘液や膣分泌物が増加することがあります。
対策
・清潔(陰部の洗いすぎは注意)
・おりものシートは避けること
・通気性の良い下着を着け、汚れたらこまめに交換
不眠・眠気
原因
妊娠中のホルモンバランスの変化、増大した子宮による動きづらさ、息苦しさ、胎動、頻尿によって寝付きにくい、中途覚醒するといった不眠症状が起こります。
また、妊娠初期の一時的な症状で、多量に分泌されるプロゲステロンの影響によって眠気を感じやすくなることがあります。
対策
・昼間の適度な運動
・就寝前の入浴・マッサージやストレッチ
・寝心地のよい枕やベッド(布団)・クッションの利用
・ヒーリング、リラクゼーション音楽・アロマの活用
・寝やすい姿勢で休むこと
・昼寝をしすぎないようにすること
上記であげた症状以外にも、耳鳴りや耳閉感、脱毛など、かなりマイナーなトラブルに悩む妊婦も多くいます。
妊娠による影響だと知らずに心配になったり、日常生活や仕事に支障がでて困ったりすることもあるかもしれません。
マイナートラブルは生活の工夫や薬で軽減できる症状もありますが、妊娠が終わるまでずっと続く場合もあります。
さらに、マイナートラブルではなく他の疾患による症状である場合には、他科との連携や治療が必要となる場合もあります。
マイナートラブルで片づけるのではなく、症状からアセスメントし医師に報告や相談を行う力を身に着けることも重要です。
妊婦一人ひとりの症状や悩みに寄り添い、妊婦の状況にあった情報提供ができるようになりましょう。
また、妊娠は喜ばしいことであるという概念や周囲の祝福によって、不安や悩み、マイナートラブルの苦痛を打ち明けることができない妊婦も少なくありません。苦痛や不安をもつことは決していけないことではありません。揺れ動いたり、戸惑ったりする妊婦の素直な気持ちを受け止めましょう。
【参考文献】
1.岡庭豊ら. 病気がみえるvol.10 産科 第3版. メディカ出版
2.森恵美ら.助産師基礎教育テキスト2018年版 第4巻 妊娠期の診断とケア 日本看護協 会出版会
3.下肢静脈瘤|病気について|循環器病について知る|患者の皆様へ|国立循環器病研究 センター 病院
4.マイナートラブル

【助産師は知らなきゃ損】臨月のウォーキングはメリットが少ない?!明日の保健指導に活かせる
- 保健指導
- 陣痛誘発
- 自然陣痛

【新人助産師と学生が押さえておきたい】CTG(NST)モニターの基礎知識|基線・基線細変動・一過性頻脈の見方をわかりやすく解説
- CTGモニター
- モニター判読
.png)
【助産師必見】超音波検査での胎児計測|基本項目と正しい計測方法を徹底解説
- 超音波検査
- 助産師によるエコー検査

“なんとなく”の指導はもう終わり。エビデデンスに基づく乳頭ケアの指導方法|妊婦さんの「やってみよう」を引き出す助産師の言葉は?
- 乳頭マッサージ
- 妊娠中

明日から使える!妊婦さんの不安を解消する「会陰マッサージ」指導のポイント|最新のエビデンスも解説
- 会陰部マッサージ
- 会陰部切開
- 経腟分娩
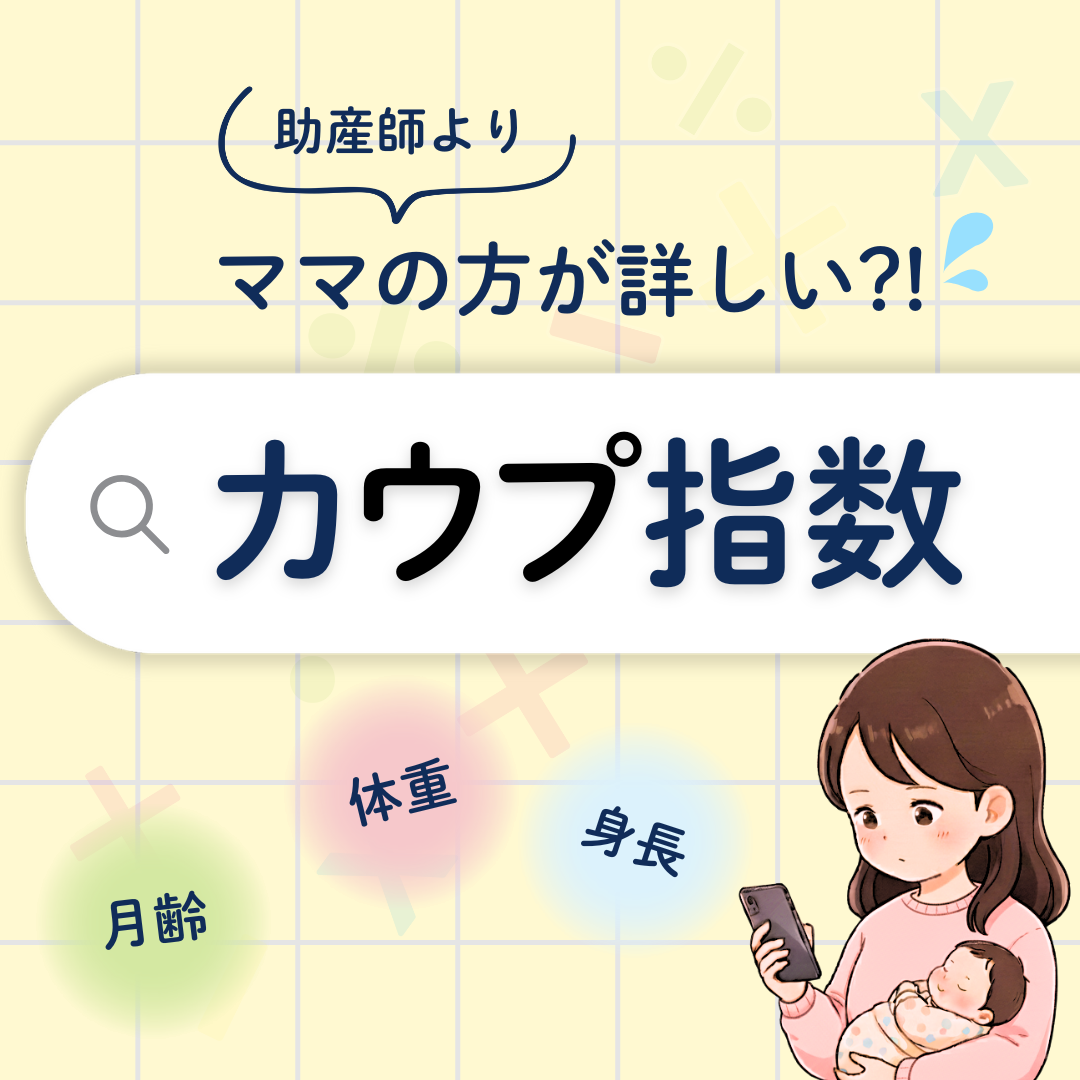
【月間3.8万検索の衝撃】ママの方が詳しいかも?助産師が知っておくべき“カウプ指数”の常識
- カウプ指数
- 月齢
- 乳幼児