
夜泣きに悩むママが安心できる場所を、もっと身近に助産師ができること
- 夜泣き
- 夜間授乳
新潟県初の夜間子育て支援「ヨナキリウム」
新潟市西蒲区の巻駅前に2025年7月オープンした夜泣きカフェ「ヨナキリウム」は、『よなきごや(著かねもと)』という漫画をモデルに、夜泣きに悩むママたちに手を差し伸べたいという思いから生まれた交流スペースです。
サービス概要
毎週水曜日の午後10時から翌朝6時まで、まさに夜泣きで困る時間帯に交流スペースを提供しています(一時預かりや託児はなし)。水族館をイメージした落ち着いた空間で、授乳室や仮眠室を完備しており、ミルクや離乳食、オムツも販売しているため、手ぶらで訪れても安心して育児ができるよう配慮されています。
スタッフ体制
施設には子育て経験のある女性スタッフが2人常駐し、育児に関するアドバイスを受けることも可能です。これにより、ママたちが孤独を感じることなく過ごせる環境が整えられています。
設立の背景
この取り組みを始めたWHALETAILの滝沢日向子代表も、自身の子どもの夜泣きで大変な経験をした一人です。「少しでもくつろげて、心の余裕をちょっと取り戻して、子どもを可愛いと思える、向き合ってあげられるような場所を提供できたら」との思いから立ち上げられました。
.jpeg)
ママたちの本音
ヨナキリウムの内覧会で聞かれたママたちの声には、
「早く朝にならないかな、夜が怖いなと、一緒に泣いていたこともあった」
「暗闇で泣いている赤ちゃんを一人であやすのは結構大変でメンタルにくる」
というような「夜が怖い」という言葉がありました。夜泣きを経験したママなら、誰もが感じる切実な気持ちです。夜間の育児は、昼間とは全く違う重圧があります。「家族は仕事で疲れてるから」と気を遣ってなかなか頼れない、泣き止ませようと外を出歩きたいけど、泣き声が目立つし、人目も気になって出られない。結局、赤ちゃんと二人きりの世界で「なぜ泣き止まないの?」という疑問、不安、焦燥がぐるぐる回る時間を過ごしているママも多いはずです。
夜間支援の必要性
出産後の女性は、ホルモンバランスの急激な変化、慢性的な睡眠不足、育児への不安と疲労など、複数の要因が重なることで心身ともに不安定な状態に陥りやすくなります。特に夜間は、一人で赤ちゃんと向き合う時間が長く、孤独感や不安感が増大しやすく、精神的に最も脆弱になりやすい時間帯といえます。前述したママたちの本音がそれを表しています。しかし、子育て支援施設の多くは日中の営業が中心であり、このようなニーズに十分応えられていないのが現状です。
助産師の視点から見たヨナキリウムの意義
予防的介入の観点
産後の精神的不調は、早期発見・早期介入が極めて重要です。ヨナキリウムのような施設は、ママたちが追い詰められる前に相談できる場として、予防的介入の役割を果たしています。これは、深刻な産後うつや育児ノイローゼを未然に防ぐという点で、公衆衛生上も大きな意義があります。産後うつの発症率は10-15%と言われていますが、軽度の精神的な不調を含めると、もっと多くのママが何らかのサポートを必要としています。夜間に利用できる施設があることで、症状が重篤化する前に適切な支援につなげることができます。
ピアサポートの効果
ヨナキリウムのもう一つの大きな意義は、同じような体験・経験をしているママ同士が出会える場を提供していることです。専門職によるサポートも重要ですが、同じ立場の人からの支援(ピアサポート)には、また違った力があります。「私だけじゃなかった」「みんな同じような悩みを抱えているんだ」という気づきは、ママたちの心を軽くし、孤独感を和らげます。これは、助産師などの専門職だけでは提供できない、とても貴重なサポートになります。
心の安全網としての価値
夜間に開いている支援施設があることの意義は計り知れません。実際に利用しなくても、「困った時にはあそこに行けば大丈夫」「利用できる場所がある」という安心感そのものが、ママたちの心の負担を軽減する力になります。

孤立しない子育て環境を目指して
子育てを取り巻く環境は、時代とともに大きく変化しています。核家族化の進行や地域との関係の希薄化により、「夜間に頼れる人がいない」と感じながら育児に向き合っているママたちは少なくありません。特に夜の時間帯は、身体的・精神的な疲労が重なるため、「誰かに話を聞いてほしい」「少しでも休みたい」といった切実な思いが高まる時間でもあります。こうした中で、「ヨナキリウム」のような場所は、子育ての孤立を防ぐために欠かせない支援の拠点となります。同じような経験を持つ人と出会い、「自分だけじゃなかった」と実感できることは、ママたちにとって大きな安心と励ましにつながります。
孤立しない子育て環境として、
- 夜間にも対応可能な相談窓口が設置されている(オンライン・チャット含む)
- 保護者同士が気軽に集い、語り合える安心・安全な場がある
- 地域の子育て支援に関する情報の積極的な収集と発信がある
- 夜泣きや乳幼児の睡眠に関する正しい知識の普及と啓発がされている
- 「こんなこと聞いてもいいのかな」とためらわず相談できる雰囲気がある
- 匿名や短時間でも気軽にアクセスできる相談体制が整備されている
といったような環境が整うことが望まれます。
子育てしやすい社会づくりのための助産師の役割
子育て中にSOSを発信できる場所があることは、母親にとって大きな心の支えとなります。ヨナキリウムのような取り組みを知ることで、孤立しない子育て環境の重要性、そしてそれを地域全体で支える意義を改めて実感させられます。助産師は、医療の専門家としての知識と経験を活かすと同時に、一人の女性として母親の気持ちに寄り添い、誰もが安心して子育てできる環境づくりに積極的に関わっていく必要があります。ヨナキリウムのような支援の場が全国に広がり、どの地域の母親も不安なく夜を迎えられるようになるためには、助産師による継続的な関わりも不可欠です。助産師一人ひとりが、自分にできることから行動を始めていけば、その小さな一歩がやがて大きな社会の変化を生み出すことへ繋がります。すべての母親が孤立することなく、子育てを前向きに楽しめる社会の実現を目指して、支援の輪が、今後さらに広がっていくことが期待されます。

夜泣きに悩むママが安心できる場所を、もっと身近に助産師ができること
- 夜泣き
- 夜間授乳

【助産師の最新知識】腕に埋め込む避妊?知っておきたい避妊インプラントの基本
- 避妊インプラント
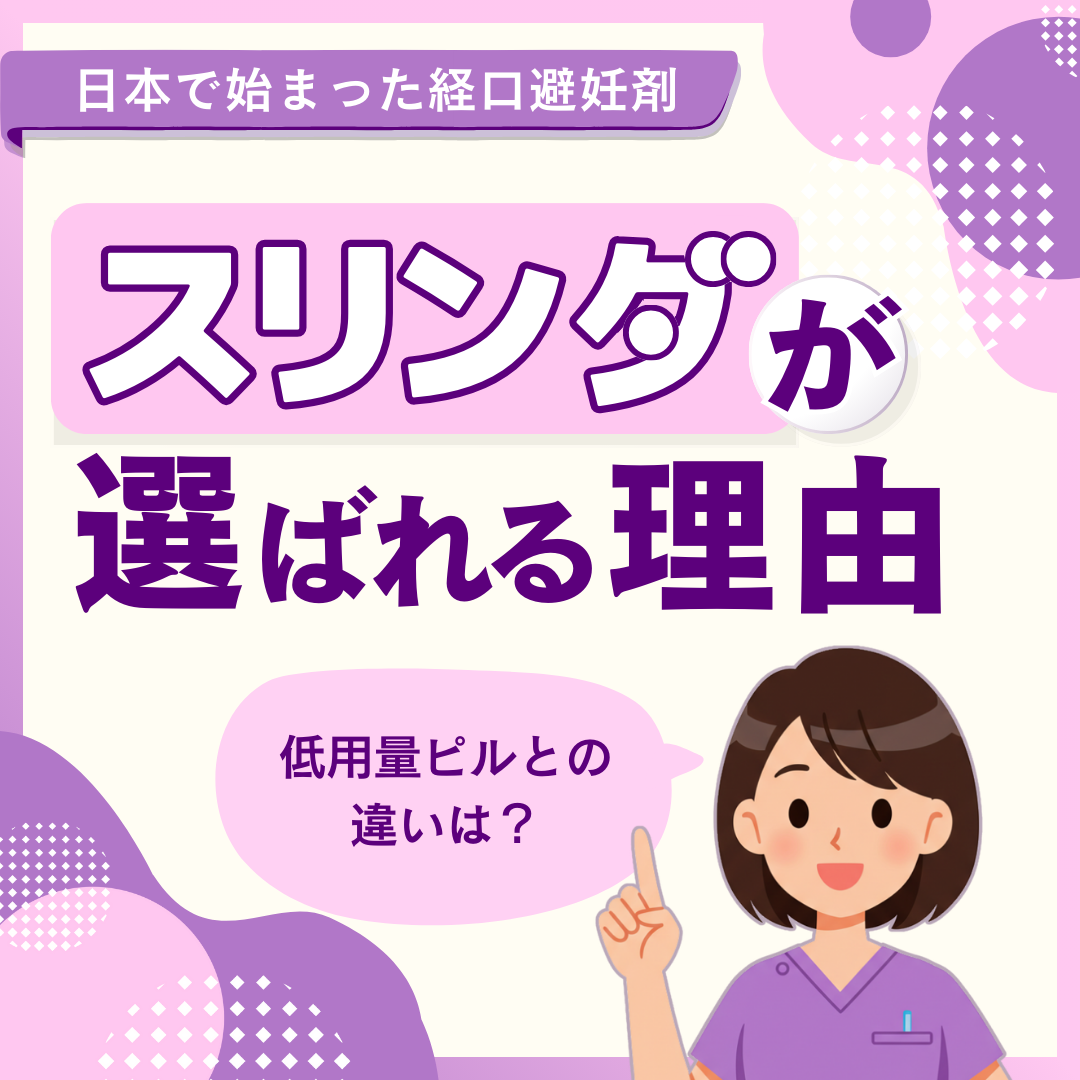
【助産師なら知っておきたい】低用量ピルとの違いは?スリンダの特徴と“選ばれる理由”を解説
- 低用量ピル
- 避妊薬
- スリンダ
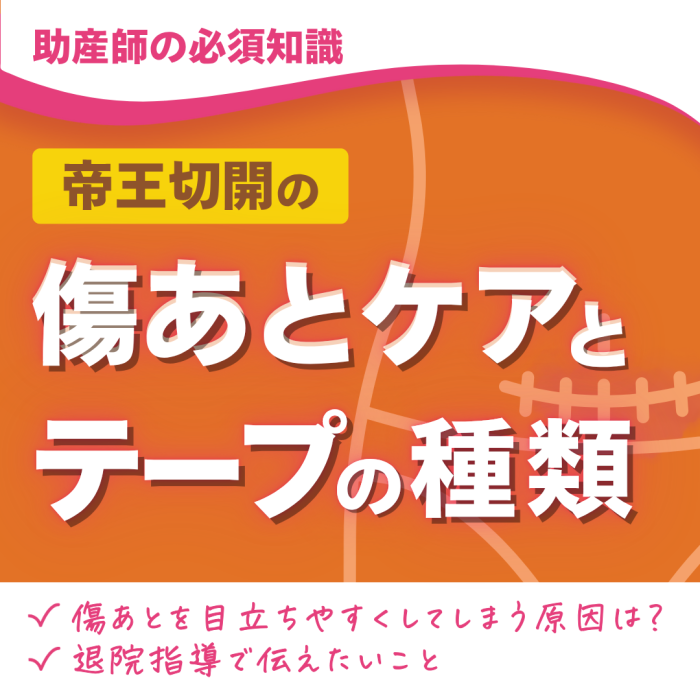
【助産師の必須知識】帝王切開の傷あとケアとテープの種類|傷あとを目立ちやすくしてしまう原因は?|退院指導で伝えたいこと
- 帝王切開
- 傷痕ケア
- 退院指導
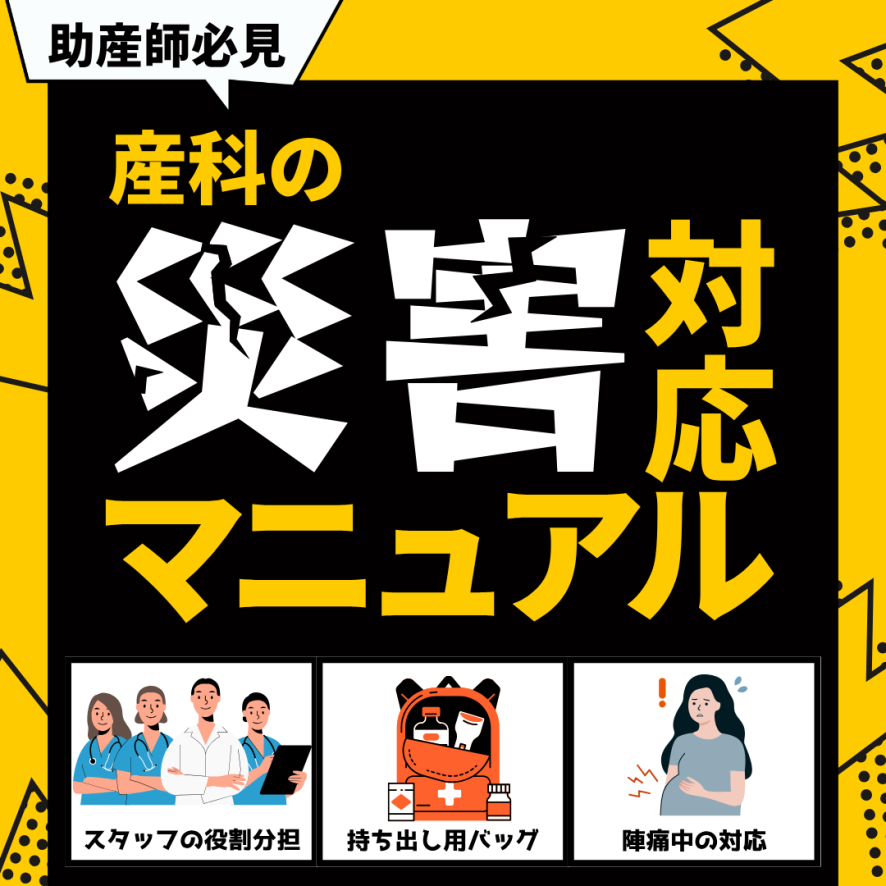
【助産師必見】産科の災害対応マニュアル|スタッフの役割分担・持ち出し用バッグ・陣痛中の対応
- 災害対策
- 医療安全
- 退院指導

【助産師必見】胎児疾患のある妊婦と家族を支える|NPO法人 親子の未来を支える会
- 胎児疾患
- 胎児異常
- 先天異常