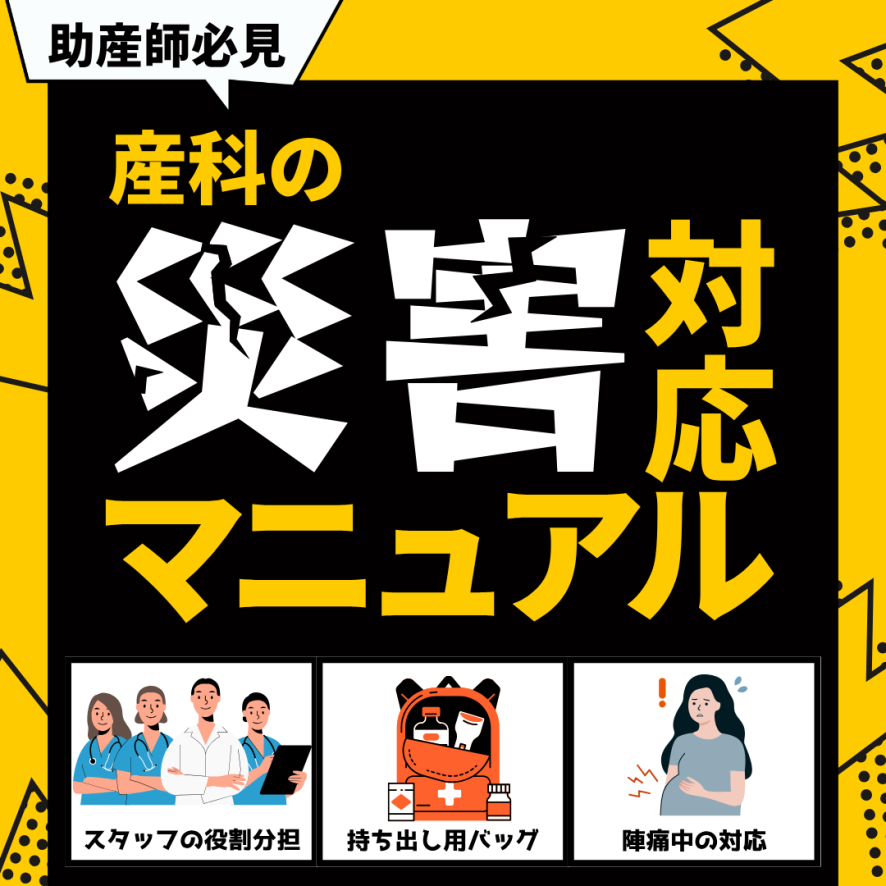
【助産師必見】産科の災害対応マニュアル|スタッフの役割分担・持ち出し用バッグ・陣痛中の対応
- 災害対策
- 医療安全
- 退院指導
地震・台風・豪雨・停電・火災……私たちが働く医療現場も、いつどんな災害に見舞われるかわかりません。とくに妊産婦、新生児は災害弱者であり、災害時の混乱の中で最も配慮が必要な存在です。助産師は、分娩や母子ケアの専門職であると同時に、有事には「現場の判断者」としての役割を担います。どのタイミングで避難させるか、医師不在時に何を優先すべきか。そんな判断を瞬時に求められる状況が、実際に起こります。災害時に母子の命を守るために、助産師が知っておくべき対応を一緒に確認していきましょう。
1.スタッフの役割分担|災害時の混乱を最小限にするために
災害発生後、どれだけ早く安全確認と初期対応を行えるかが、その後の混乱を大きく左右します。まずは安全確認、安全確保をしましょう。災害時にスタッフが慌てずに必要な行動をできるようにアクションカードを取り入れてる病院も多いです。業務に入る前に、今日のメンバーの場合の自分の役割と必要な行動は何か、シュミレーショントレーニングを日々行うことで、あらゆる役割の初期対応をイメージできるようになります。
【アクションカードの役割例】
・リーダー役(師長または経験年数が多い助産師)
→館内放送や情報収集、部長や医師との連携、消防・救急との連携、避難経路の確認、人数把握、方針決定
・患者安全確認役
→妊産婦・新生児の安全確認、ケガの有無をチェック
・物品確認・ライフライン対応役
→持出し物品、非常灯、電源、水道、トイレなどの機能確認
・記録係
→発災時からの記録を開始し、検証
初期消火や防災シャッターなどの設備を作動させるには、日頃の訓練が必要です。定期的にアクションカードを使用した避難訓練を実施し、それぞれの役割がスムーズに実行できる体制を整えておきましょう。夜勤や休日など、スタッフが最小限の場合には1人が複数の役割を担う必要があります。事前に最低限の優先順位(命の安全確保→情報収集→物品確認→記録)を共有し、判断基準をマニュアル化しておくことが重要です。
2.非常用物品
災害時は一刻を争うため、すぐに持ち出せるようにバッグの準備は定期点検が非常に重要です。バッグはリュック型だと両手が空き、介助もしやすいです。
【妊産婦用】
・母子手帳、健康保険証
・携帯トイレ、生理用ナプキン
・マスク、消毒液
・タオル、ブランケット
・飲料水、非常食(授乳中でも食べられるもの)
【赤ちゃん用】
・おむつ、おしり拭き
・哺乳瓶
・乳児用液体ミルク、粉ミルク
・おくるみ
【分娩用】
・使い捨て手袋、マスク、キャップ、ガウン
・分娩セット
・ルートキープ用ボトル
・医薬品:アトニン、パルタン、トランサミン
・アンビューバッグ、マスク、パルスオキシメーター
・挿管セット
・ドップラー
・血圧計、体温計、聴診器
・ヘッドライト
・縫合セット
・分娩台帳、パルトグラムなど簡易記録用紙、ペン
・産婦の寝衣
・母子標識
【病棟用】
・外部連絡ツール(トランシーバーなど)
・管理日誌(患者一覧)
・緊急連絡網
・ヘルメット
・ホイッスル
物品はあくまでも一例です。それぞれの施設で何が必要か検討、確認してみましょう。
3.陣痛中・分娩中の妊産婦への対応
災害時、もっとも判断が難しいのが分娩進行中の妊産婦への対応です。今、移動すべきか、そのまま分娩介助するべきかの判断は、現場の助産師の判断に委ねられるケースもあります。
【対応のポイント】
・災害発生時は産婦のもとから離れない。
・状況を管理者に報告し、避難の必要性とその可否を検討する。
・原則は安全確保できる場所での分娩続行であり、明確な危険がない場合は、移動はせずその場で分娩介助、もしくは院内の安全な場所に移動して分娩管理を行う。
・すぐに分娩進行はしないと判断した場合は、早期に避難誘導をする。
・災害によりCTGモニターが使えなくなる場合もあるので、ドップラーやエコーなど簡易超音波機器で胎児心拍の確認ができるように物品を整えておく。
・無痛分娩や促進剤の中断、急速遂娩の必要性、弛緩出血や新生児仮死への対応などは医師に報告し、対応を相談する。
・母子標識を装着し、母子が離れないようにする。
・母子ともに低体温予防に努める
4.切迫早産で入院中の妊婦への対応
切迫早産で入院中の妊婦は、安静が必要であり、移動や環境の変化はリスクとなります。建物の損壊や火災などがなければ無理な移動は避け、病室内での安全確保を優先します。
【対応のポイント】
・点滴治療の中止と内服薬への切り替えの対応をあらかじめ決めておく
・子宮収縮抑制剤など、非常時にも投与が継続できるよう準備しておく
・リスクが高い場合は、最小限の移動にとどめることが基本
・歩行できない場合は、担架での搬送を検討
5.NICUに入院している新生児への対応
NICUに入院している新生児は、生命維持に高度な医療機器を必要とするため、日々の点検と避難する場合の対応を周知徹底しておきます。
【対応のポイント】
・コットや保育器は固定する。
・非常電源に接続されている。
・緊急用キャリー型保育器など災害時専用の搬送具を備えておく。
・必要に応じて、救急車やヘリコプターなど、適切な搬送手段を確保する。
・医療スタッフが主導しながら、面会中の家族に新生児の移動を一時的に協力してもらう。
産科における災害対応は、他の診療科に比べ、特殊な課題が多く存在します。また周産期医療センターやクリニックなど施設によっても役割が異なります。日頃から「もし今、この瞬間に災害が起きたらどうするか?」をチームで共有し備えておくことで、いざという時に慌てることなく冷静な行動が取れるようになります。助産師として母子の命を守るために、平時から災害に備える準備をしていきましょう。
参考文献
1)公益社団法人日本看護協会,改訂版分娩取扱施設における災害発生時の対応マニュアル作成ガイド,公益社団法人日本看護協会 2024

夜泣きに悩むママが安心できる場所を、もっと身近に助産師ができること
- 夜泣き
- 夜間授乳

【助産師の最新知識】腕に埋め込む避妊?知っておきたい避妊インプラントの基本
- 避妊インプラント
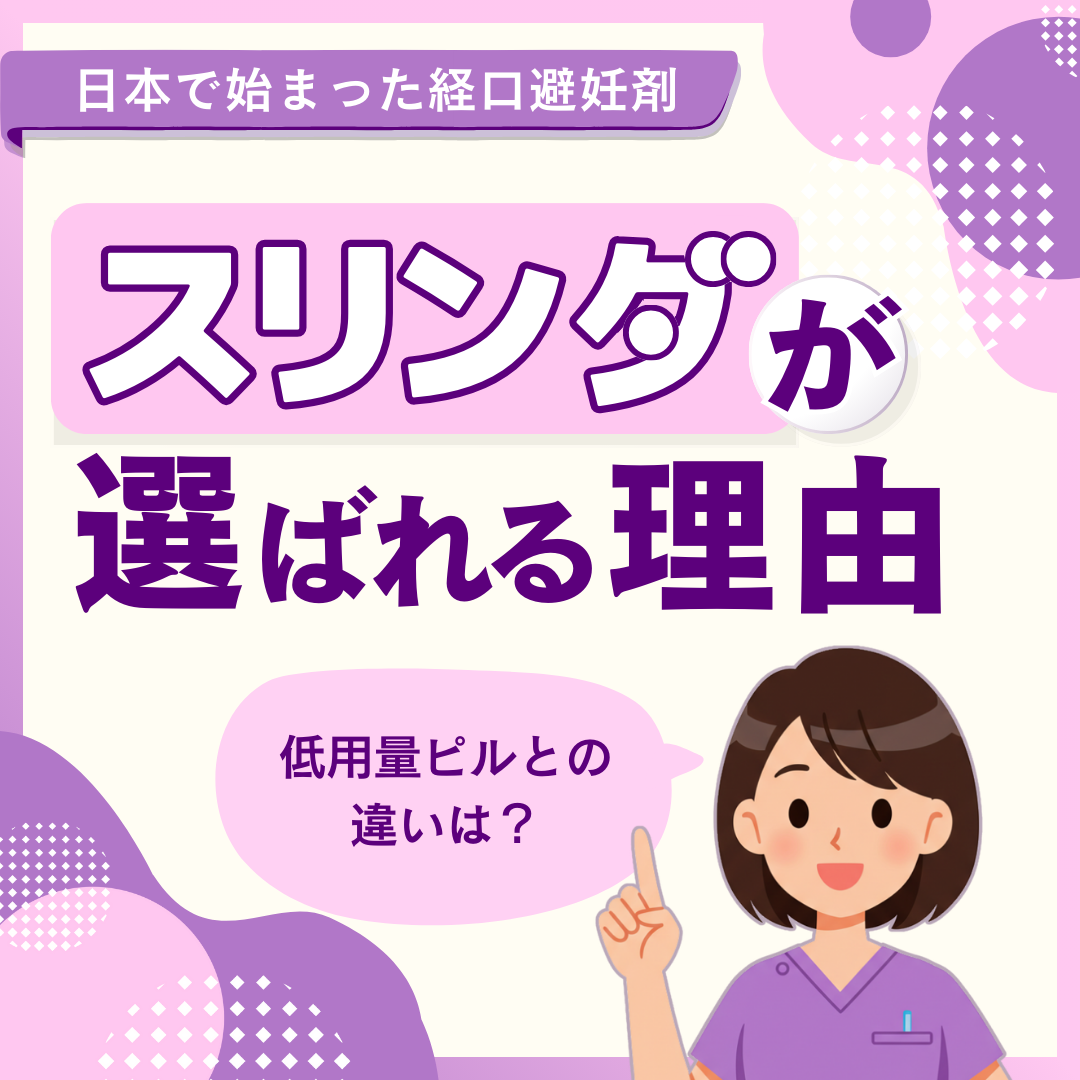
【助産師なら知っておきたい】低用量ピルとの違いは?スリンダの特徴と“選ばれる理由”を解説
- 低用量ピル
- 避妊薬
- スリンダ
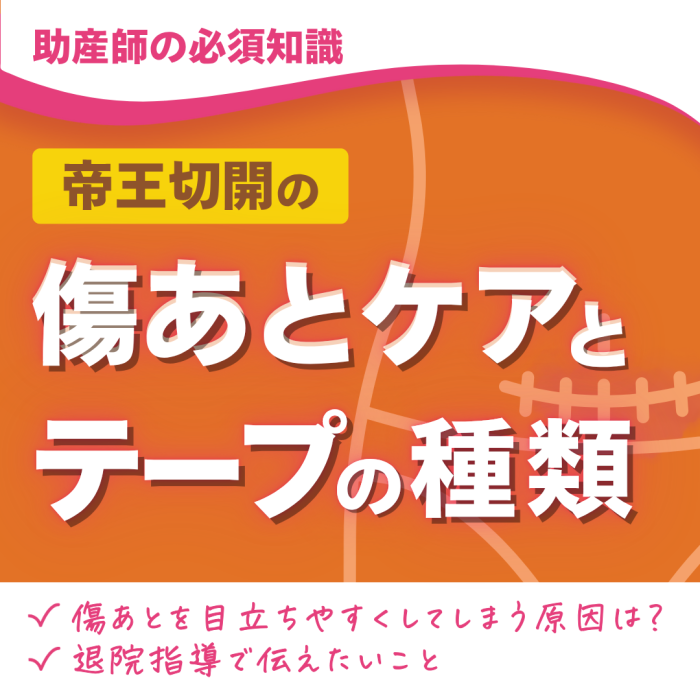
【助産師の必須知識】帝王切開の傷あとケアとテープの種類|傷あとを目立ちやすくしてしまう原因は?|退院指導で伝えたいこと
- 帝王切開
- 傷痕ケア
- 退院指導
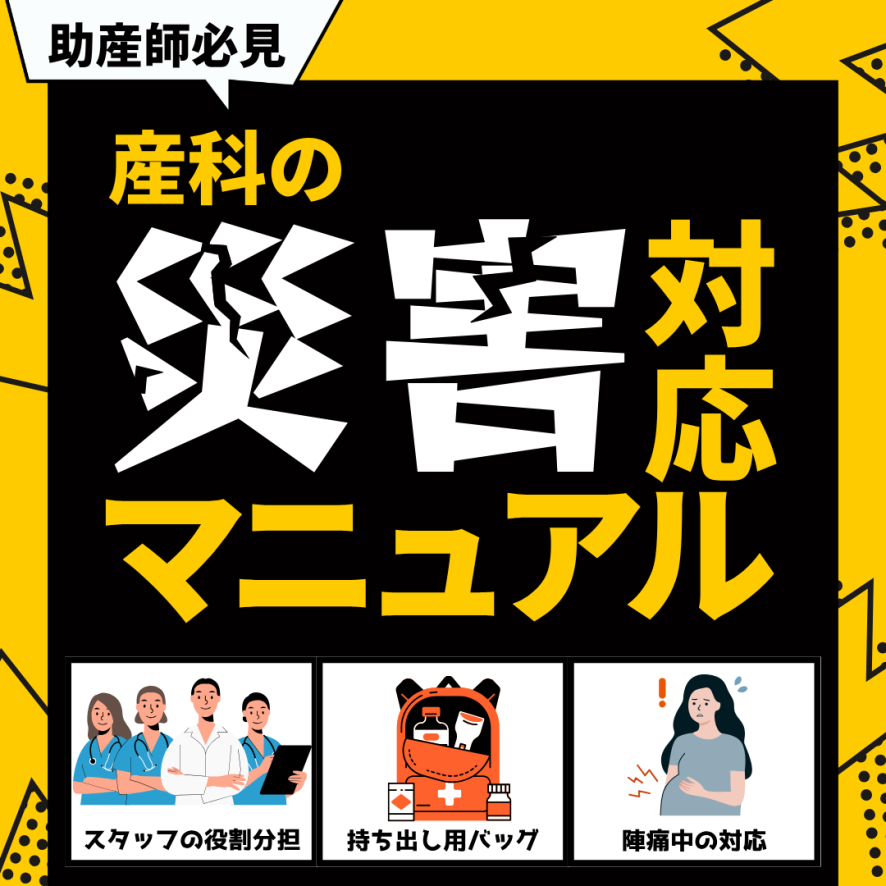
【助産師必見】産科の災害対応マニュアル|スタッフの役割分担・持ち出し用バッグ・陣痛中の対応
- 災害対策
- 医療安全
- 退院指導

【助産師必見】胎児疾患のある妊婦と家族を支える|NPO法人 親子の未来を支える会
- 胎児疾患
- 胎児異常
- 先天異常