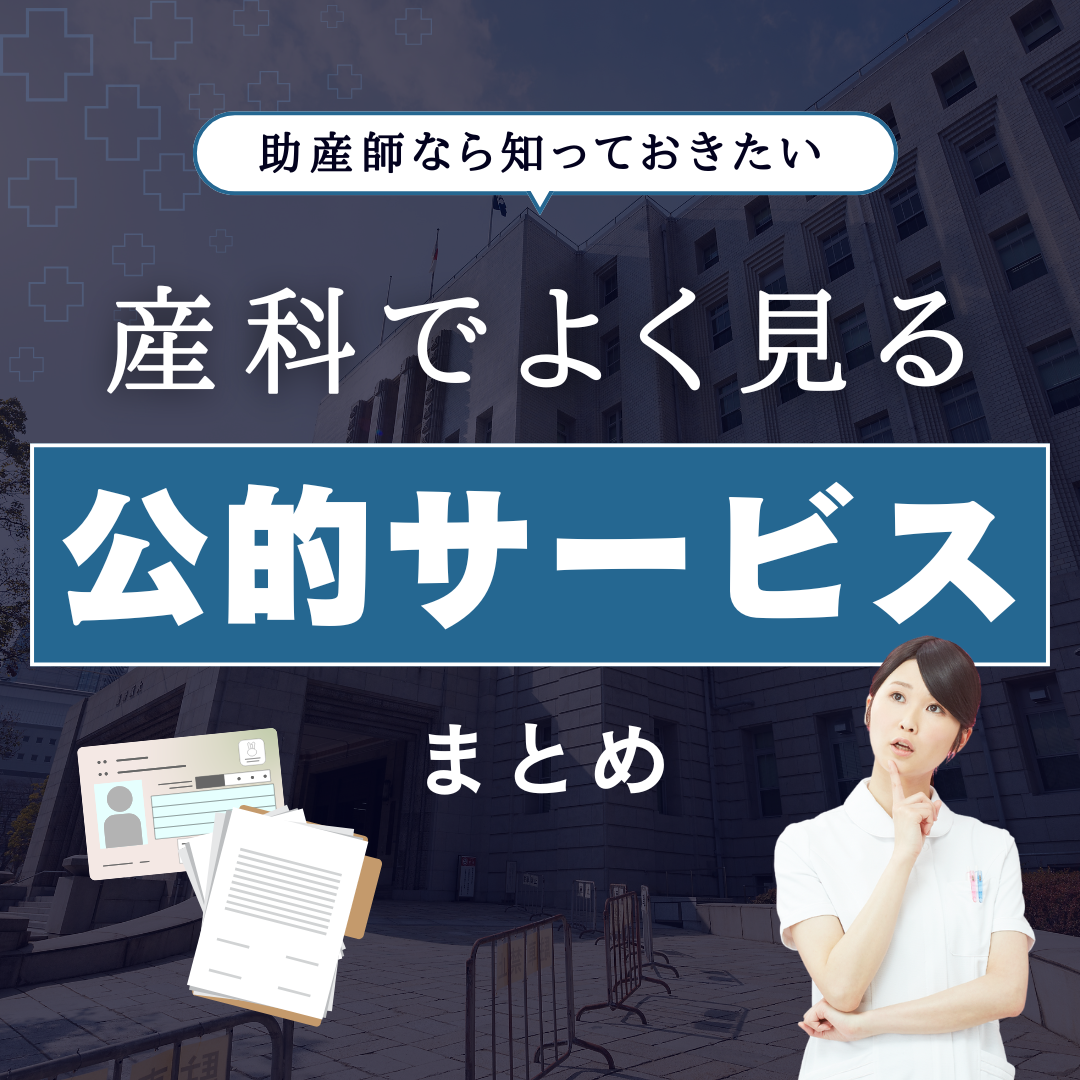
【助産師なら知っておきたい】産科でよく見る公的サービスまとめ
- マイナ保険証
- 産科医療保障制度
- 高額療養費制度
高額療養費制度とは?
高額療養費制度は、1ヶ月(1日から末日まで)に支払った医療費が一定の基準額(自己負担限度額)を超えた場合、その超えた金額を支給する制度です。
対象となるのは健康保険適用の診療費や薬代、入院費などです。(入院中の食事代や差額ベッド代、先進医療にかかる費用は含まれません。)
〇自己負担限度額の計算方法
自己負担限度額は所得によって異なります。
自己負担額の計算は、以下のような基準があります。(70歳未満の方)
①区分ア 年収約1,160万円以上:月額252,600円+(医療費※1-842,000)×1%
②区分イ 年収約770〜1,160万円:月額167,400円+(医療費※1-558,000)×1%
③区分ウ 年収約370〜770万円:月額80,100円+(医療費※1-267,000)1%
④区分エ 年収約~370万円:57,600円(固定)
④区分オ 住民税非課税世帯:35,400円(固定)
※1医療費:1ヶ月にかかった医療費10割
これにより、収入が低い世帯ほど負担額が軽減される仕組みになっています。
〇高額療養費の支給申請
自身が加入している公的医療保険(健康保険組合、共済組合など)に高額医療費の支給申請書を提出または郵送することで支給を受けることができます。
限度額適用認定証とは?
支払った医療費は高額療養費制度で払い戻されるものの、支給されるまでには3ヶ月ほどかかり、一時的な支払いであってもその出費は大きな負担になります。
高額な医療費の支払いをせず、初めから自己負担限度額の支払いのみをするために必要な書類が「限度額適用認定証」です。
医療費が高額になることが事前に分かっている場合は、あらかじめ「限度額適用認定証」を取得します。
そして医療機関に提示することで、窓口での支払いを自己負担限度額までに抑えることができます。
この認定証を提示して支払いをすれば、あとで高額療養費の支給申請をする必要もありません。帝王切開などで入院費用が50万円かかった場合でも、所得に応じた限度額までの支払いで済むようになります。
〇取得方法
限度額認定証は、加入している健康保険の窓口(市役所、会社など)で申請することで発行されます。
必要な書類は健康保険証、身分証明書(場合による)所得証明書類(場合による)です。

マイナ保険証とは?
「マイナ保険証」とは、マイナンバーカードを健康保険証として利用する仕組みで、健康保険証として利用できるように登録したマイナンバーカードのことです。
2021年よりマイナンバーカードを「健康保険証」として利用できるようになり、2024年12月2日より「健康保険証」が新規で発行されなくなるのと同時に、「限度額適用認定証」も廃止されました。
マイナ保険証を利用するには、事前に保険者(国保や社保)に紐づけをしておくことが必要です。
紐付けされたマイナ保険証を利用することで、医療機関は医療費を請求する健康保険組合を把握することができます。そのため、紐づけが正しく行われていないと、高額療養費の限度額適用が反映されない場合があります。
マイナンバーカードの健康保険証の利用申し込みは、
・医療機関(顔認認証付きカードリーダーから申し込める)
・スマートフォンから(マイナポータルのアプリから申し込める)
・セブン銀行(ATM画面のマイナンバーカードでの手続き→健康保険証利用の申し込み)
で行えます。
〇利用方法
1.マイナンバーカードを窓口にある顔認証付きのカードリーダーで受け付けします。
2.顔認証または、4桁の暗証番号入力のどちらかを選択して、本人確認を行います。
3.医師、薬剤師に提供する情報(過去の診療・薬剤情報、特定健診情報)について「同意する」「同意しない」を選択して、受付終了です。
〇マイナ保険証のメリット
限度額認定証の事前申請が不要:マイナ保険証を提出すれば、限度額適用認定証がなくても窓口負担が自己負担額まで軽減されるようになり、高額な医療費を一時的に自己負担したりしなくて済むようになります。
手続きの簡素化:限度額適用認定証の書類を取得したり、提出する手間がなくなり、煩雑さが軽減されます。
即時適用:急な入院や出産でもスムーズに限度額が適用されるため、費用の負担が一時的に膨らむ心配がありません。
より良い医療の提供:処方された薬剤や健診などの情報提供に同意をすれば、お薬手帳がなくても過去の情報を医師、薬剤師が共有することができます。薬剤の重複投与などのリスクを避けることができ、スムーズに適した医療を受けることができます。
確定申告にも便利:マイナポ―タルで医療費通知情報を入手できるため、医療費控除の確定申告が簡単に行えます。
転職時の登録が不要:就職や転職に伴う再度の登録は必要ありません。保険者への加入届け出は必要です。
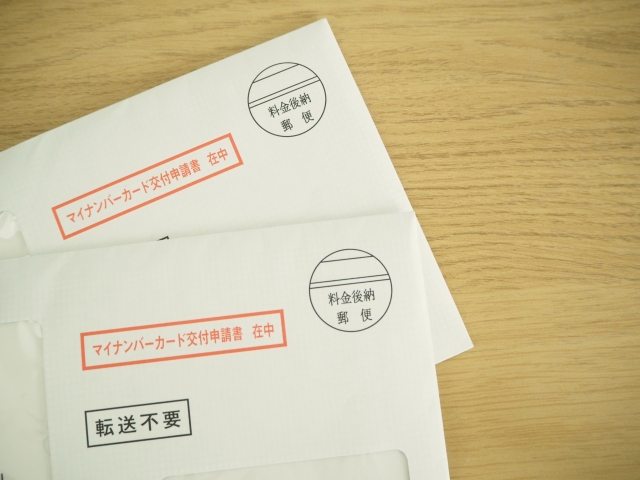
産科医療補償制度について
出産に関連する万が一の事態に備える「産科医療補償制度」。
この制度は、分娩時の予期せぬ重度脳性麻痺に対し、新生児やその家族に対して一定の補償を行う、医療機関が加入する制度です。
<創設の背景>
分娩時の医療事故では、過失の有無の判断が困難な場合も多く、裁判で争われる傾向があります。このような紛争が多くあることが産科医不足の理由の一つとされています。そのため産科医不足の改善や産科医療提供体制の確保が重要な課題とされ、より安心して産科医療を受けられる環境整備の一環として平成21年1月に創設されました。
<産科医療補償制度の意義>
この制度は、
・医療機関と産婦双方の安心を高めるものであり、分娩に関連して発症した重度脳性麻痺児 とその家族への迅速な経済的負担の補償や支援を速やかに行うこと
・原因分析を行い、同じような事例の再発防止のための資料提供を行う
・紛争の防止や早期解決および医療の質の向上を図る
以上のことを目的としています。
<補償について>
〇運営組織
日本医療機能評価機構
〇加入方法
産科医療補償制度に加入している分娩機関であれば妊産婦へ登録証が配布されます。
妊産婦は出産予定の分娩機関から登録証の書類をもらって提出すれば医療機関が手続きを行います。
産科医療補償制度専用コールセンターに連絡して登録証をもらうこともできます。
原則として在胎週数22週に達する日までに妊産婦情報を登録します。
〇加入状況
日本国内のほぼ全ての分娩機関が制度に加入しています。
〇対象者
①2015年~2021年までに出生の子ども:在胎週数32週以上出生体重1,400g以上または28週以上で所定の低酸素状態を満たしている。
2022年1月以降に出生した子ども:在胎週数28週以上(出生体重にかかわらず)
②身体障害者手帳1・2級相当の脳性まひ
③先天性や新生児期の要因によらない脳性まひ
以上3つの基準をすべて満たし、運営組織が「補償対象」として認定した場合に補償金を支払います。分娩機関に過失がなくても補償金が支払われます。
〇補償金額
最大3,000万円を支給(準備一時金600万円+補償分割金2,400万円)
〇掛金について
掛金は分娩1件ごとに分娩機関が掛金を負担をし、出産費用にこの補償制度の掛金が含まれています。出産育児一時金に掛金相当額が加算されて支給されるため、妊産婦の実質的な負担はありません。令和4年1月以降は1万2千円となっています。
〇補償申請の期限
子どもの満1歳の誕生日から満5歳の誕生日までです。
そのため、登録証は母子手帳と共に出産後も大切に保管をしてもらいます。
満5歳の誕生日を過ぎると補償申請を行えません。

まとめ
高額療養費制度や限度額認定証、さらに産科医療補償制度などの公的サービスは、医療費の負担を軽減したり、もしもの事態に備える強い味方です。これらの制度への知識があるとママたちの経済的な心配や不安に対して役立つことがあると思います。
また赤ちゃんを抱っこしたり、大きなお腹を抱えての書類申請や支払い手続きも大変です。
手続きが大幅に簡略化されるマイナ保険証の説明も事前に伝えられるとよいですね。
参考文献
1)厚生労働省,「高額療養費制度を利用されるみなさまへ」,
厚生労働省ホームページhttps://www.mhlw.go.jp/content/000333279.pdf(参照2024年12月2日)
2)全国健康保険協会「高額な医療費を支払ったとき(高額療養費)」,
全国健康保険協会ホームページ https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3030/ (参照2024年12月2日)
3)全国健康保険協会,「医療費が高額になりそうなとき」,
全国健康保険協会ホームページ https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3020/ (参照2024年12月2日)
4)厚生労働省,「マイナンバーカードの健康保険証利用について」,
厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html (参照2024年12月2日)
5)公益財団法人 日本医療機能評価機構,「産科医療補償制度」,
公益財団法人 日本医療機能評価機構ホームページ http://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp/ (参照2024年12月2日)

夜泣きに悩むママが安心できる場所を、もっと身近に助産師ができること
- 夜泣き
- 夜間授乳

【助産師の最新知識】腕に埋め込む避妊?知っておきたい避妊インプラントの基本
- 避妊インプラント
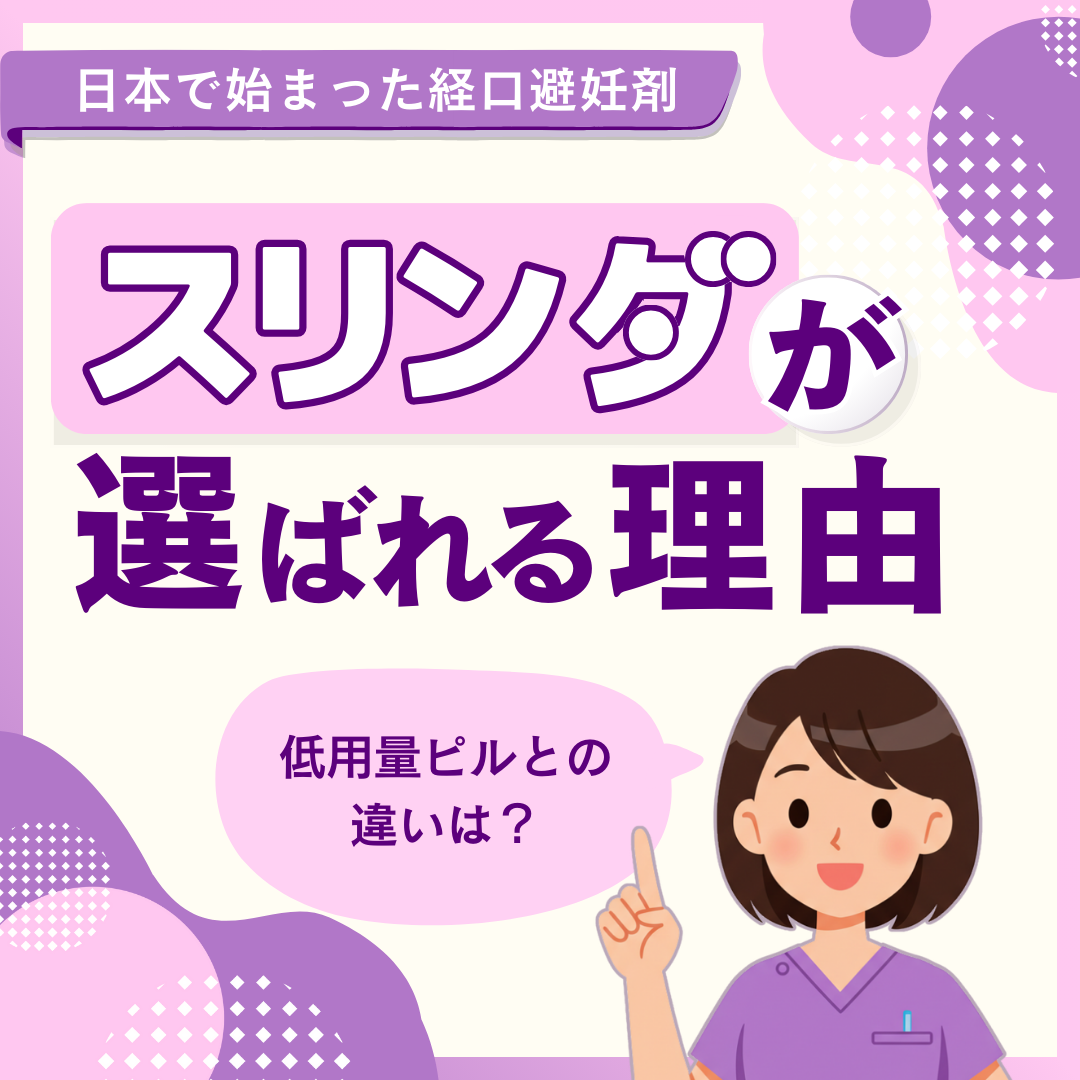
【助産師なら知っておきたい】低用量ピルとの違いは?スリンダの特徴と“選ばれる理由”を解説
- 低用量ピル
- 避妊薬
- スリンダ
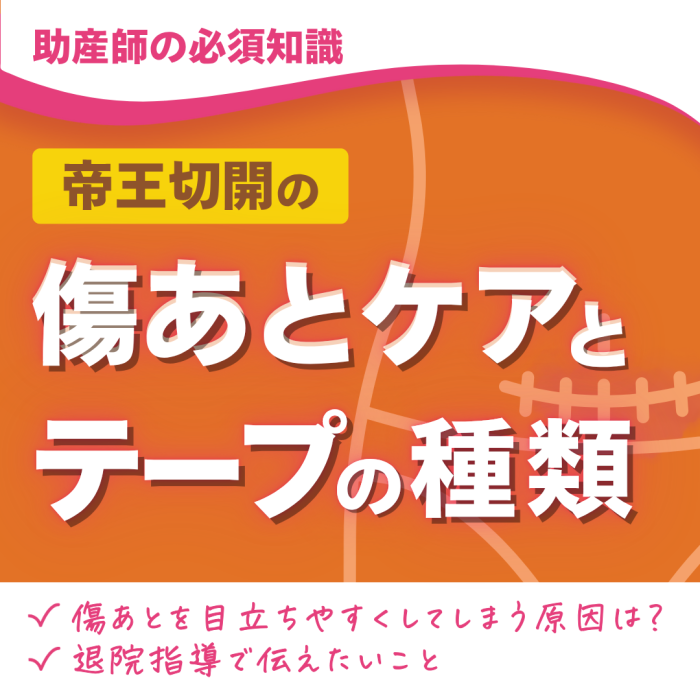
【助産師の必須知識】帝王切開の傷あとケアとテープの種類|傷あとを目立ちやすくしてしまう原因は?|退院指導で伝えたいこと
- 帝王切開
- 傷痕ケア
- 退院指導
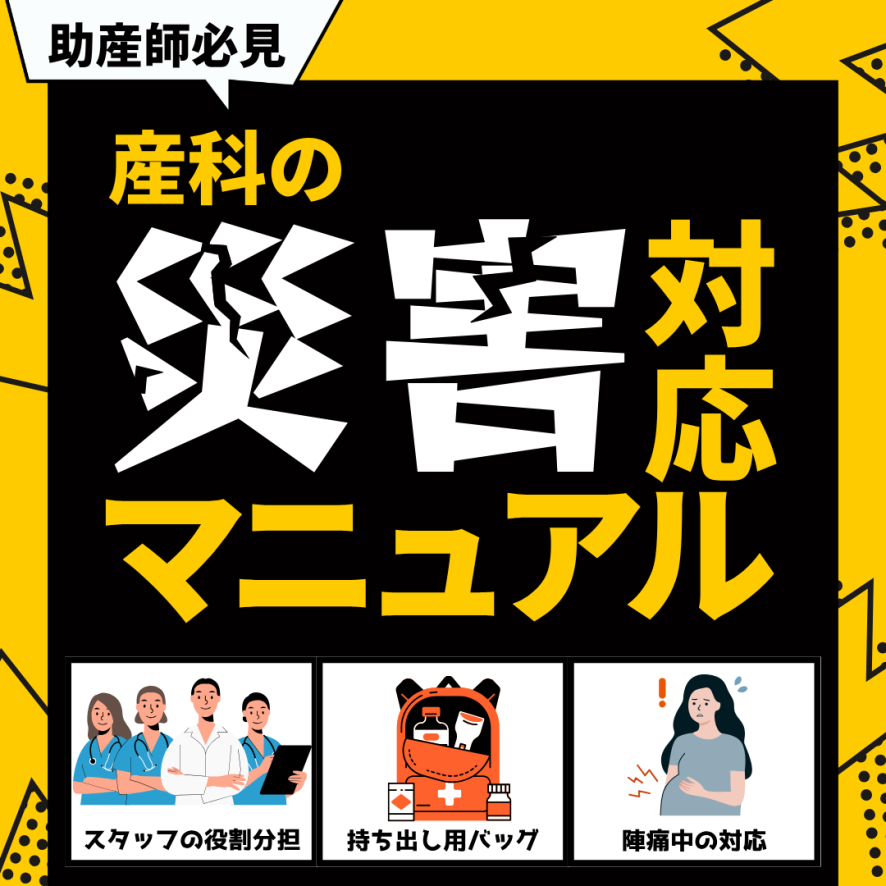
【助産師必見】産科の災害対応マニュアル|スタッフの役割分担・持ち出し用バッグ・陣痛中の対応
- 災害対策
- 医療安全
- 退院指導

【助産師必見】胎児疾患のある妊婦と家族を支える|NPO法人 親子の未来を支える会
- 胎児疾患
- 胎児異常
- 先天異常