
【助産師必見】国内2箇所目の赤ちゃんポストと内密出産|女性と赤ちゃんのその後は?
- いのちのバスケット
- こうのとりのゆりかご
- 内密出産
赤ちゃんポストは、親が育てられない乳幼児を匿名で受け入れる施設です。日本では、2007年に熊本市の慈恵病院に初めて設置されました。ポストは外壁に設置され、扉を開けると保温機能や酸素吸入機を備えた保育器があり、赤ちゃんを預けることができます。熊本市の発表によると設置から2023年度までに預けられた赤ちゃんは累計で179人となりました。赤ちゃんポストに赤ちゃんが預けられると院内職員が駆け付け、医師による健康状態の観察や児童相談所への連絡、その後の養育の確保などの対応がされます。慈恵病院、賛育会病院では予期せぬ妊娠や孤立出産のおそれがある人の支援をする電話相談窓口が設置されており、追い詰められた女性の声を事前にキャッチするための取り組みもなされています。
赤ちゃんポストに預ける理由
- 妊娠を周囲に言えなかった(特に未成年や学生)
家族や学校、社会からの非難を恐れ、相談できないまま妊娠・出産に至るケースがあります。 - パートナーに逃げられた、暴力を受けた
妊娠を告げた途端に連絡が取れなくなる、妊娠を理由に暴力を受けるなど、支えを得られない中で孤立してしまう女性がいます。 - 経済的困窮や生活の不安
育てる自信がなく、児童福祉制度や支援にアクセスできないまま追い詰められてしまうこともあります。 - 出産・育児に関する知識不足や不安
誰にも相談できないまま妊娠し、未受診妊婦となり、出産した後に「どうしてよいかわからない」という状況に陥ることもあります。
内密出産とは?
内密出産は、妊婦が病院の担当者にのみ身元を明かし、他の機関や親族には知られずに出産できる制度です。母親の身元情報は病院で厳重に保管され、原則として自治体や親族には開示されません。ただし、子どもが将来、自分の出自を知りたいと希望した場合、母親の同意があれば情報が開示される仕組みが求められています。妊娠中から母親に関わりが持てたケースでは母子手帳の発行や遺伝的な病気の有無など重要な情報を赤ちゃんへ残すために複数回の面談なども実施されます。
赤ちゃんポストに預けられた、または内密出産をした後の流れ
①赤ちゃんの戸籍
赤ちゃんポストに預けられた赤ちゃんは、戸籍法上「棄児(きじ)」として扱われます。病院は警察と児童相談所に連絡し、警察は事件性の有無を確認します。児童相談所は子どもを一時保護し、身元の調査を行います。身元が判明しない場合、病院の所在地の市長が子どもの名前や本籍地を定めて戸籍を作成する「就籍」という手続きが行われます。その後、乳児院や児童養護施設に入所し、里親委託や特別養子縁組が検討されます 。
内密出産の場合は病院が母親の本人確認を行い、出生届も病院側が提出するため法律上「棄児」には該当しません。戸籍も通常の出生と同じく届け出られた内容に基づいて作成されます。ただし母親の名前が戸籍に記載されない場合もあり、その際は実母欄が「不詳」となります。出生の事実は公的に記録されるため子どもが出自を知る権利を行使する際に母親が同意すれば情報開示も可能となります。
②親の身元は分かる?
赤ちゃんポストに預けられた赤ちゃんの親の身元は、児童相談所が可能な限り調査します。しかし、匿名で預けられた場合や連絡先が不明な場合、親の特定は困難です。慈恵病院では、預け入れ時に手紙やメッセージカードを通じて親に連絡を促す取り組みを行っていますが、実際に親と連絡が取れるケースは限られています 。内密出産の場合は①で述べたように情報開示によって親の身元を知ることが出来るケースも存在します。
③預けられた赤ちゃんのその後
ポストに預けられた赤ちゃんは児童相談所により一時保護され、赤ちゃんの福祉を最優先に、里親委託や特別養子縁組などが検討されます。養子縁組が成立すれば、新しい家庭で育てられ、その家庭の戸籍に入り法的にも実子と同じ扱いになります。実親が名乗り出た場合にもすぐに赤ちゃんが実親に引き渡されることはなく、児童相談所が赤ちゃんの安全や育生環境が整っていると判断すれば実親に返還されることもあります。ただしすでに特別養子縁組が成立しているケースでは法的に親子関係が切れているため原則として親子関係の回復は出来ません。親権を取り戻すには家庭裁判所の許可が必要です。実親が名乗り出た時点で育児放棄や虐待などが疑われる場合には慎重に審査され、必ずしも赤ちゃんが実親に返還されるとは限りません。赤ちゃんの最善の権利が最優先されます。
令和5年時点での内訳は以下の通りです。
・児童養護施設で養育 31人(内身元判明25人、身元不明6人)
・里親のもとで養育 14人(身元判明9人、身元不明5人)
・特別養子縁組が成立 87人(身元判明63人、身元不明24人)
赤ちゃんポストのメリット
①赤ちゃんの命を守る最終手段
予期せぬ妊娠や育児放棄、極端な孤立により、赤ちゃんが遺棄されたり命を落とす事件が後を絶ちません。赤ちゃんポストは、そうした極限状態にある母親が「せめて命だけは助けたい」と思ったときに利用できる、社会の最後のセーフティーネットです。誰にも相談できず、追い詰められた中でも赤ちゃんを安全に託せる手段があることは、命を救う大きな意義を持ちます。
②匿名で預けられる
赤ちゃんポストは基本的に匿名で利用できます。「誰にも知られずに出産してしまった」「家族や社会からの批判が怖い」という母親にとって、名前や身元を明かさずに赤ちゃんを託せる仕組みは心理的なハードルを下げ、思いとどまらせる力があります。また、後日連絡を取りたくなった場合のために手紙や連絡先を残す選択肢もあるため、完全に関係を断つ必要はありません。
③安全な環境で育つ機会を得られる
ポストに預けられた赤ちゃんは、医療機関で健康状態を確認された後、児童相談所を通じて一時保護され、乳児院や養育施設で育てられます。その後、特別養子縁組や里親制度によって新しい家庭に迎え入れられることもあります。親が育てられない事情がある場合でも、子どもには愛情を注がれる環境で育つ機会が与えられることになります。
④社会課題への問いかけ
赤ちゃんポストは、単に命を救う装置ではなく、「すべての命は守られるべき」という社会の意思表示でもあります。この存在があることで、予期せぬ妊娠や育児不安を抱える女性に対する理解や支援の必要性が可視化され、福祉や医療体制の改善に繋がるきっかけにもなります。ポストを巡る議論自体が、命の尊さを社会に問いかける役割を果たしています。

赤ちゃんポストのデメリット
①実親の情報が不明になりやすい
匿名で預ける仕組みのため、赤ちゃんの実の親の情報が分からないままになることがあります。出生に関する記録が残らないことで、子どもが将来「自分は誰の子なのか」と悩む可能性があり、出自を知る権利を保障できないという点が問題視されています。また、家族歴や遺伝性の病気など重要な情報が得られなくなるリスクも伴います。
②赤ちゃんの安全が保障されないケース
本来、医療機関や公的機関の支援を受けながら出産・育児するべきところを、赤ちゃんポストに頼ることで、妊婦が適切な医療を受けずに出産する事態を助長する可能性があります。例えば自宅などで1人で危険な状態で出産した後に赤ちゃんをポストに預けるケースでは、赤ちゃんの健康や命が危険にさらされるリスクもあり、根本的な支援の不足が背景にあります。
③親子支援の機会を逃す
赤ちゃんポストの利用者の中には、経済的困窮や周囲の無理解によって追い詰められている人もいます。適切な福祉サービスや相談支援が届いていれば、赤ちゃんを手放さずに済んだ可能性もあります。しかし、ポストに預けることで支援の入り口から外れ、親自身が孤立したままになってしまうこともあり、根本的な問題の解決には繋がらないことがあります。
④子どもの人権が守られにくい
赤ちゃんポストが「命を救うため」として正当化される一方で、「ポストに預けられた」という事実が子どもにとって精神的な負担になる場合もあります。また、どのような状況であれ親に捨てられたという感覚や、身元が不明な状態で育つことに対する不安や喪失感を抱くケースもあります。匿名性と人権のバランスについては今後も慎重な議論が必要な部分です。

法的課題と今後の展望
日本では、内密出産に関する明確な法整備がなく、病院が母親の名前を知りながら出生届を提出しない場合、刑法第157条「公正証書原本不実記載罪」に抵触する可能性があります。また、子どもの出自を知る権利と母親の匿名性のバランスをどう取るかが課題です。ドイツでは、2014年に内密出産法が制定され、母親の身元情報を役所で保管し、子どもが16歳になれば閲覧できる制度が整備されています。日本でも早急に法整備されることが望まれます。
助産師として、赤ちゃんポストや内密出産について知っておくことはとても重要なことです。こうした制度は、「どうしても育てられない」と感じたときに、赤ちゃんの命を守るための“最後の選択肢”として用意されています。でもその一方で、制度の内容を知らなければ、必要な支援につなげるチャンスを逃してしまうこともあります。助産師が女性に寄り添い支援することで尊い赤ちゃんの命と未来を守ることが出来るかもしれません。出生数約70万人に対して、中絶件数は12万件を超え、生後0日の赤ちゃんが遺棄や虐待により亡くなったケースも日々報道されています。さまざまな事情を抱えた支援を必要とする女性が多くいることを助産師は知っておかなければなりません。

夜泣きに悩むママが安心できる場所を、もっと身近に助産師ができること
- 夜泣き
- 夜間授乳

【助産師の最新知識】腕に埋め込む避妊?知っておきたい避妊インプラントの基本
- 避妊インプラント
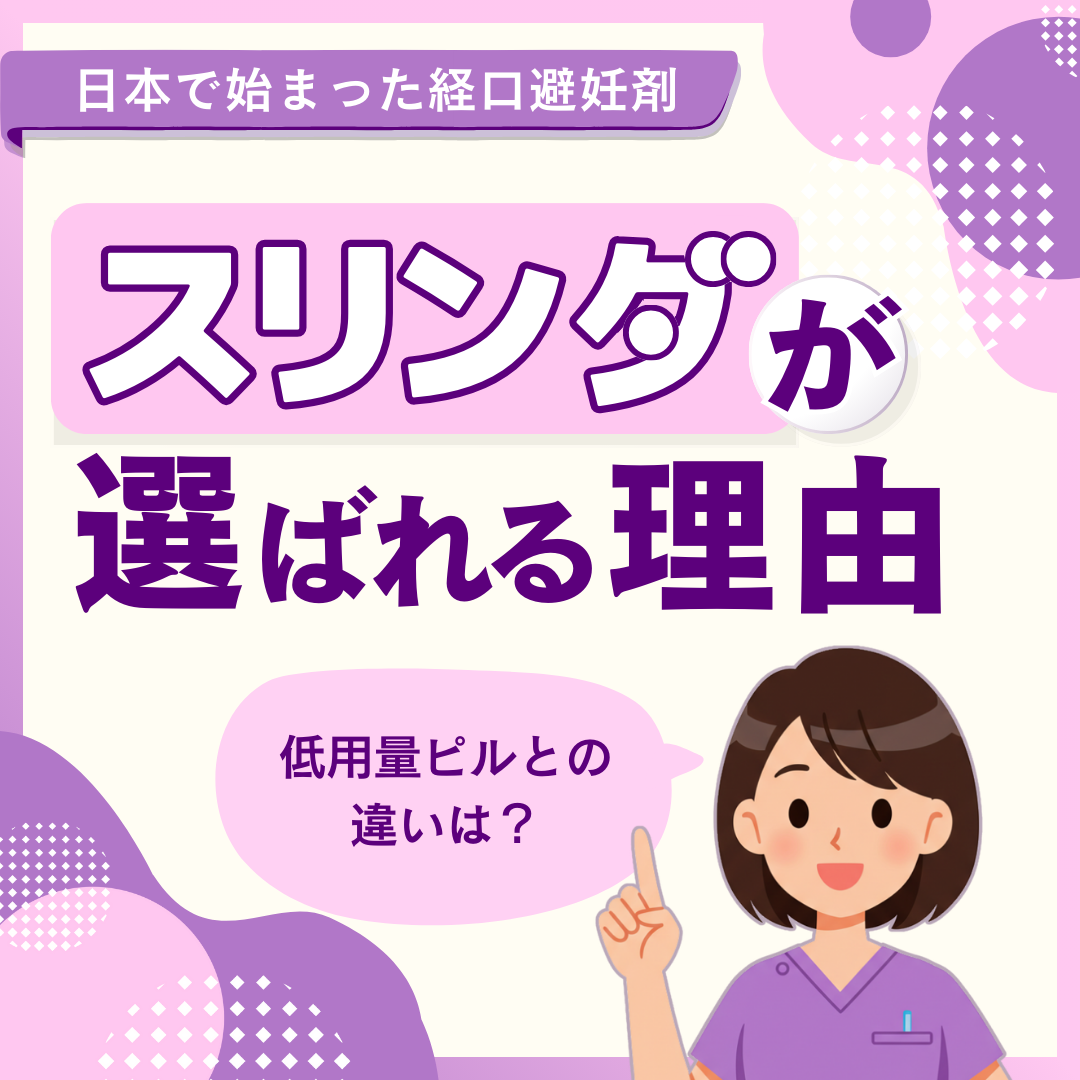
【助産師なら知っておきたい】低用量ピルとの違いは?スリンダの特徴と“選ばれる理由”を解説
- 低用量ピル
- 避妊薬
- スリンダ
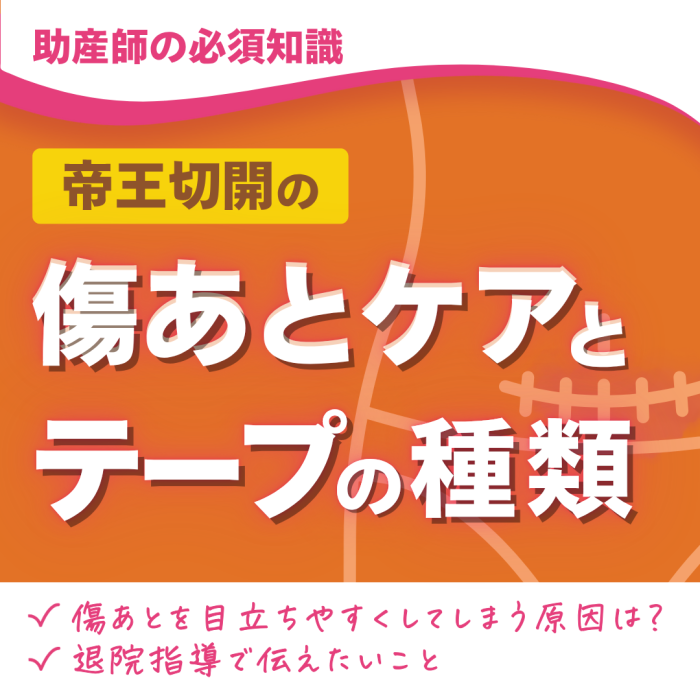
【助産師の必須知識】帝王切開の傷あとケアとテープの種類|傷あとを目立ちやすくしてしまう原因は?|退院指導で伝えたいこと
- 帝王切開
- 傷痕ケア
- 退院指導
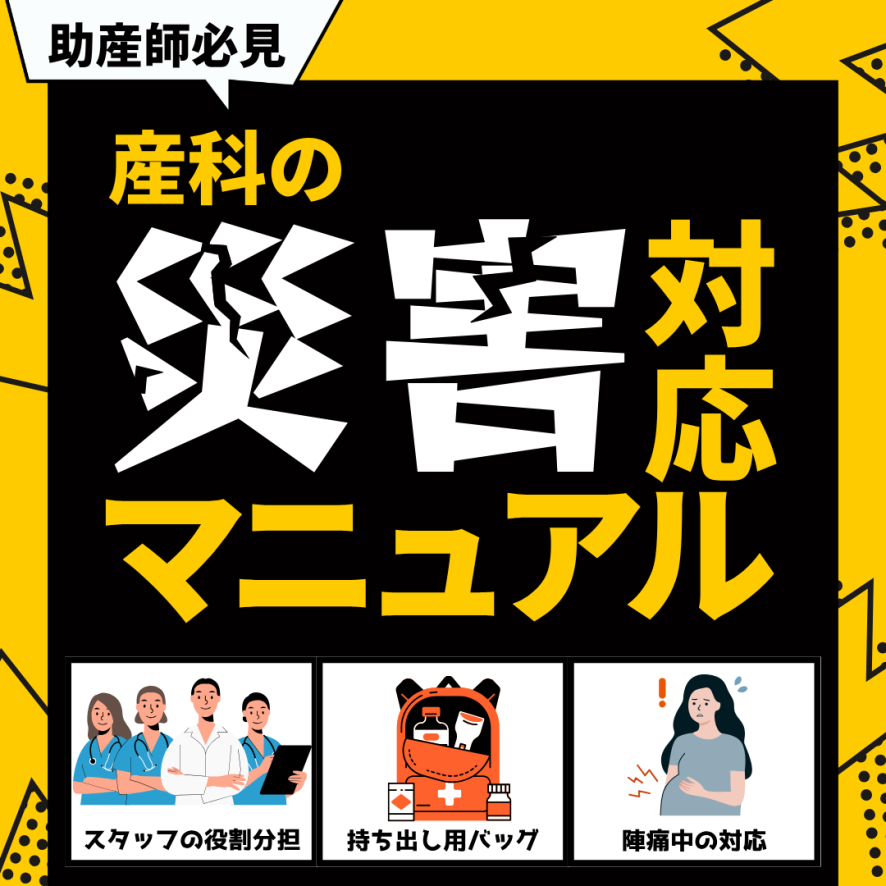
【助産師必見】産科の災害対応マニュアル|スタッフの役割分担・持ち出し用バッグ・陣痛中の対応
- 災害対策
- 医療安全
- 退院指導

【助産師必見】胎児疾患のある妊婦と家族を支える|NPO法人 親子の未来を支える会
- 胎児疾患
- 胎児異常
- 先天異常