
【助産師必見】子宮頚がんって何?基本から治療まで解説!
- 子宮頸がん
- 婦人科疾患
- 妊娠と子宮頸がん
子宮頸がんとは子宮頸部にできるがんのことです。性交渉などの性的接触によって感染したHPVウイルスが原因となり発症します。現在、日本では20〜30代での罹患率が高く、約1万人の女性が罹患する病気で、毎年約3000人の女性が子宮頚がんで亡くなっています。子宮頸がんの進行するペースは非常にゆっくりで前がん状態から進行がんになるまで2〜3年かかります。そのため、子宮頸がんは健診を定期的に受けていれば、早期に発見することができ、比較的治療もしやすいため予後がよいがんとされています。初期のがんで発見されれば子宮を摘出する必要もなく、手術後の妊娠も可能で、子宮頸がんで亡くなることを防ぐことができます。しかし、発見が遅れて進行した子宮頸がんになっていれば、子宮の摘出が必要で、手術後も放射線治療や抗がん剤の治療を行い、再発のリスクを抱えていくことになります。また、妊娠出産の可能性を失うことになったりと心身共に大きな負担となります。
子宮頸がんの危険因子
若年での性交渉、妊娠、出産、複数の男性との性交渉、不潔な性行為、免疫不全状態
子宮頸がんの症状
早期にはほとんど自覚症状がありません。
進行に従って、異常なおりものや、性交時の出血、下腹部の痛み、月経以外での出血、腰や下腹部の痛み、下肢の浮腫などがあります。気になる症状がある場合は早めに婦人科を受診しましょう。
子宮頸がんの検査と診断
細胞診:あくまで子宮頸がんの可能性があるかどうかを調べるも推定診断であり、がんを確定するものではありません。
HPV検査:子宮頸部から細胞を採取し、HPVに感染しているかどうかを調べる検査です。コルポスコープ検査が必要かどうかを調べるために行われることがあります。
組織診(コルポスコープ検査):がんの確定診断をする検査。コルポスコープという拡大鏡を使って、異常が疑われる子宮頸部の組織を採取し検査を行います。必要な場合は子宮頸部を円錐状に切除する手術を行って、組織診を行うこともあります。
MRI・CT・PETなどの画像検査:確定診断後、子宮の周囲や体全体にがんが広がっていないかを確認します。その結果で進行期を決定し、治療方針が決まります。
他にも超音波検査、内診、直腸診、腫瘍マーカー検査などを併用し診断を行います。
子宮頸がんの種類
子宮頸がんには発生過程が3段階あります。がんになる前の段階の「子宮頸部異形成」、子宮頸部の表面にだけがんがある「上皮内がん」、子宮頸部周囲の組織に入り込む「浸潤がん」です。
そして、子宮頸がんの種類は大きく「扁平上皮がん」と「腺がん」の2種類に分けられます。「扁平上皮がん」は子宮頸部の入口表面を覆う扁平上皮細胞に発生するがんで、「腺がん」は子宮体部近くにある腺組織の円柱上皮細胞から発生するがんです。「腺がん」は扁平上皮がんに比べ、発見しにくく初期からリンパ節転移もしやすいです。治療効果も得にくいため治療の難しいがんとされています。
子宮頸がんのステージ分類

子宮頸がんの治療
手術、放射線治療、抗がん剤治療のいずれかを単独、もしくは組み合わせて行います。
1.手術
がんの広がりにより子宮頸部の一部または子宮全摘を行います。卵巣と卵管は年齢や病状に合わせて切除するか決めます。
円錐切除:子宮頸部の一部を円錐状に切除する手術です。切除病変の広がりを詳しく調べる診断的適応と治療的適応に分けられます。子宮の多くを残すことはできますが、その後の出産や妊娠に影響が出る場合もあります。
単純子宮全摘出術:子宮体部とともに子宮頸部を切除する手術です。子宮頸部の周りの組織は切り取りません。円錐切除で切除断面にCIN3があった場合や、診断がAISまたはごく早期のがん(1A1期)の場合に行います。開腹手術、膣式手術、腹腔鏡下手術のいずれかの方法で行います。
準広汎子宮全摘出術:子宮体部、子宮頸部を含む単純子宮全摘出術より少し広い範囲を切除する手術です。子宮と一緒に子宮を支えている基靭帯など子宮頸部の周りの組織の一部と、膣の一部を切除します。リンパ節郭清の有無は問いません。膀胱神経の大部分を温存することができるため、排尿障害が起こることはほとんどありません。
広汎子宮全摘出術:準広汎よりもさらに広い範囲で切除する手術です。子宮体部、子宮頸部、子宮傍組織、膣壁、膣壁傍組織の一部、骨盤内リンパ節の広範囲を切除します。がんを完全に取りきることができる可能性は高くなります。しかし、排尿に関係する神経が走っている基靭帯も切除するため、リンパ浮腫・排尿障害などの影響があります。
広汎子宮頸部摘出術:妊孕性を温存するために子宮体部と卵巣を残し、それ以外を広汎子宮全摘出術と同じ範囲で切除する手術です。広汎が必要な病期の場合で、将来子供を望んでおり、妊娠可能な年齢の時に考慮します。1A2期または、1B1期で明らかなリンパ節転移がないなどの一定基準を満たしている必要があります。
2.放射線治療
放射線を照射することで、がん細胞を傷つけてがんを小さくする治療です。子宮頸がんでは病期に関わらず放射線治療を行うことができ、治療効果も出やすいため、根治目的や術後の補助療法として行われます。進行、再発の子宮頸がんに対しては、腫瘍の抑制や症状緩和を目的に行われることもあります。放射線により、卵巣の機能がほぼ失われますが、排尿機能や性生活への影響は手術より軽いです。副作用として急性反応と晩期合併症があります。急性反応では、照射後数週間で倦怠感、吐き気、下痢 皮膚症状、膀胱炎などの症状がみられますが、治療が終われば自然に治っていきます。晩期合併症は治療後数ヶ月から数年で消化管から出血したり、閉塞、穿孔、直腸膣ろう、尿路障害といった症状を起こすこともあります。
手術や放射線治療によって、閉経前に卵巣を切除したり機能を失った場合は、卵巣欠落症状としてほてり、発汗、動悸、いらいら、食欲低下、倦怠感、頭痛、骨粗しょう症、高脂血症など更年期障害と同様の症状がみられます。
3. 化学療法
抗がん剤を用いて、がん細胞を縮小させる治療です。初発例に対しては微小病変を根絶することが目的で、再発例に対しては症状の緩和と延命が第一目的の治療となります。
子宮頸がんには、プラチナ製剤であるシスプラチン、カルボプラチンが主に使用されています。プラチナ製剤単剤のみによる治療と他剤を併用する方法があり、プラチナ製剤以外の薬はパクリタキセル、イリノテカンなどがあります。副作用として、しびれなどの末梢神経障害や食欲不振、嘔気嘔吐、脱毛、骨髄抑制などがあります。
4. CCRT(同時化学放射線治療)
手術でがんを摘出することが困難な場合などに、放射線治療と抗がん剤治療を同時に行う治療です。抗がん剤は放射線の治療効果を増強し、全身再発を防ぐとともに、全身に転移する見えないがん細胞にもダメージを与える治療になります。
妊娠と子宮頸がん
妊婦健診の初期検査の中には子宮頸がんの検査が含まれており、子宮頸がん患者の3.3%は妊娠中に発見されています。
子宮頸がんの受診率はOCEDのHPに掲載されていますが、欧米が7〜9割の受診率に対して日本は43%という結果です。妊娠することで初めて子宮頸がん検査を受けたという人も少なくないかもしれません。
子宮頸がん検診が妊婦検診の初期検査に含まれる理由としては、妊娠出産年齢が上昇し、子宮頸がんの罹患年齢が若年化しているため、妊娠出産年齢と子宮頸がんの好発年齢のピークが重なる傾向にあることがあります。また前述したように、性交渉によってHPV感染が起こるため、性交渉によって成立した妊娠初期には、異型細胞や子宮頸がんの発見が多くなります。他にも、妊娠が進んだあとでの検査は、子宮の入口から出血しやすくなること、また万が一子宮頸がんが発見された場合は、今後の検査や治療の予定を踏まえると初期の受診が望ましく、妊婦健診では初期に子宮頸がん検査を実施することになっています。
もし、妊娠中に子宮頸がんが疑われた場合でも治療、検査内容は妊娠していない時と同じです。子宮頸がんの経過はゆっくりなので、妊娠初期に前がん病変が発見されても、出産を終えるまでにそれほど進行することはありませんし、妊娠中に何度も検査をすることもありません。出産まで経過を観察し、出産後に治療を行うのが一般的です。
しかし、子宮頸がんの病期によっては、治療が妊娠や出産に影響を及ぼすことがあります。妊娠前に進行した子宮頸がんが見つかった場合は、将来の妊娠や出産に与える影響について治療開始前に妊孕性の温存についてなど医師に確認して、治療を行う必要があります。将来、妊娠出産の希望がある場合は、1B1期までは妊孕性を温存することが選択肢となる場合があります。妊孕性を温存する治療として、子宮頸部円錐切除術、広汎子宮頸部摘出術があります。通常であれば切除する部分を残すため再発のリスクがあること、また子宮頸部が短くなるため、流早産のリスクは高まります。
妊娠中に進行した子宮頚がんが見つかった場合は、経過観察を行いながら妊娠を継続するか、もしくは妊娠を中断し、治療を優先するか決めなければいけません。子宮頸がん検査の結果で、突然子宮頸がんであることが判明し、妊娠を諦めなければいけなくなるため、精神的負担が大きくなります。すでにがんが進行していて治療が必要な場合、治療を開始する時点で22週を超えていれば、帝王切開にて出産し治療を開始することもあります。
確率的には大変まれで特殊な事例ですが、母親の子宮頸がんのがん細胞が混ざった羊水を赤ちゃんが肺に吸い込むことによって、子宮頸がんの細胞が赤ちゃんの肺に移行し、小児での肺がんを発症したという例の報告もあります。これは、小児がん患者で肺にがんをもつ2名を遺伝子解析によって調査したことで発見されました。遺伝子解析によって、この2名の小児がん患者から他人由来の遺伝子が検出されたこと、さらにこの2名の母親が子宮頚がんを発症していたため、遺伝子比較をしたところ母親由来の遺伝情報を持っていることが明らかとなり、HPVの遺伝子も検出されました。これらのことから、2名の小児の肺がん患者は母親の子宮頸がんの細胞が移行したという結論が症例が発表されており、母体の子宮頸がんが子どもに移行する可能性もあると言えます。
子宮頸がんが赤ちゃんに大きな影響を与えることはほとんどありませんが、子の健康のためにも母親の子宮頸がんの予防は重要になってきます。
HPVワクチン
子宮頸がんは、HPVワクチンを接種することでHPVの感染を予防することができます。ただし、すでにHPVに感染している細胞から取り除く効果は認められていません。HPVに感染する前にワクチンを投与すると最も予防効果が高いため、初めての性交渉の前に接種することが勧められています。日本では現在、小学校6年生から高校1年生相当の女子を対象に定期接種が行われていて、対象者は公費でワクチン接種を受けることができます。しかし、ワクチンによって全てのHPVの感染を防げるわけではないので、ワクチン接種と定期的な子宮頸がんの健診を受けることが必要です。
20歳を過ぎたら2年に1回検査を受けることが推奨されています。若い日本人女性の子宮頸がん検診の受診率はまだまだ低いです。妊娠出産をすると検査に行こうと思ってもなかなか行けないこともあり、その間に進行する可能性もあります。これから妊娠出産を考えている女性が子宮頸がんのために妊娠を諦めたり悲しい思いをすることなく、妊娠出産の時期を健康で過ごすことができるよう検査を受ける必要性を伝えていく必要があると思います。また女性のライフサイクルの支援としても、全ての女性が健康でいられることを目指し、子宮頸がんに対する知識の普及と検診に対する意識向上を促していくことも助産師の大事な活動です。検診を受けることで予防ができるがんです。大切な自分の体を守りましょう。
参考文献
1)日本産科婦人科学会 HP子宮頸がん https://www.jsog.or.jp/citizen/5713/
2)日本婦人科腫瘍学会 子宮頸癌治療ガイドライン2022 金原出版
3)国立がん研究センター がん情報サービス
https://ganjoho.jp/public/cancer/cervix_uteri/index.html
4)国立がん研究センター 母親の子宮頸がんが子どもに移行する現象を発見
https://www.ncc.go.jp/jp/information/pr_release/2020/20210107/index.html
5)特定機能病院 愛知がんセンター 子宮頚がんについて

夜泣きに悩むママが安心できる場所を、もっと身近に助産師ができること
- 夜泣き
- 夜間授乳

【助産師の最新知識】腕に埋め込む避妊?知っておきたい避妊インプラントの基本
- 避妊インプラント

【助産師なら知っておきたい】低用量ピルとの違いは?スリンダの特徴と“選ばれる理由”を解説
- 低用量ピル
- 避妊薬
- スリンダ
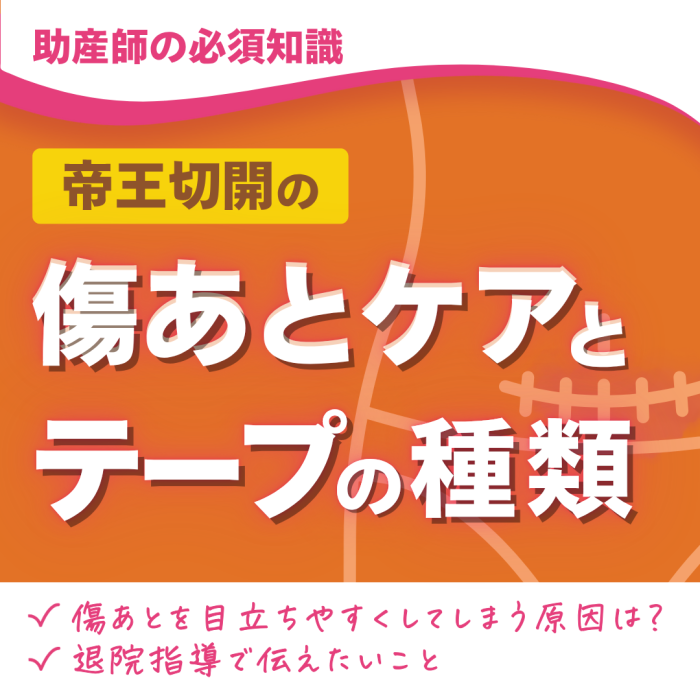
【助産師の必須知識】帝王切開の傷あとケアとテープの種類|傷あとを目立ちやすくしてしまう原因は?|退院指導で伝えたいこと
- 帝王切開
- 傷痕ケア
- 退院指導

【助産師必見】産科の災害対応マニュアル|スタッフの役割分担・持ち出し用バッグ・陣痛中の対応
- 災害対策
- 医療安全
- 退院指導

【助産師必見】胎児疾患のある妊婦と家族を支える|NPO法人 親子の未来を支える会
- 胎児疾患
- 胎児異常
- 先天異常