
【永久保存版】助産師が押さえておきたいアプガースコア|評価の基準と現場でのポイント
- アプガースコア
1.アプガースコアってなに?
アプガースコアは、新生児の健康状態を5つの項目で評価し、それぞれ0〜2点、合計10点で表すスコアです。1952年、アメリカの麻酔科医ヴァージニア・アプガー博士が提唱し、世界中で使用されています。評価のタイミングは出生後1分、5分です。蘇生を必要とした新生児など状態が不安定な場合は必要に応じて10分後に再度、評価を行います。1分での点数は新生児の緊急性の判断、蘇生の必要性を示し、5分での点数は新生児の神経学的予後にも関連すると言われていて、新生児の出生後早期の状態を判断するのにとても重要な指標です。
スコア | |||
0点 | 1点 | 2点 | |
皮膚色 Appearance | 蒼白 | 体幹ピンク 四肢チアノーゼ | 全身ピンク |
心拍数 Pulse | なし | <100回/分 | ≧100回/分 |
刺激に対する反応 Grimace | 反応しない | 顔をしかめる 弱く泣き出す | 咳、くしゃみ 強く泣く |
筋緊張 Activity | 四肢弛緩 | やや屈曲 少しだけ四肢を動かす | 活発に四肢を動かす |
呼吸 Respiration | なし | 緩徐(不規則) | 強く泣く |
2.各項目を深掘りしてみよう!
◆ 皮膚の色(Appearance)
皮膚の色は、赤ちゃんの酸素化状態や末梢循環を反映します。明るい光の下で、顔・体幹・四肢など全身をしっかり観察しましょう。
- 0点:全身チアノーゼ・蒼白
- 1点:体幹はピンク、末梢性チアノーゼ
- 2点:全身ピンク
皮膚の色を観察する際に重要なのが中心性チアノーゼの有無です。末梢チアノーゼは生理的なこともありますが、中心性チアノーゼは肺循環への移行がうまく行われていない可能性があります。中心性チアノーゼの原因としては呼吸障害(肺の虚脱、肺水)、PPHN(遷延性肺高血圧)、先天性心疾患などがあげられます。酸素投与の必要性は皮膚の色だけでは判断が難しいため、児が産まれたらなるべく早くSpO2モニターを装着し、測定をしましょう。皮膚の色を観察する際には体幹(中心性チアノーゼの有無の確認)→顔(口唇や舌、頬)→上肢→下肢の順番で観察をする、など全身を抜けなく観察ができるように工夫すると良いでしょう。
皮膚の色とSpO2
皮膚の色は「見た目の酸素化の指標」であるのに対し、SpO2は「客観的な酸素化の数値」です。生後すぐのSpO2は右手で測定します。右手のSpO2は純粋に心臓から出た動脈血の値であり動脈管の影響を受けません。下肢のSpO2測定も可能であれば右手のSpO2と下肢のSpO2の値に差がないかどうかを確認します。右手と下肢の数値に差がある場合、肺循環が不十分であったり、右左シャント(遷延性肺高血圧)が存在している可能性があります。右手のSpO2も下肢のSpO2も低値である場合には全身が低酸素の状態であると言えます。

◆ 心拍数(Pulse)
心拍数は、新生児の循環状態を示すもっとも重要な評価項目です。
- 0点:心拍なし。
- 1点:100回/分未満。
- 2点:100回/分以上。
出生後すぐにSpO2モニターを右手に装着しても心拍数やSpO2が表示されるまでには2分程度かかるとされています。1分後までに心拍数を確認するためには聴診器で6秒間心音を聞き、×10して1分換算する方法が推奨されます。臍帯動脈の拍動でも心拍数の確認が可能ですが、拍動が弱くて感じ取りにくい、触れる部位や角度によって拍動が分かりにくいなど正確性に欠けます。出生直後〜1分までに心拍数を評価するには聴診が最も適していると言えます。蘇生が必要な児では可能であれば3誘導心電図モニターを装着し、心拍数を持続的に確認することが望ましいです。心拍が100回/分未満である場合は陽圧換気の適応になります。
◆ 刺激への反応(Grimace)
鼻腔吸引や足底への軽い刺激にどう反応するかをみる項目です。神経学的な反応性や意識レベルを推し量るヒントになります。
- 0点:無反応
- 1点:顔をしかめる、小さな動きのみ
- 2点:泣く、くしゃみ、咳など明確な反応
反応が弱い場合に気道の閉塞や低酸素が原因となっていることがあります。刺激への反応を確認する際は気道確保・気道が開通しているかも合わせて確認しましょう。吸引や足底の刺激以外ではタオルで羊水を拭く動作を通じて皮膚へ刺激を与えたり、背中を優しくさすると良いです。過剰な刺激は避けましょう。
◆ 筋緊張(Activity)
筋緊張は、神経系の成熟や循環状態のよさを反映します。
- 0点:ぐったり。四肢が伸展し、無動
- 1点:四肢に軽い屈曲がある
- 2点:手足をばたばた動かしている、活発
仰臥位の状態で、四肢が自然に屈曲していれば筋緊張は概ね良好と言えます。自発的な動きがあるかも観察しましょう。抵抗性を確認するため上下肢に触れた際の反応も確認すると良いです。
◆ 呼吸(Respiration)
呼吸の有無や質は、新生児の生命維持に直結します。泣いていれば原則2点ですが、呼吸の“質”に注目しましょう。
- 0点:呼吸なし(無呼吸)
- 1点:努力性呼吸、弱い・不規則な呼吸
- 2点:規則的で安定した呼吸、または力強い啼泣
努力性呼吸、弱い・不規則な呼吸とは…
- 一次性無呼吸:刺激で再開することがある
- 二次性無呼吸:中枢性抑制による呼吸停止。刺激では反応せず、蘇生が必要。
- 鼻翼呼吸:鼻を広げて吸気する努力性呼吸
- 陥没呼吸:肋間・剣状突起下・鎖骨上がへこむ
- シーソー呼吸:胸がへこみ、お腹が出るように逆に動く
泣いていなくても胸腹部が規則的に上下動する安定した呼吸であれば2点となります。努力性呼吸、弱い・不規則な呼吸が認められた場合には酸素投与や陽圧換気の必要性を検討しましょう。努力性呼吸がありSpO2が低い(目標値に達していない)場合は酸素投与が必要です。陽圧換気は酸素投与だけではSpO2が改善しない、自発呼吸はあるが努力性呼吸が強い場合に有効な方法です。陽圧換気は自発呼吸があることを前提にしています。自発呼吸がなければバッグバルブマスクによる換気が優先しましょう。

3.1分値と5分値の意味
アプガースコアは、出生直後(1分値)と、そこから回復しているか(5分値)をみることで、赤ちゃんの状態変化を把握します。
- 1分値:生まれた直後の緊急性、蘇生の必要性を判断
- 5分値:介入後の回復状態、神経学的予後の予測に役立つ
例えば1分値4点→陽圧換気→5分値8点なら「介入が奏功した」と評価できます。低スコアが持続する場合には10分値の評価やNICU搬送も視野に入ります。
4.アプガースコアは「ツール」
スコアが高いからといって絶対に安心なわけではありません。先天異常や代謝疾患などはスコアに反映されないこともあります。逆に、スコアが低くても適切に介入すれば速やかに改善することもあります。大切なのは、「全体像をみて判断すること」です。点数をつけるだけにならないように赤ちゃんの全身状態をしっかり観察して総合的に判断をしましょう。
5.記録・伝達
アプガースコアを記録する際には合計点だけでなく、項目別のスコアも必ず残しましょう。
申し送りでは「末梢チアノーゼがあり1点」「呼吸は努力性で1点」など、背景を補足することでスタッフ間での共通理解が深まります。
アプガースコアは、新生児の「今の状態」を数字にして捉えるための大切なツールです。でも、点数をつけること自体が目的ではありません。評価を通して、「この子には今、何が必要か?」を考えられるようになることがいちばん大切です。初めのうちは、点数の付け方に戸惑ったり、先輩の評価とずれたりすることもあると思います。徐々に数を重ねるうちに観察力も判断力も育ってきます。「泣いている=元気」と思わず、皮膚の色や呼吸の仕方まで丁寧に見ていく力を、日々の経験で少しずつ磨いていきましょう。
参考文献
新生児蘇生法テキスト2020(日本版 NCPR)
病気がみえる vol.10 産科 第4版
厚生労働省「新生児蘇生法ガイドライン(NCPR)関連資料」

【新人助産師必見】出生直後に助産師が確認すべき3つの視点|バイタルサイン・成熟度・外表奇形の観察ポイント
- 新生児のバイタルサイン
- 成熟度
- 外表奇形
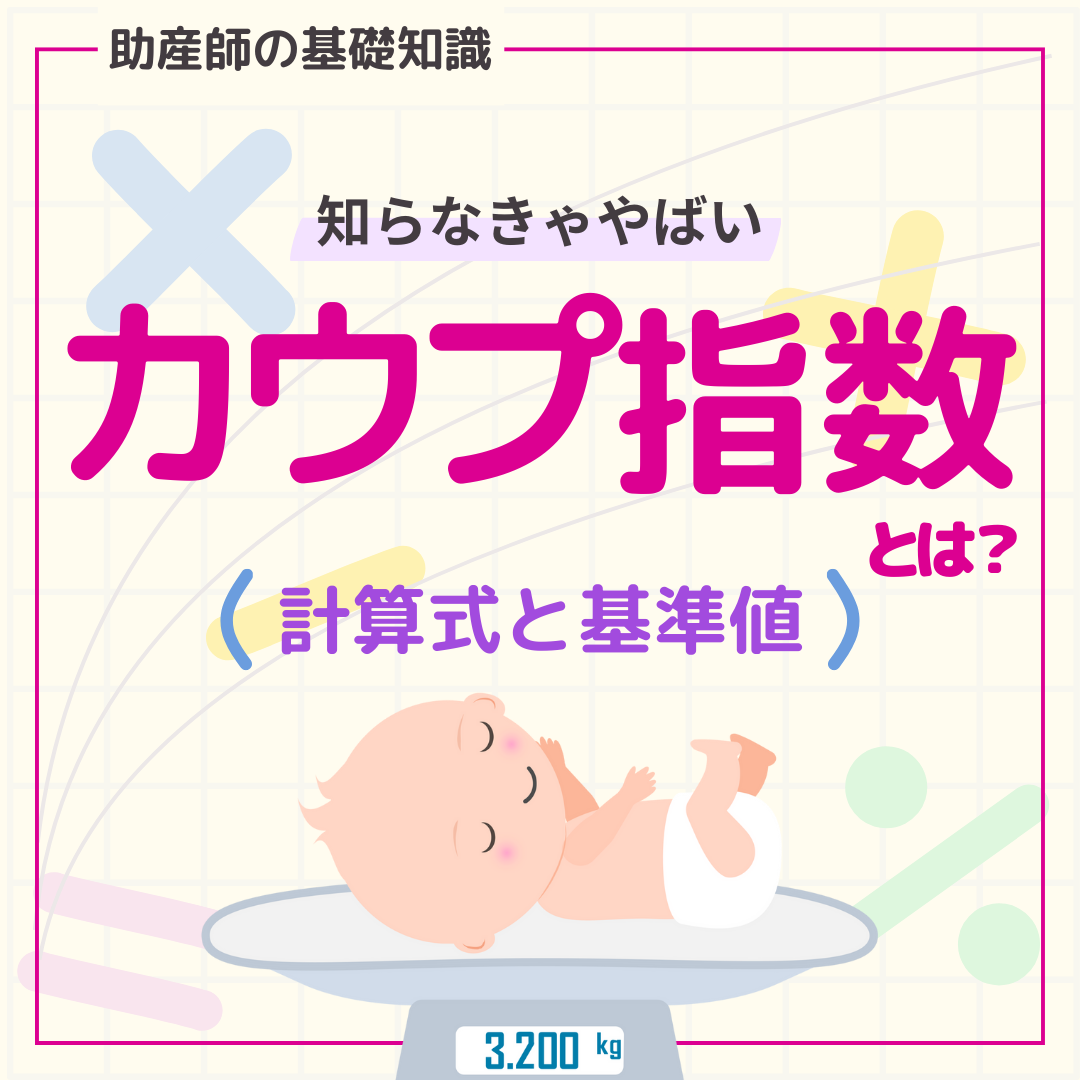
【知らなきゃやばい】カウプ指数とは?計算式と基準値|助産師の基礎知識
- 産後ケア
- 赤ちゃんの発育
- 育児相談

【新人助産師と学生が押さえておきたい】CTG(NST)モニターの基礎知識|基線・基線細変動・一過性頻脈の見方をわかりやすく解説
- CTGモニター
- モニター判読
.png)
【助産師必見】超音波検査での胎児計測|基本項目と正しい計測方法を徹底解説
- 超音波検査
- 助産師によるエコー検査

“なんとなく”の指導はもう終わり。エビデデンスに基づく乳頭ケアの指導方法|妊婦さんの「やってみよう」を引き出す助産師の言葉は?
- 乳頭マッサージ
- 妊娠中

明日から使える!妊婦さんの不安を解消する「会陰マッサージ」指導のポイント|最新のエビデンスも解説
- 会陰部マッサージ
- 会陰部切開
- 経腟分娩