
【新人助産師必見】出生直後に助産師が確認すべき3つの視点|バイタルサイン・成熟度・外表奇形の観察ポイント
- 新生児のバイタルサイン
- 成熟度
- 外表奇形
①出生直後の観察ポイント
赤ちゃんが産まれたら最初の数秒〜30秒以内に①呼吸、②筋緊張、③在胎週数を確認します。啼泣があり、筋緊張も良好で、正期産であれば母親のそばでルーチンケアをしながら赤ちゃんの観察を行います。
②出生30秒〜1分
赤ちゃんのアプガースコアを1分後、5分後の時点で評価します。アプガースコアは短時間で、分かりやすく全身状態の評価が出来る指標です。蘇生が必要な状態ではないかを1分値までに判断することが出来ます。アプガースコアの5分値は、新生児の神経学的予後を予測する上で重要であると考えられています。5分値が低い場合は、長期的な神経発達に影響が出る可能性があるため注意が必要です。
項目 | 0点 | 1点 | 2点 |
呼吸 | 無呼吸 | 不規則・弱い | 力強い呼吸・泣いている |
心拍数 | なし | 100未満 | 100以上 |
筋緊張 | だらんとした状態 | 軽く屈曲 | 活発に動く |
刺激への反応 | 無反応 | 顔をしかめる | 咳き込む・くしゃみ |
皮膚色 | 全身チアノーゼ | 四肢チアノーゼ | ピンク色 |
③バイタルサインの測定
・体温
新生児は体温調節機能が未熟なため出生直後から適切な保温と体温のモニタリングが必要です。出生直後は羊水で濡れた状態であり、外気温の影響を受けやすいため出生後最初の体温測定は直腸温での測定が行われます。直腸温での測定することで鎖肛の有無を確認することも出来ます。新生児の直腸粘膜は非常に脆弱なため、繰り返しの直腸温測定は粘膜損傷や穿孔のリスクがあることから、原則として直腸温での測定は1回限りとし、その後は腋窩温での測定が推奨されてます。
体温が36.5℃未満である場合は低体温とされ、末梢血管の収縮によって皮膚の血流が減少し、代謝性アシドーシスや無呼吸、さらには低血糖を引き起こす危険性があります。特に早産児や低出生体重児、仮死児では体温維持が難しく、出生後早期から保育器に収容して管理をすることがあります。逆に37.5℃を超える「高体温」状態では過剰に保温していることによる影響や感染の可能性が考えられます。発熱とともに傾眠傾向や哺乳不良、呼吸数の変化などが見られる場合は医師に報告します。
・ SpO2
胎児循環から新生児循環へと切り替わる過程で、呼吸の開始とともに酸素化は急速に進行します。出生直後のSpO₂はすぐには正常値まで到達しません。SpO2の目標値は出生1分後で60%以上、3分後で70%以上、5分後で80%以上、10分後で90%以上です。出生後速やかに右手にモニターを装着してSpO2の測定を開始します。酸素飽和度が時間経過とともに適切に上昇しているかを確認し、目標値に到達しない場合には呼吸状態や心雑音の有無などを合わせて観察します。右手と下肢でSpO2の値に差がある場合は、動脈管開存や大動脈縮窄などの心奇形を疑うきっかけにもなります。
・低血糖
出生し胎盤からの糖の供給が絶たれると、赤ちゃんの血糖は一時的に低下します。赤ちゃんは低下した血糖を安定させるために肝臓のグリコーゲンを分解し、エネルギー源を確保しようとします。正常児では血糖は徐々に安定しますが、母体糖尿病、SGA(子宮内発育不全児)、低出生体重児、仮死児、低体温児では、低血糖のリスクが高く、出生後1時間以内から数時間ごとに血糖測定が必要です。一般的には、45mg/dL未満を低血糖と定義し、30mg/dL未満ではブドウ糖の静注が必要になることもあります。低血糖の症状としては、哺乳力の低下、手足の振戦、嗜眠、無呼吸発作、けいれんなどがあります。症状が不明瞭な新生児では、低血糖が遷延することで脳障害(後遺症)をきたす可能性もあります。
④身体計測
赤ちゃんが産まれたら体重、身長、頭囲、胸囲を計測します。身体計測をすることで赤ちゃんの発育状況を客観的に評価し、在胎週数とのバランスが取れているかを確認します。出生体重が2500g未満の低出生体重時や在胎週数と比較して小さいSGA児は出生後、低体温や低血糖になりやすく慎重な管理が必要です。4000g以上の巨大児も低血糖を起こしやすくハイリスクと言えます。頭囲が大き過ぎる場合には脳腫瘍や水頭症、小さ過ぎる場合には小頭症、頭の形が歪である場合には頭蓋骨癒合などの可能性があります。また頭囲に対して胸囲が小さ過ぎる場合には発育不良や肺低形成などの可能性があります。全体的に小さいまたは大きいのか、左右差や非対称性がないか、在胎週数相当から大きく外れていないか、成長曲線から大きく外れていないか、頭囲と胸囲のバランスは悪くないかバイタルサインや全身状態と合わせて観察する必要があります。
⑤外表奇形
出生直後の視診によって分かる外表奇形の中には早期に治療を開始する必要がある緊急性の高いものから、特に治療を必要としないものまで様々です。
・頭部
頭囲を測定した後、大泉門、小泉門、頭蓋縫合、骨重積の有無などを観察します。頭囲が大き過ぎたり、小さ過ぎる場合に水頭症や小頭症の可能性があります。大泉門、小泉門が大き過ぎる、小さ過ぎる、膨隆している、陥没しているなどの異常がある場合、頭蓋縫合早期癒合や脳腫瘍などが隠れている可能性があります。頭蓋縫合早期癒合の場合、頭の形が歪になることがありますが、出生後すぐの赤ちゃんの頭は産道を通過する際の圧力で変形していることもあるため出生後すぐだけではなく、定期的に観察する必要があります。また頭の大きさや形だけでなく脂腺母斑の有無など皮膚の状態も観察しましょう。脂腺母斑のある部位からは基本的に毛髪が生えないため見た目への影響があります。
・顔
まず顔全体を観察します。左右非対称な顔つきである場合、顔面神経麻痺の可能性があります。目の観察は出生後、新生児眼炎の予防の点眼を行う際に行うのが良いです。目から順に目、鼻、口、耳とパーツ毎に確認をしていきます。口唇口蓋裂がある場合、専用の乳首を使用した授乳をするなど対処が必要です。また耳の外表奇形は難聴を合併しているケースもあるため聴力検査の結果も合わせて確認する必要があります。
・体幹
背中を観察する際には脊柱を指でなぞるように触れてみるのが良いです。おしりの割れ目が左右どちらかに斜めになっていたり、非対称である場合や仙骨部に皮膚の陥没やえくぼがある、多毛である場合に潜在性二分脊椎の可能性があります。胸部の外表奇形でよく見られるのが漏斗胸で、男児に多く男女比は3〜4:1です。胸筋の欠損が見られるポーランド症候群では胸部に左右差があります。腹部では臍ヘルニアや尿管膜遺残など臍の周囲の異常が比較的頻度が高いです。腹部に腫瘤を触知する、左右差がある場合には腫瘍の有無を確認する必要があります。
・四肢
四肢に見られる外表奇形は多指症、合指症、外反足などがあります。指は必ずカウントし、本数だけでなく爪の有無や大きさ、指の長さなどにも注意をして観察しましょう。外反足は程度によっては治療が必要となります。
・臀部
臀部の外表奇形として最も発見されやすいのが鎖肛です。前述の通り、鎖肛を発見する目的で出生後すぐの体温測定は直腸温(肛門)で測定されています。もし鎖肛を見つけたら直腸腟瘻など瘻孔から便が排泄されている場合もあるため排便があるかどうか必ず確認しましょう。瘻孔も存在せず排便出来ない場合には腸閉塞になるリスクが高く、早期に人工肛門を増設する必要があります。
・陰部
停留睾丸でないか、陰茎が小さくないか、陰核が肥大していないかを確認します。性分化異常や内分泌疾患が隠れている場合があります。
以下の表に、部位別に代表的な奇形とそのリスク・関連疾患をまとめます。
■ 頭部・顔面の外表奇形
部位 | 観察異常 | 関連疾患・リスク |
頭蓋 | 頭蓋縫合早期癒合、水頭症、小頭症、脂腺母斑 | クルーゾン症候群、染色体異常、皮膚腫瘍前駆病変 |
顔 | 顔面非対称、顔面神経麻痺 | 吸引分娩の影響、先天性麻痺 |
眼 | 眼瞼下垂、逆さまつげ、小眼球、眼間開離 | 動眼神経麻痺、21トリソミー、視覚障害 |
鼻 | 鼻梁低形成、鼻孔閉鎖 | 顔面奇形、緊急対応を要する呼吸障害 |
口腔 | 口唇口蓋裂、舌小帯短縮、巨舌、エプシュタイン真珠 | 染色体異常、Beckwith-Wiedemann症候群など |
耳 | 小耳症、副耳、耳前瘻孔、耳低位 | 聴覚障害、腎奇形、18トリソミー |
■ 頸部・体幹の外表奇形
部位 | 観察異常 | 関連疾患・リスク |
頸部 | 頸嚢胞、側頸瘻 | 感染・呼吸障害、手術適応 |
背部 | 正中線陥凹、多毛、皮膚瘤 | 二分脊椎、脊髄係留症候群 |
胸部 | 漏斗胸・鳩胸、乳頭異常、ポーランド症候群 | 呼吸制限、胸筋欠損、上肢奇形 |
■ 四肢・泌尿生殖器の外表奇形
部位 | 観察異常 | 関連疾患・リスク |
手足 | 多指・合指・内反足、短指症 | 骨形成異常、遺伝性疾患 |
肛門 | 鎖肛、肛門前方位 | 消化管閉塞、直腸膣瘻 |
外陰 | 停留睾丸、陰茎小、肥大陰核 | 性分化異常、内分泌疾患 |

⑥成熟度の評価
出生時には、推定在胎週数と身体的・神経学的成熟度が一致しているかを評価することで、早産や子宮内発育不全(IUGR)の見落としを防ぐことができます。デュボビッツ法(Dubowitz)は、21項目(皮膚の質・耳介の形・姿勢・筋緊張など)から評価し、より高精度な在胎週数推定が可能ですが、臨床現場では簡易化されたニューバーラードスコア(New Ballard Score)が主流です。ニューバーラードスコアは身体的6項目と神経学的6項目を評価し、点数に応じて在胎週数を算出します。例えば、足底のしわの分布や耳介の反り、踵と耳の距離など、外表からも判断可能な指標が含まれており、出生後12時間以内に実施することが推奨されます。
出生直後の新生児観察は、助産師が専門職として担う最初の「命の見極め」です。体温、SpO₂、血糖の変化を通して、赤ちゃんの生理的適応を多面的に把握し、低体温・低酸素・低血糖といった危険サインに即応する力が求められます。また、外表奇形の有無を確実に観察することで、重大な先天異常や合併症の見逃しを防ぎます。成熟度評価を通じて、在胎週数と発育の整合性を判断することも、安全な新生児管理に欠かせない視点です。観察力は経験で養われるスキルであり、助産師の臨床判断力を支える根幹となるものです。
・参考文献
助産師基礎教育テキスト 第2版
新生児蘇生法(NCPR)テキスト 2020
小児科学第9版
病気がみえる産科
病気がみえる小児科

【助産学生・新人助産師必見】帝王切開術後の看護のポイントと観察項目
- 手術侵襲
- ポイントまとめ
- 手術後観察

【新人助産師と学生が押さえておきたい】CTG(NST)モニターの基礎知識|基線・基線細変動・一過性頻脈の見方をわかりやすく解説
- CTGモニター
- モニター判読
.png)
【助産師必見】超音波検査での胎児計測|基本項目と正しい計測方法を徹底解説
- 超音波検査
- 助産師によるエコー検査

“なんとなく”の指導はもう終わり。エビデデンスに基づく乳頭ケアの指導方法|妊婦さんの「やってみよう」を引き出す助産師の言葉は?
- 乳頭マッサージ
- 妊娠中

明日から使える!妊婦さんの不安を解消する「会陰マッサージ」指導のポイント|最新のエビデンスも解説
- 会陰部マッサージ
- 会陰部切開
- 経腟分娩
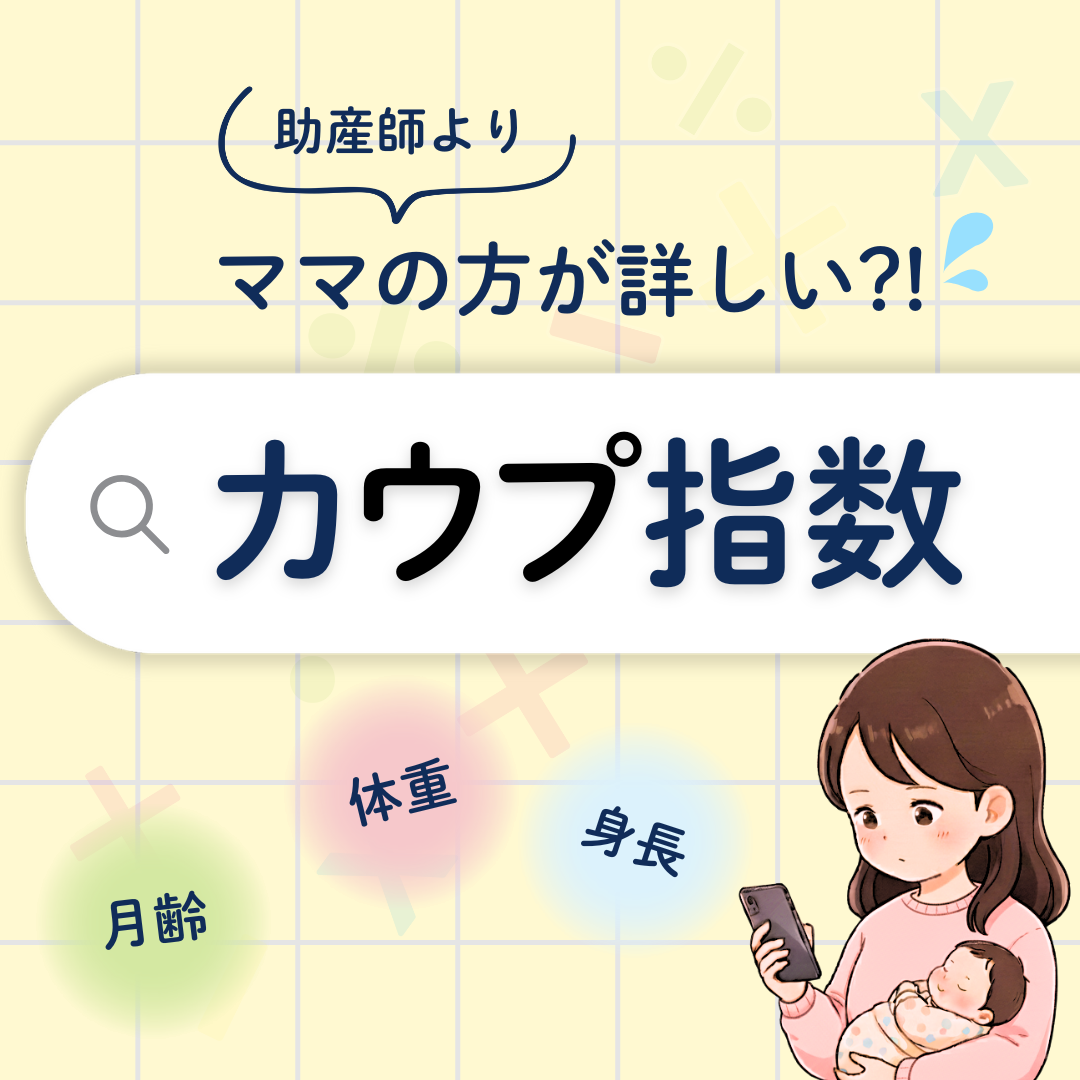
【月間3.8万検索の衝撃】ママの方が詳しいかも?助産師が知っておくべき“カウプ指数”の常識
- カウプ指数
- 月齢
- 乳幼児
