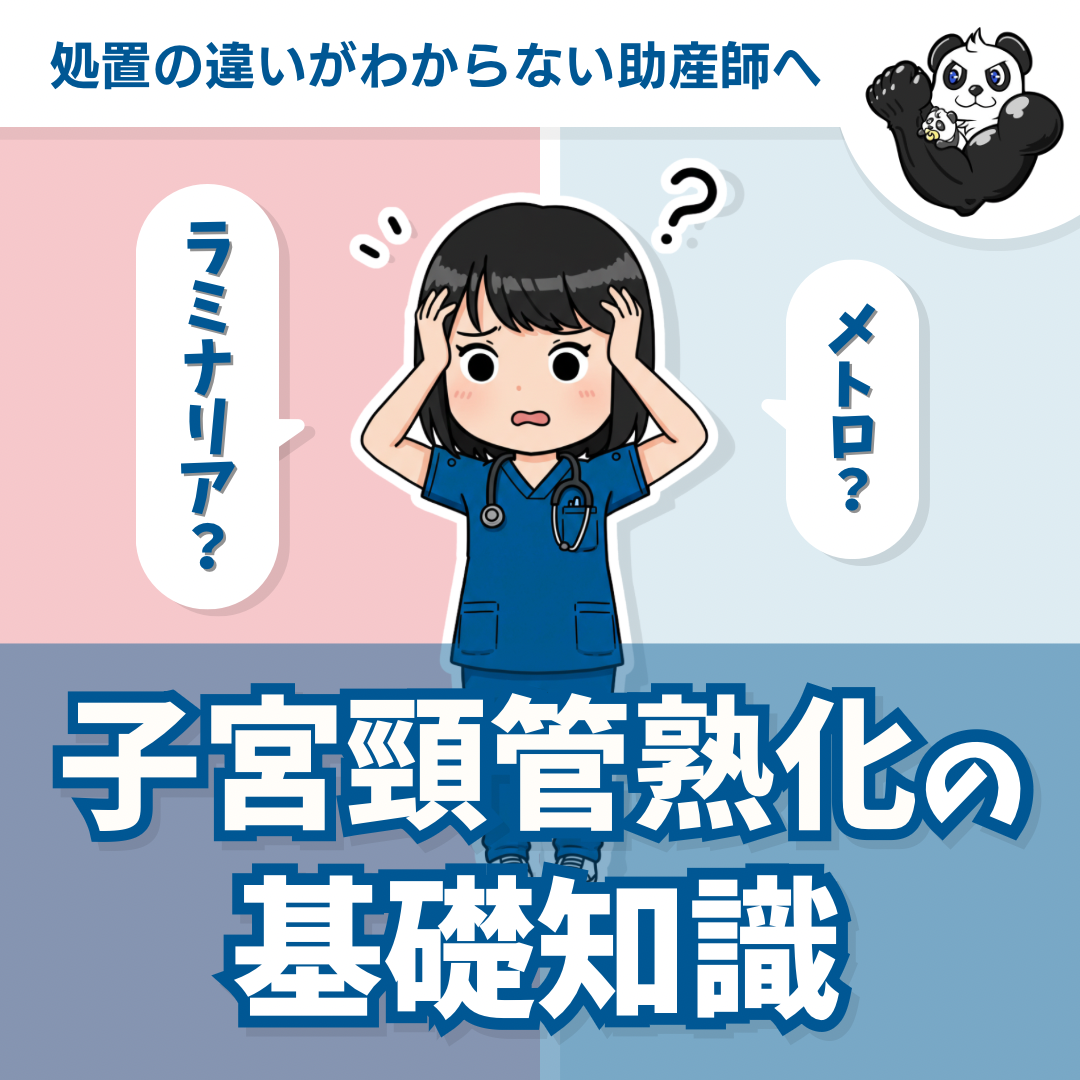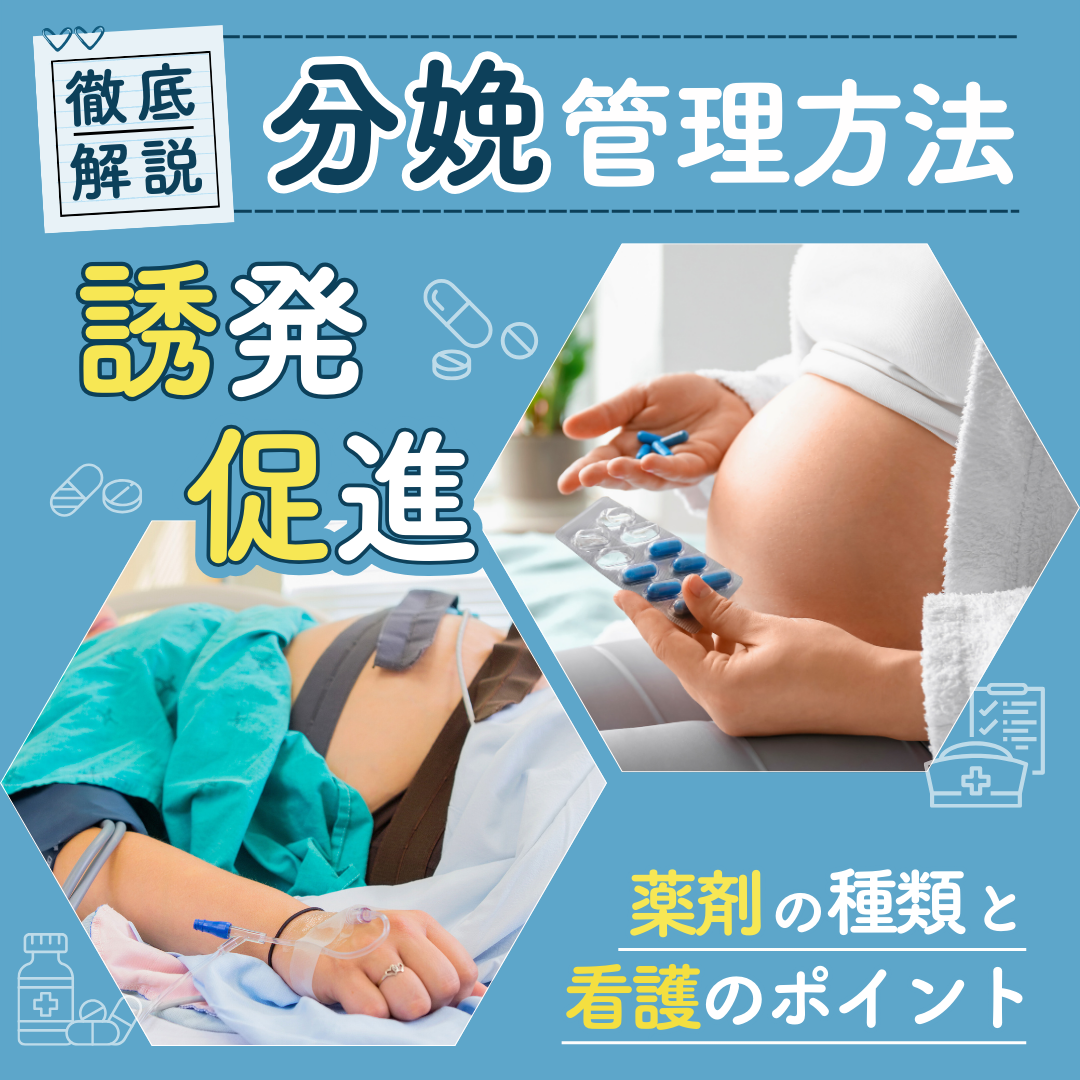ビショップスコアの計算方法と活用法|助産師・学生が押さえておきたいポイント
- ビショップスコア
- 分娩進行
1. ビショップスコアとは
子宮頸管と熟化
子宮頸管は子宮の下部に存在する子宮と膣をつなぐ管状の器官です。妊娠中は胎児を子宮内に保持するために子宮頸管は硬く閉じられています。出産が近付くと胎児が通過しやすいように柔らかくなっていきます。これを頸管熟化と言います。頸管熟化が始まると児頭の圧迫によって子宮口が開大し、子宮頸管の展退が起こり胎児が通過して出産に至ります。
歴史と背景
ビショップスコアは、1964年にEdward Bishop医師が「子宮頸管の成熟度を定量的に評価する」ために発表した方法です。当時、分娩誘発の成功率は子宮頸管の状態によって大きく左右されることが知られていましたが、判断は医師や助産師の主観に頼るしかありませんでした。そこで、子宮頸管の状態を客観的に表現するために開発されたのがビショップスコアです。
現代における意義
現在でも、分娩誘発の成否を判断する大切なツールとして使われています。特に妊娠後期に「予定日超過」や「母体・胎児の理由で分娩を進めたい」といった場面では、ビショップスコアを確認してから分娩誘発の方法や時期を決定するのが一般的です。
2. 評価項目と点数基準の解説
ビショップスコアは次の5項目で評価します。
項目 | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 |
子宮口開大度(cm) | 閉鎖 | 1–2 | 3–4 | 5–6 |
頸管展退度(%) | 0–30 | 40–50 | 60–70 | 80以上 |
児頭の位置(station) | −3 | −2 | −1〜0 | +1〜+2 |
頸管の硬さ | 硬 | 中等度 | 軟 | ― |
子宮口の位置 | 後方 | 中央 | 前方 | ― |
① 子宮口の開大度
子宮口がどれくらい開いているかをcm単位で評価します。「外子宮口」ではなく「内子宮口」で評価をします。
- 閉鎖=0点
- 1〜2cm=1点
- 3〜4cm=2点
- 5〜6cm=3点
② 頚管の展退度
頚管の長さがどれくらい短縮しているかを%で評価します。
- 0〜30%=0点
- 40〜50%=1点
- 60〜70%=2点
- 80%以上=3点
③ 児頭の下降度(Station)
児頭が骨盤内に陥入し固定しているのかどうか児頭と坐骨蕀(station±0)の位置関係を確認します。
- −3=0点
- −2=1点
- −1〜0=2点
- +1〜+2=3点
④ 頸管の硬さ
内診で触れたときの子宮頸管の感触を評価します。目安は「鼻翼状=硬」「口唇状=中」「マシュマロ状=軟」です。
- 硬=0点
- 中等度=1点
- 軟=2点
⑤ 子宮口の位置
子宮口が骨盤の中でどこに位置しているかをみます。子宮口は分娩が進むにつれて児頭の下降とともに後方から前方に移動してきます。
- 後方=0点
- 中央=1点
- 前方=2点
3. 合計点と意味
合計点は0〜13点となり、次のように解釈されます。
- 6点以下:子宮頸管が未熟。誘発前に熟化が必要となる。
- 7点以上:経産婦は7点以上で成熟と判断し誘発可とすることもある。施設によって判断が異なる。
- 9点以上:成熟。分娩誘発が有効とされる。
4. 計算方法と具体例
ビショップスコアの計算方法はとてもシンプルで、内診所見を表に当てはめて点数化して合計します。
症例例① 初産婦・40週・誘発前
開大1cm=1点、展退40%=1点、station−2=1点、頸管中等度=1点、子宮口後方=0点
→ 合計4点(未熟)
症例例② 経産婦・39週・誘発予定
開大3cm=2点、展退70%=2点、station−1=2点、頸管軟=2点、子宮口中央=1点
→ 合計9点(成熟)
症例例③ 陣痛発来・初産婦
開大5cm=3点、展退90%=3点、station0=2点、頸管軟=2点、子宮口前方=2点
→ 合計12点(十分成熟)
5. ビショップスコアの活用法
分娩誘発の適応判断
スコアが低い場合は、誘発に先立ってバルーンやプロスタグランジンで頸管熟化を行います。6点以下でそのまま誘発を始めると失敗のリスクが高まるため、必ず熟化を優先することが推奨されています。特に3点以下の非常に熟化が不良な例では原則、陣痛促進剤の投与は行いません。9点以上であれば24時間以内に90%、8点以上なら70〜80%が2日以内に分娩に至るとされています。初産婦はまだ1度も出産を経験していないため子宮頸管が熟化するまでに時間がかかることが多く、経産婦は出産を経験しているため子宮頸管も伸展されてて柔らかくなりやすく、子宮口の開大や展退が初産婦と比較してスムーズです。そのため同じ点数であっても初産婦・経産婦で分娩進行にはかなり差があります。例えば分娩誘発を開始する際にビショップスコアが6点であれば初産婦であれば陣痛促進剤を使用しても失敗する可能性も高いが、経産婦では分娩に至ることもあります。経産婦が点数が急激に上がるのに対し、初産婦は徐々に点数が上がっていくケースが多いです。これはフリードマン曲線など他の分娩進行を予測する指標でも同じことが言えます。
経膣分娩の予測
分娩誘発を開始する前の点数が高いほど経膣分娩が進みやすく、特に9点以上では自然な分娩経過に近い進行が期待できます。逆に点数が低いと、誘発をしても進まない可能性があり、母体や胎児への負担も大きくなります。分娩誘発の効果が得られない場合は頸管熟化の評価を再度行い、熟化の処置を行ってから再度誘発したり、分娩誘発の時期を改めることもあります。予定日超過での分娩誘発で分娩進行が見られない場合や分娩誘発中に母体または胎児に異常が見られる場合には経腟分娩を断念し、安全性の面から帝王切開を選択することもあります。
カンファレンスや記録での活用
スタッフ間で正しくビショップスコアを活用できていれば「Bishop 7点」と記録するだけで、子宮頸管の状態を伝えることができます。内診所見は評価者によって表現にばらつきが出やすいため、スコアを併用することで客観性を保ち、チーム全体での共通認識を持つことができます。
6. 注意点と限界
ビショップスコアはとても便利ですが、万能ではありません。
- 評価者の経験によって硬さや位置の解釈に差が出ることがあります。
- 骨盤の大きさや児頭の大きさ、母体合併症など他の因子も分娩進行を評価する上で重要です。
- 点数が低くても分娩が進むケースもある。(特に経産婦ではビショップスコアで未熟と判断されても分娩誘発が成功することが初産婦と比較して多い。)
- 点数が高くても帝王切開になるケースもあります。(巨大児・CPDなど子宮頸管が熟化していても児頭が加工してこない場合や分娩誘発中に母体または胎児に異常が認められる場合など)
したがって、ビショップスコアはあくまで分娩進行を評価する上での「1つの指標」として活用し、母体と胎児の全体像をふまえて総合的に判断することが必要です。
7. 学び方の工夫
- 2点を覚えておくのがおすすめ
2点の内診所見は子宮口開大度「3〜4cm」、頸管の展退度「60〜70%」、児頭の下降度「-1〜0」、頸管の硬さ「軟」、子宮口の位置「前」です。この内診所見をフリードマン曲線に当てはめると「加速期」〜「極期」の曲線の傾きが急になる部分とほぼ一致します。子宮頸管の熟化が進み、これから分娩が一気に進行すると予測される時期です。
- 実習では必ず「自分の評価」と「指導者の評価」を比較して感覚を磨く
内診はある程度の数をこなして、経験を積むことで感覚が磨かれていきます。経験が浅いうちは自分の内診所見と医師や先輩助産師の内診所見が異なることもあります。正しい評価や判断をするためには内診技術を磨いて行く必要があります。
ビショップスコアは、分娩誘発や経膣分娩の見通しを立てる上で欠かせない指標です。5つの項目を正しく評価して合計することで、子宮頸管の成熟度を客観的に把握できます。「6点以下は未熟」「9点以上は成熟」という目安を覚えておくと、臨床判断がしやすくなります。しかし、ビショップスコアはあくまで参考指標です。点数がすべてを決めるわけではなく、母体や胎児の全体的な状態をふまえた総合的な判断が求められます。新人助産師さんや学生さんにとっては、このスコアを学ぶことが、分娩の理解を深める第一歩になるでしょう。実習や臨床の中で繰り返し評価を行い、先輩と所見を照らし合わせながら感覚を磨いていくことが大切です。ビショップスコアを正しく活用できるようになると、分娩誘発の判断や申し送りに自信が持てるようになります。ぜひ日々の学びに取り入れて、実践力を育てていってください。
引用・参考文献
病気がみえるvol.10 産科
産婦人科診療ガイドライン 産科編2020
日本助産学会 ガイドライン委員会:エビデンスに基づく助産ガイドラインー妊娠期・分娩期・産褥期2020
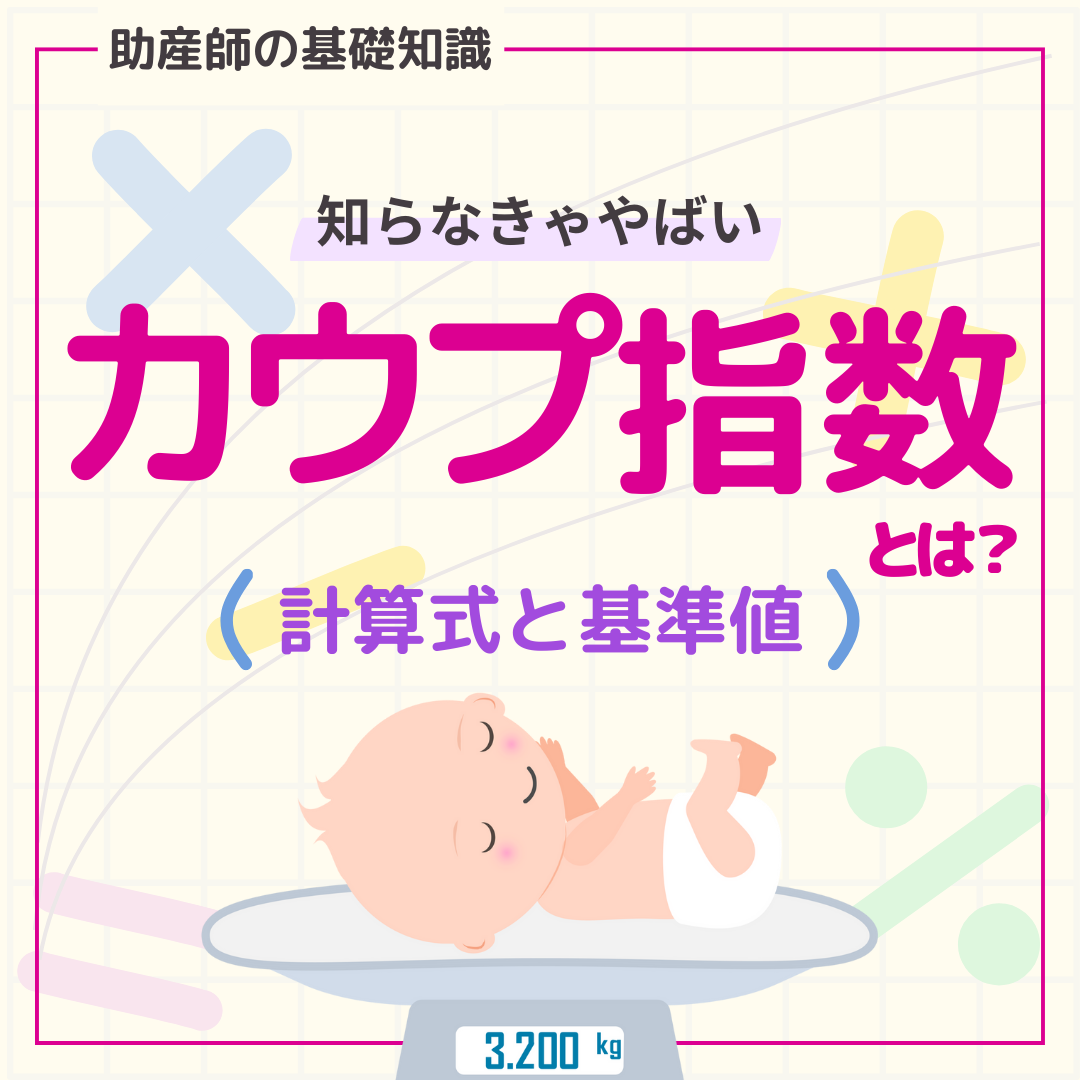
【知らなきゃやばい】カウプ指数とは?計算式と基準値|助産師の基礎知識
- 産後ケア
- 赤ちゃんの発育
- 育児相談

【新人助産師と学生が押さえておきたい】CTG(NST)モニターの基礎知識|基線・基線細変動・一過性頻脈の見方をわかりやすく解説
- CTGモニター
- モニター判読
.png)
【助産師必見】超音波検査での胎児計測|基本項目と正しい計測方法を徹底解説
- 超音波検査
- 助産師によるエコー検査

“なんとなく”の指導はもう終わり。エビデデンスに基づく乳頭ケアの指導方法|妊婦さんの「やってみよう」を引き出す助産師の言葉は?
- 乳頭マッサージ
- 妊娠中

明日から使える!妊婦さんの不安を解消する「会陰マッサージ」指導のポイント|最新のエビデンスも解説
- 会陰部マッサージ
- 会陰部切開
- 経腟分娩
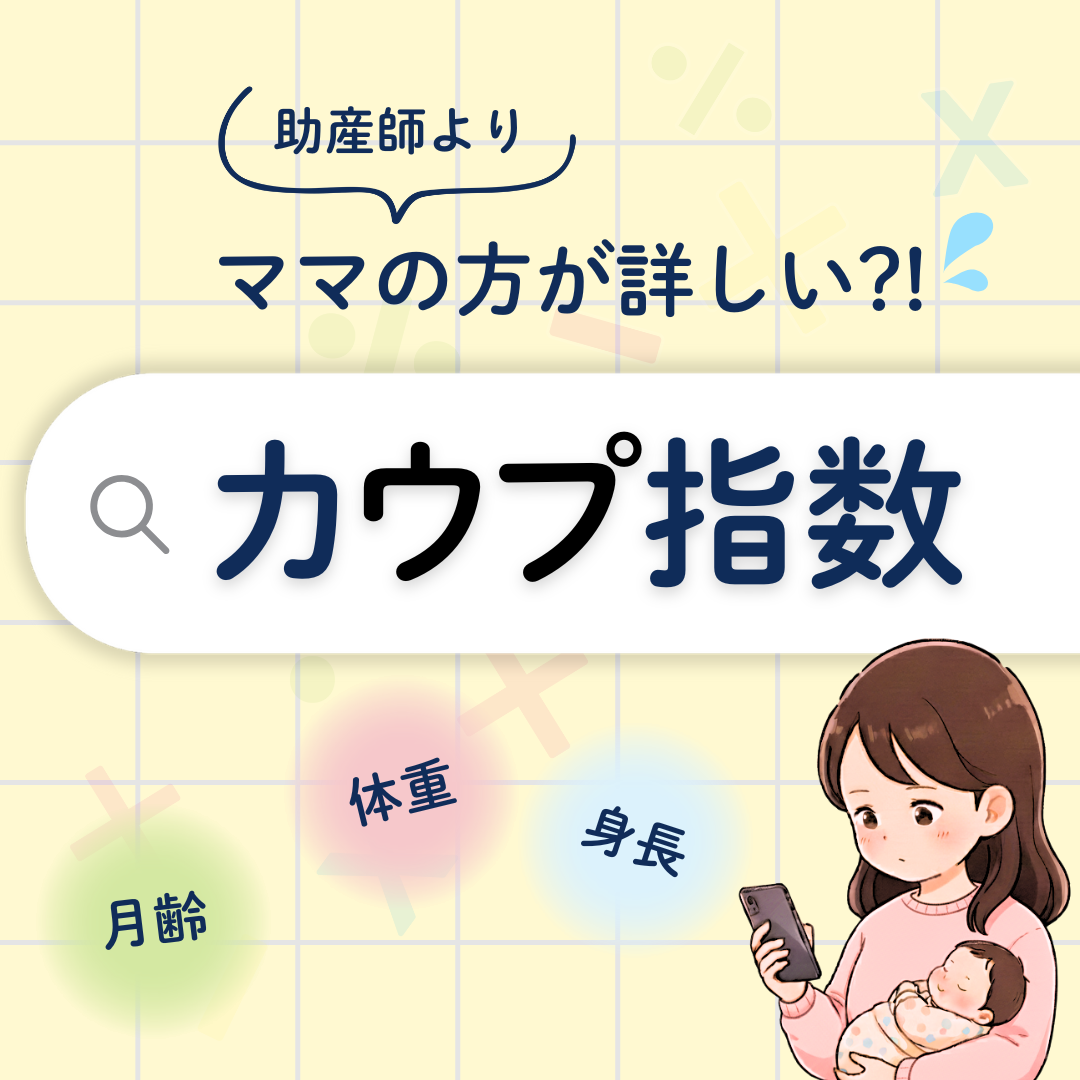
【月間3.8万検索の衝撃】ママの方が詳しいかも?助産師が知っておくべき“カウプ指数”の常識
- カウプ指数
- 月齢
- 乳幼児