
Late Preterm児(後期早産児)とは?特徴・リスク・看護のポイントを徹底解説
- 早産
- Late Preterm児
- 後期早産児
定義と発達の背景
Late preterm児は早産児のカテゴリーに入り、正期産(37週0日〜41週6日)の直前にあたる時期に生まれます。この時期の胎児は急速な体重増加と臓器の最終的な成熟過程にあり、特に脳容量は妊娠35週から40週の間に約35〜40%増加するといわれています。脳の構造だけでなく、神経回路の形成やシナプスの発達も活発で、呼吸や循環の制御、体温保持、哺乳動作など生命維持に直結する機能が短期間で急速に整えられていく時期です。つまり、この数週間で得られる発達の伸びしろを失った状態で出生すると、胎外環境で適応するための準備が整っていない状況に置かれることになります。Late preterm児は母体合併症(妊娠高血圧症候群、糖尿病、甲状腺機能異常、自己免疫疾患など)、切迫早産、多胎妊娠、前期破水、胎児発育不全などの背景を持つ場合が多く、出生前からリスク管理を行うことが重要になります。

Late preterm児の特徴とリスク
呼吸器系
Late preterm児の肺の成熟は十分ではなく、肺胞の表面張力を低下させるサーファクタントの産生が不十分なことがあります。サーファクタントは在胎34週頃から増えますが、36週時点では量や質が成熟児に及ばないことがあり、肺胞虚脱を防ぎきれず呼吸窮迫症候群(RDS)が発症しやすくなります。さらに肺間質や肺血管の適応も不十分で、羊水の排出・吸収が遅れると一過性多呼吸(TTN)が生じやすくなります。症状は出生後すぐに出現する場合もあれば、数時間後に増悪することもあります。呼吸数増加や呻吟、陥没呼吸は重要なサインで、見逃すと急速に低酸素血症へ進行します。出生直後はSpO₂モニタリングを継続し、必要時は保育器に収容し、酸素投与や持続陽圧呼吸(CPAP)で呼吸を補助します。
循環器系
出生後、通常であれば動脈管は酸素分圧の上昇とプロスタグランジンE₂の減少によって収縮します。しかしLate preterm児は呼吸機能の未熟さにより酸素分圧が十分に上がらず、またプロスタグランジンを分解する酵素活性も低いため閉鎖が遅れます。動脈管開存(PDA)が続くと肺血流が増え、肺うっ血や呼吸困難を悪化させます。動脈管開存(PDA)が続いていると哺乳後に呼吸数が増える、SpO₂が低下するといった所見が見られることもあります。そのため哺乳中や哺乳後の呼吸状態の変化を注意深く観察する必要があります。脈拍、末梢温、毛細血管再充満時間(CRT)、心雑音の有無、呼吸状態の変化は循環異常の早期発見につながるため、日々の観察で意識して確認しましょう。
体温調節
Late preterm児は皮下脂肪や褐色脂肪が少なく、熱産生力が弱い上に体表面積が大きく熱喪失しやすいという特徴があります。低体温は酸素消費と糖消費を増やし、呼吸抑制や低血糖を引き起こします。また体温低下は酸素解離曲線を左方にシフトさせ、組織への酸素供給が低下するため、全身の代謝バランスが崩れやすくなります。出生後すぐのドライアップ(皮膚乾燥)と適切な保温環境は必須で、カンガルーケアは保温と母子の愛着形成の両面から有効なケアと言われています。
栄養・哺乳
吸啜・嚥下・呼吸の協調運動は在胎37週頃に完成すると言われています。Late preterm児ではこの協調性が未熟で哺乳中に呼吸が乱れたり、疲れて途中で眠ってしまうことが多くあります。そのため摂取量不足による体重減少や低血糖、黄疸悪化のリスクがあります。授乳開始直後は勢いよく吸啜していても、数分後には疲れて動きが止まってしまったり、呼吸が速くなりチアノーゼが出現することもあります。授乳は短時間・高頻度を心がけ、哺乳量を確保していく必要があります。
代謝と低血糖
Late preterm児は肝臓のグリコーゲン蓄積が少なく、糖新生能力も低いため低血糖を起こしやすいです。特に哺乳不良や低体温では注意が必要になります。低血糖が持続すると脳障害のリスクがあるため、必要に応じて血糖測定を行い、低血糖を認めた場合には早期の介入が必要です。
黄疸
肝酵素活性が低くビリルビン排泄が遅れるほか、腸内細菌叢の形成も遅いため腸肝循環が促進され、黄疸が進行しやすいです。正期産児より黄疸が出やすいだけでなく、重症化もしやすい傾向があるため黄疸の治療を開始する基準も低く設定されています。Late preterm児は脳(血液脳関門)が未熟でビリルビンが脳に移行しやすく、核黄疸のリスクも高いためより慎重に観察することが必要です。
感染
IgG移行量が少なく免疫能が未熟で、敗血症や肺炎の発症リスクが高いです。初期症状が不明瞭なことが多く、哺乳力低下や傾眠など微細な変化を見逃さない観察が必要です。
神経系
脳の髄鞘化は進行途中で、中枢神経による呼吸や体温制御も不安定です。筋緊張や原始反射が弱いことがあり、授乳姿勢保持や覚醒維持が難しいケースもあります。
観察と看護のポイント
Late preterm児の安全な管理には、出生直後から退院まで、そして退院してからも「観察→評価→必要時の介入」を繰り返すことが大切です。成熟児に比べ、症状の出方が不明瞭で分かりにくいのに進行は早いことが多いため判断が難しいことがあります。「なぜ見るのか」「どう見るのか」「異常時の対応」「見逃した場合のリスク」まで理解しておくことが大切です。
呼吸状態
呼吸障害はLate preterm児において最も注意すべき合併症の一つです。肺サーファクタントの不足や肺内液の吸収遅延、PDAによる肺うっ血などが原因で、出生直後からの呼吸数増加、努力呼吸、呻吟、陥没呼吸が見られることがあります。観察では、呼吸数を1分間しっかり数え、胸郭・鎖骨上・肋間の陥没の有無、呼吸音、鼻翼呼吸、啼泣の強さ、SpO₂の推移をチェックします。授乳中の呼吸状態の変化も重要で、哺乳中にSpO₂が低下した場合は直ちに授乳を中止し安静・酸素投与を検討します。呼吸状態の悪化は急速な低酸素血症から循環不全や脳障害に至る危険があり、重要な観察ポイントと言えます。
循環状態
PDAや心筋の未熟性により循環動態は不安定になりやすく、呼吸状態にも直結します。観察では心拍数、心雑音の有無、四肢末梢温、毛細血管再充満時間(CRT)、皮膚色を確認します。哺乳後の頻脈やSpO₂低下、末梢冷感の出現は心負荷のサインであり、医師への報告が必要です。
体温
熱産生力の低さと熱喪失のしやすさから低体温を起こしやすいです。直腸温や腋窩温を定期的に測定し、保温環境を適切に維持します。体温低下は酸素消費増加や低血糖の誘因となるだけでなく、酸素解離曲線の左方シフトにより組織酸素供給が低下します。軽度の低体温でも代謝バランスを崩すため、早期の補正が必要です。
哺乳状況
哺乳は栄養補給だけでなく低血糖・黄疸予防のためにも重要です。Late preterm児は疲れやすく、哺乳中に眠ってしまうことが多いため、授乳時間は10〜15分を目安に設定し、疲労サインがあれば中止します。哺乳後の補足(搾乳、カップフィーディング、哺乳瓶)で摂取量を確保します。授乳間隔は昼夜問わず3時間以内を厳守します。観察では吸啜の強さ、リズム、哺乳中の呼吸変化、授乳後の満足度(泣きやまない、すぐ寝てしまうなど)を記録します。
血糖値
低血糖は哺乳不良や低体温と密接に関連します。出生直後から定期的に血糖を測定し、低値であれば直ちに哺乳または静脈内糖投与を行います。無症状の低血糖も多く、症状が出た時点ではすでに進行していることがあるため、予防的測定が重要です。
黄疸
退院後にピークを迎えるケースも多いため、経皮ビリルビン測定や採血で退院後も継続的に黄疸の経過を見る必要がある場合があります。顔面だけでなく胸・腹部、四肢まで黄疸が進展していないか確認します。黄疸値の上昇を認めた場合は光線療法や入院管理を検討します。
感染兆候
免疫未熟のため感染症の進行は速く、初期症状は哺乳力低下や傾眠といった非特異的なものが多いです。体温の上下変動、呼吸状態の変化、反応性の低下を敏感に察知することが必要です。感染を疑う場合には速やかに採血・培養を行い、抗菌薬投与の準備をします。
家族支援と退院後フォロー
情報提供のタイミングと方法
家族への説明は入院中の複数の場面で繰り返し行い、授乳支援や体温測定など日常ケアの中で「なぜこの観察が必要か」を具体的に示します。例えば「哺乳中に呼吸が速くなったら一度やめて休ませであげると、呼吸が整って安全に哺乳できます」など、行動と理由をセットで説明します。
退院前に伝えるべき観察ポイント
退院後も家庭で続けられる観察項目として、呼吸(速さ・陥没呼吸・チアノーゼ)、体温(36.5〜37.5℃)、哺乳量と回数(3時間以内)、排泄(尿6回以上)、黄疸の進行などを具体的な基準とともに伝えます。さらに「この状態になったらすぐ受診」という緊急時の判断基準も伝えておくことが必要です。Late preterm児は保育器に収容され母児分離となることもあるため母児同室で過ごせなかった、または同室で過ごした期間が短かった場合には育児技術の習得が不十分であるケースもあります。退院までに授乳、沐浴、おむつ交換などの基本的な育児技術を習得できているか確認しましょう。
心理的支援
Late preterm児は外見が成熟児に近いため家族がリスクを過小評価してしまうことがあります。その反面、退院後は「本当に育てられるか」という不安も抱きやすいです。「注意は必要だが家族の観察で守れる」こと、過度に心配しすぎなくても良いこと、家庭での観察の仕方を家族の理解度に合わせて繰り返し伝えていくことで家族の不安を軽減していくことが助産師の重要な役割でもあります。
退院後のフォロー体制
退院後1週間以内で再診予約をし、退院後の経過を観察します。また保健師に情報共有し、哺乳や体重増加が不安定な場合や家族が不安を抱えている場合には早めの訪問や地域での継続フォローを依頼します。夜間・休日でも対応可能な医療機関の連絡先一覧を渡すなどして緊急時の対応にも備えておきましょう。
長期的な発達フォロー
Late preterm児は身体的問題が落ち着いても、発達や行動面で微細な遅れが見られることがあります。特に言語発達などは就学前まで経過観察することが望ましいです。退院後も定期的な健診や発達フォローを案内し、継続的に発達をフォローしていきます。
Late preterm児は見た目は成熟児でも機能は未熟で、呼吸・循環・体温・哺乳・代謝・免疫に多くのリスクを抱えます。助産師はLate preterm児の背景を理解し、観察とケアの根拠を持ってケアにあたることが大切です。また、家族支援と地域連携を含めた継続的な支援は赤ちゃんの成長・発達を見守る上で重要です。
参考文献
- 日本新生児成育医学会『新生児蘇生法(NCPR)テキスト 第4版』 メディカ出版, 2020
- 日本周産期・新生児医学会『周産期医療ガイドライン 2022年度版 新生児編』
- 日本産科婦人科学会『産科ガイドライン 2023年度版』
- 『新生児学入門』医学書院, 2021
- 『NICUマニュアル』.南江堂, 2022

【新人助産師と学生が押さえておきたい】CTG(NST)モニターの基礎知識|基線・基線細変動・一過性頻脈の見方をわかりやすく解説
- CTGモニター
- モニター判読
.png)
【助産師必見】超音波検査での胎児計測|基本項目と正しい計測方法を徹底解説
- 超音波検査
- 助産師によるエコー検査

“なんとなく”の指導はもう終わり。エビデデンスに基づく乳頭ケアの指導方法|妊婦さんの「やってみよう」を引き出す助産師の言葉は?
- 乳頭マッサージ
- 妊娠中

明日から使える!妊婦さんの不安を解消する「会陰マッサージ」指導のポイント|最新のエビデンスも解説
- 会陰部マッサージ
- 会陰部切開
- 経腟分娩
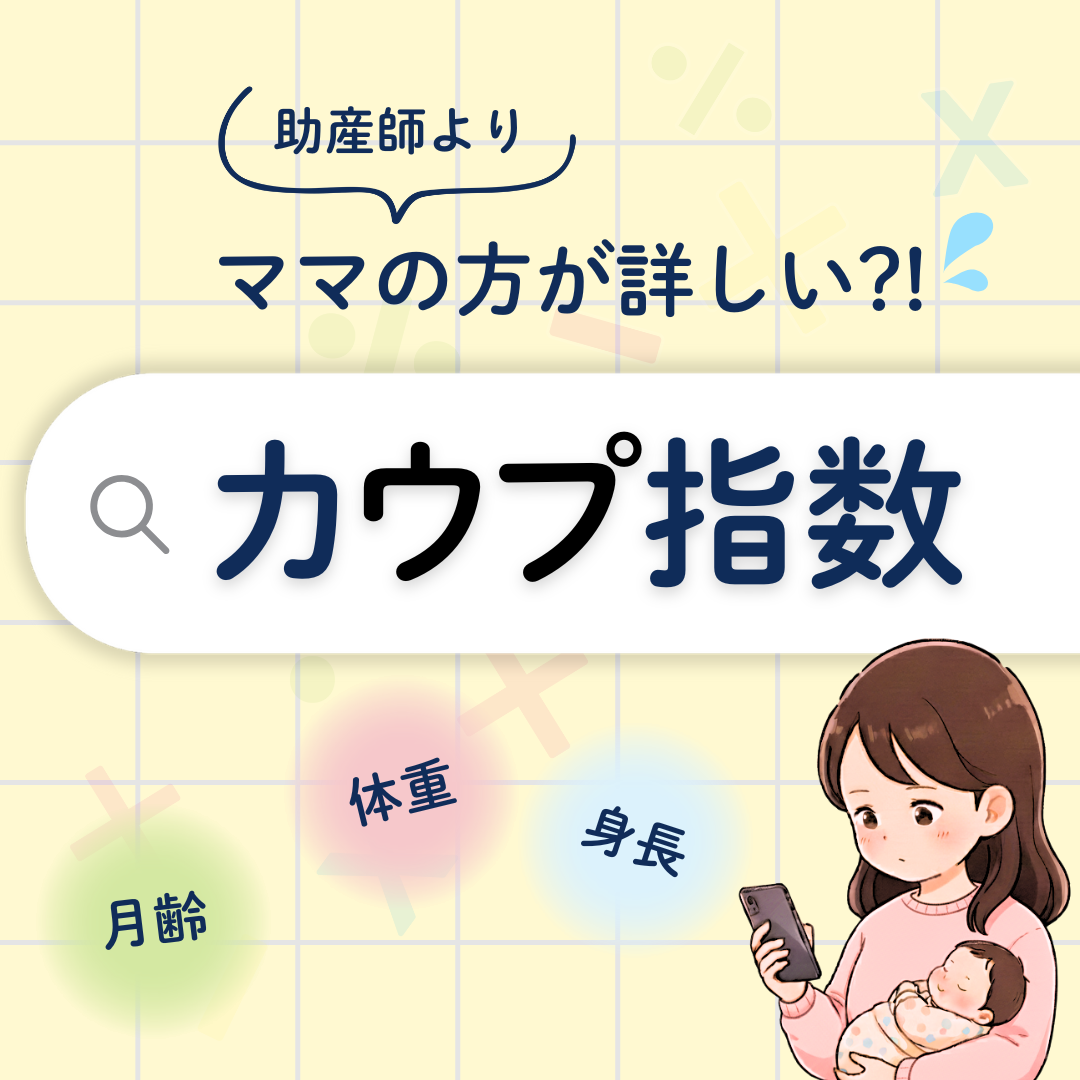
【月間3.8万検索の衝撃】ママの方が詳しいかも?助産師が知っておくべき“カウプ指数”の常識
- カウプ指数
- 月齢
- 乳幼児

Late Preterm児(後期早産児)とは?特徴・リスク・看護のポイントを徹底解説
- 早産
- Late Preterm児
- 後期早産児

