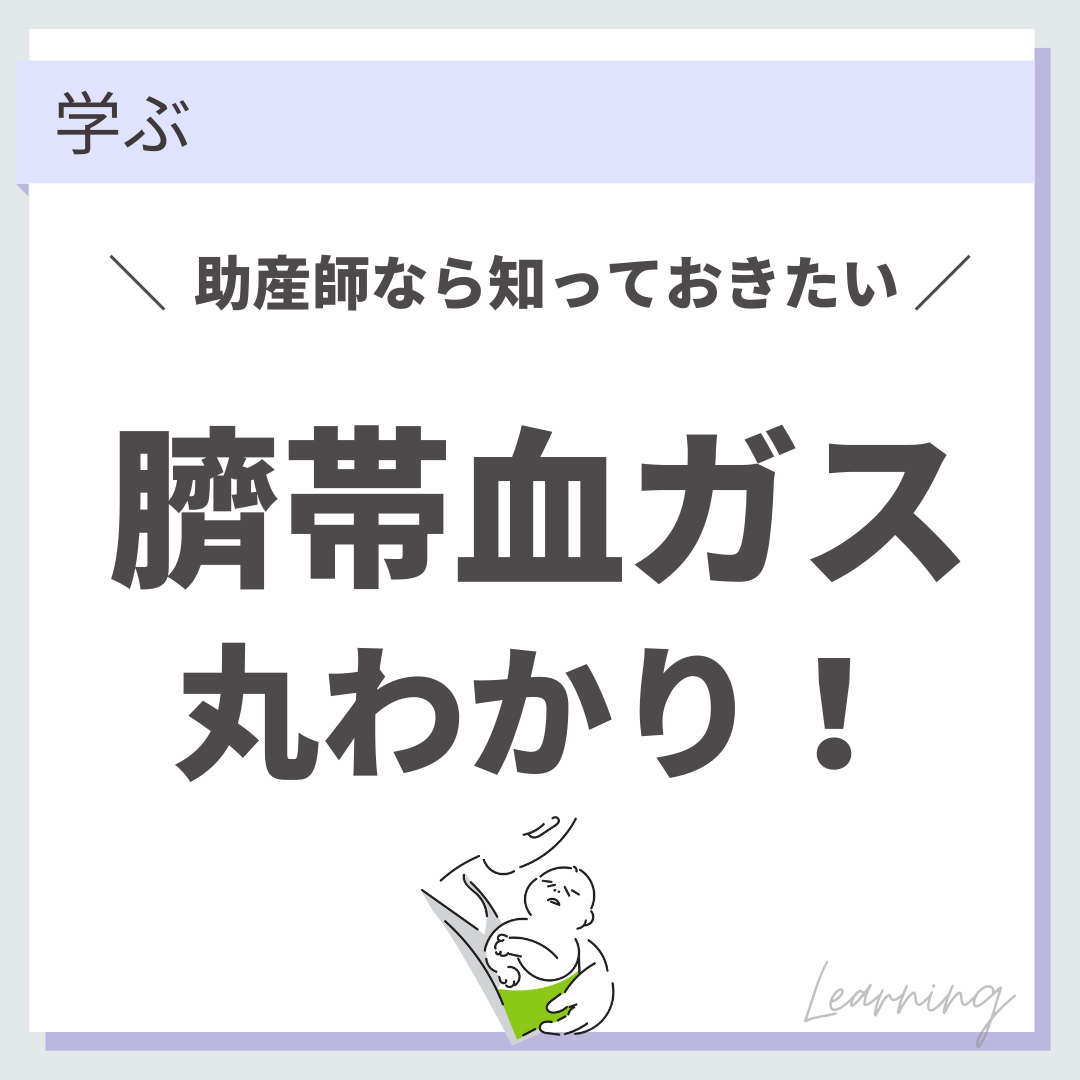助産師が臍帯血ガスを“読める”ようになるべき理由|“数字の裏側”を完全解説
- 臍帯血ガス
- 血ガス
1. 臍帯血ガスが示す意味と重要性
臍帯血ガスは、胎児が分娩中にどれだけ酸素不足やストレスを受けたか、客観的に示す唯一のデータです。
臍帯血ガスで分かること
- 胎児がアシドーシス(低酸素状態)だったか、アルカローシスではないか
- 酸塩基バランスの崩れ方(アシドーシスが呼吸性か代謝性か)
CTG(胎児心拍モニタリング)は分娩中の状態を「予測」するツールですが、臍帯血ガスは「結果」を明確に示します。つまり、臍帯血ガスデータはその分娩の安全性を証明する根拠ともなるのです。
2. 助産師が臍帯血ガスを理解すべき理由
① 医療安全と説明責任のため
pHやBEがどの程度だったかは、「適切な分娩管理がなされたか」を評価する材料になります。助産師がこの意味を理解していないと、分娩後の報告や記録に不備が生じるリスクがあります。
② 分娩管理の質を高めるため
臍帯血ガスは、分娩のすべての経過を反映した結果です。
分娩第1期・第2期遷延への対応はどうだったか、促進剤の使用、吸引や鉗子のタイミングが妥当だったのか。それぞれの時期で、CTGの変化に気づき、対応できていたのか。これらを振り返るためにはCTGの振り返りだけでなく、臍帯血ガスという客観的指標を読む力が必要です。
③ 新生児ケアの質を高めるため
臍帯血ガスの結果から、新生児蘇生の必要性やNICU搬送の判断の妥当性を検証できます。
たとえば、pHが極端に低い児は、出生直後に元気であってもその後の低体温療法や脳保護管理の対象になる可能性があります。データを理解できる助産師は、先を読んだ準備と対応ができるようになります。
3. 臍帯血ガスを見て、助産師がやるべきこと
臍帯血ガスが読めるようになったら、次の3つの視点で行動します。
① 分娩経過の振り返りと評価
臍帯血ガスの結果は、自分の助産診断を振り返るためのデータとなります。
- 医師に報告をしたタイミング
- 促進剤の投与を検討・相談したタイミング
- 吸引・鉗子分娩または帝王切開を検討・相談したタイミング
- 会陰切開を依頼するタイミング
- 頻収縮になっていたときの相談や対応
- CTGで波形レベル2~4の時の対応とそのタイミング(スタッフコール、体位変換、酸素投与など)
結果を分析することで、次の分娩に生かせる具体的な改善点が見えてきます。
② チーム内共有と報告
臍帯血ガスは、医師だけでなく分娩に携わるスタッフ全体で共有すべき情報です。
助産師が結果を理解した上で報告することで、スタッフ全体で医療介入のタイミングや方法について振り返りを行い次の分娩に活かすことができます。
③ 保護者への説明補助
臍帯血ガスは、ママや家族への説明資料としても重要です。
「急いで吸引したけど赤ちゃんは元気?」という疑問に対して、「赤ちゃんが泣いていて色もピンクだから大丈夫」という視覚的なものだけではなく、数値という客観的な裏付けを示すことでママや家族の安心につながります。

4. ゴールは読めることではなく活かすこと
臍帯血ガスを読む目的は、数字の意味を知ることだけではなく行動を変えることです。
- 自分自身の分娩期のケアや観察、介助技術の振り返りになる
- 分娩後のカンファレンスで分析し改善点を挙げる
- ハイリスク妊婦の次回管理に活かす材料とする
- 教育資料に活用する
- 新生児フォローアップの情報に役立てる
臍帯血ガスは、数値を確認してその分娩を終わりにするものではなく、次の安全な分娩につなげる材料なのです。
5. 臍帯血ガスと法的リスク
臍帯血ガスは、その場にいなくても胎児がどの程度の低酸素状態だったか判断することができます。そのため産科医療の訴訟では、臍帯血ガスは必ず確認されます。
実際の事例(匿名)
- 正常分娩だったが、新生児に神経学的後遺症が残ったケース
- カルテには「異常なし」と記載されていたが、臍帯血ガスではpH 6.95
- 「適切な対応ができたか」を問われる裁判で、臍帯血ガスの解釈が争点に
助産師としては、結果を見て医師に適切に報告できるか、分娩経過とセットで正しく結果を理解し説明できるかが重要です。
6. 助産師が臍帯血ガスを活かすための勉強法
臍帯血ガスを読む力は、数値暗記ではなく「意味を理解すること」が大切です。
おすすめの学習ステップ
- 基礎を押さえる
→ 正常値・異常値と、その背景を理解(pH、BE、pCO₂の意味) - ケースで考える
→ 「この分娩でこの結果、なぜ?」を考える - カンファレンスで考えを発言する
→ 発言することで医師や他の助産師の様々な分析視点を得ることが出来る - 関連ガイドラインを読む
→ 産科医療補償制度の再発防止報告やNCPR(新生児蘇生法)の教材など - 臨床で毎回確認する習慣をつける
→ データをただ記録するだけでなく、自分で解釈する練習
ツール活用
- 臨床ノートやポケットマニュアル
- 院内の教育資料を見直す
- SNSやオンライン勉強会での共有
どれだけ分娩介助件数を重ねても、助産師にとって分娩は不安やリスクがつきものです。臍帯血ガスを理解し活用することは、助産師にとって単なる知識習得ではなく分娩の質を保証し、説明責任を果たすための確固たる根拠となります。また、正しく結果を読み解き適切に報告、介入ができる能力は、チーム医療で信頼される必須スキルです。
臍帯血ガスデータを「読む」から「活かす」へ。これが、臍帯血ガスに対する助産師の新しいスタンダードです。臍帯血ガスについて詳しく学び、明日の分娩から学びを活かしましょう。
【参考文献】

【新人助産師と学生が押さえておきたい】CTG(NST)モニターの基礎知識|基線・基線細変動・一過性頻脈の見方をわかりやすく解説
- CTGモニター
- モニター判読
.png)
【助産師必見】超音波検査での胎児計測|基本項目と正しい計測方法を徹底解説
- 超音波検査
- 助産師によるエコー検査

“なんとなく”の指導はもう終わり。エビデデンスに基づく乳頭ケアの指導方法|妊婦さんの「やってみよう」を引き出す助産師の言葉は?
- 乳頭マッサージ
- 妊娠中

明日から使える!妊婦さんの不安を解消する「会陰マッサージ」指導のポイント|最新のエビデンスも解説
- 会陰部マッサージ
- 会陰部切開
- 経腟分娩
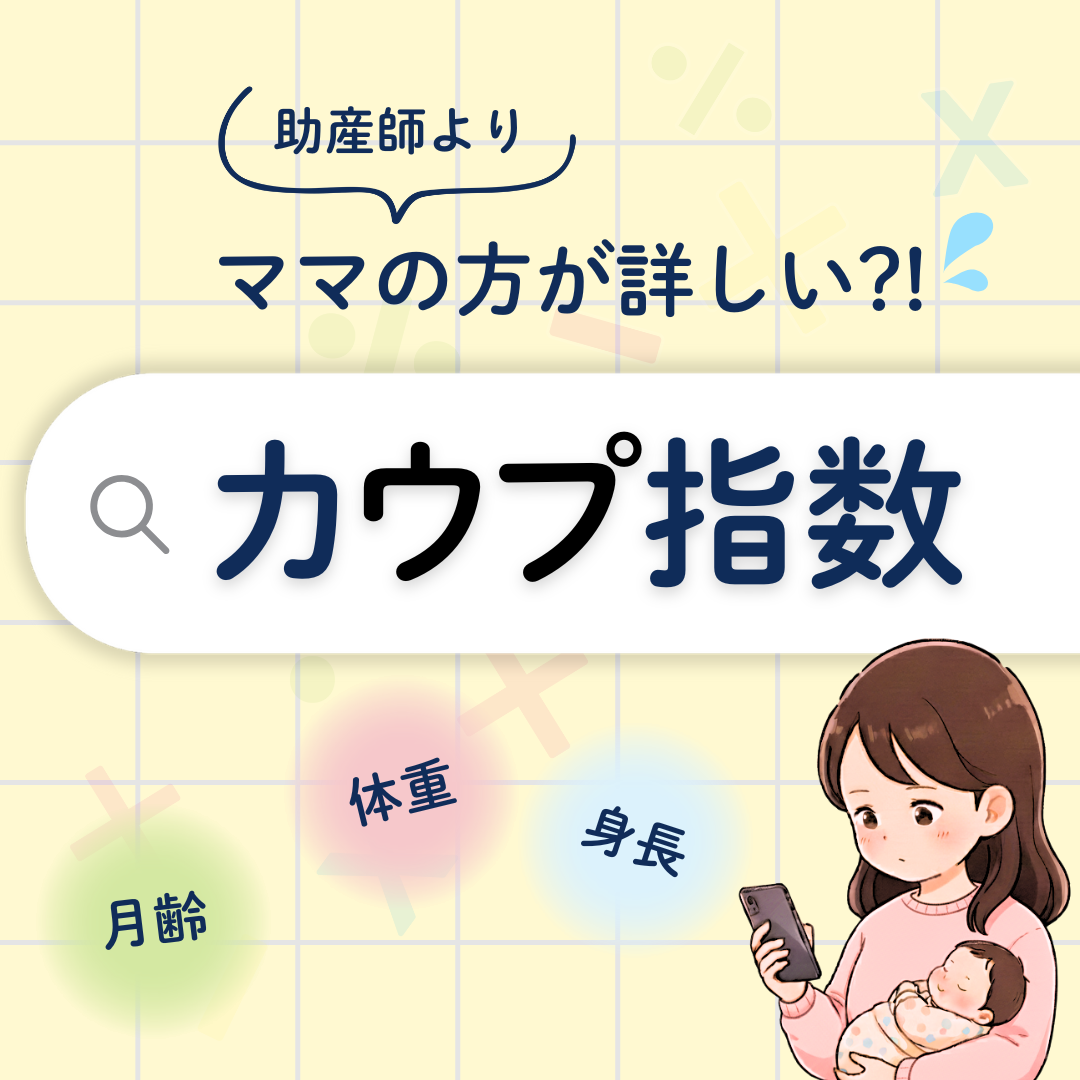
【月間3.8万検索の衝撃】ママの方が詳しいかも?助産師が知っておくべき“カウプ指数”の常識
- カウプ指数
- 月齢
- 乳幼児

Late Preterm児(後期早産児)とは?特徴・リスク・看護のポイントを徹底解説
- 早産
- Late Preterm児
- 後期早産児