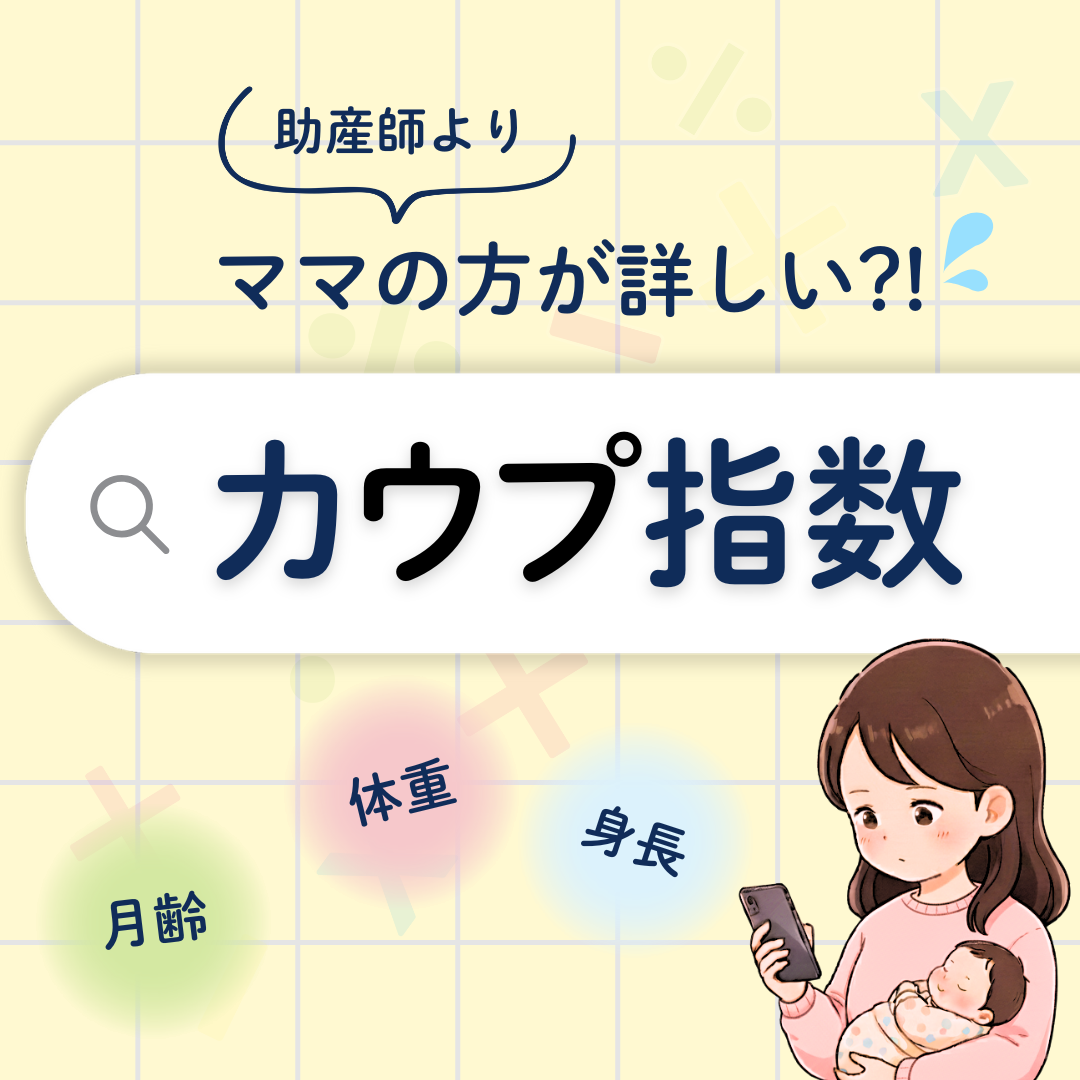今回は、一般社団法人マタニティトレーニング&ケア協会代表の山村美暖さんと一緒に臨月の運動について考えていこうと思います。山村さんは、もともとパーソナルトレーナーとして芸能界の方や医療者の方に向けたサポートをされていました。ご自身の第一子妊娠中にマタニティトレーニングを学ぶため、文化が進んでいるアメリカに渡り、本場アメリカのマタニティトレーナーの資格を取得。その後も論文をベースに勉強と実践を繰り返し、第2子では理想としていた「いきまないお産」も達成されています。

じょさんしnavi柏村
「産後は骨盤底筋群が弱くなるとかゆるむ」とよく表現していますが、実際産後の骨盤底筋はどのような状態になりますか?

山村
よく聞く表現ですよね。だから「締めないといけない」「鍛えないといけない」と表現されます。ただしイメージしてほしいのは「妊婦さん自身が骨盤底筋」という状態です。10か月間、体の変化に耐えて、重い体と24時間生活して、お産という大仕事を終えて…過重労働の状態なんです。つまり必要なのは締める・鍛える、ではなくまずは休ませてあげることが必要です。

じょさんしnavi柏村
骨盤底筋といえば産後のトラブルの1つに尿漏れがありますよね。尿漏れ=緩んでいる、だから骨盤底筋も締めなきゃ、という認識のズレが起こっていたんですね。

山村
そうなんです。まずは骨盤底筋がリラックスできる状態を作ってあげることが必要です。ただし休ませるというのはただ横になっているのではなくて、骨盤底筋が苦労を肩代わりしていたほかの筋肉たちを呼び戻してあげるという視点が大切です。


じょさんしnavi柏村
骨盤底筋を意識することが必要なんですね。それでは、実際に臨床でよく紹介しているケーゲル体操は、産後の身体にとって有効なのでしょうか。

山村
産後にケーゲル体操で骨盤底筋を収縮させる運動をすると、尿漏れが予防されるということは研究でも証明されていますし、効果はあります。だから産後のママ達にはケーゲル体操を知ってもらいたいし、骨盤底筋を意識して生活してほしいです。ただし先ほども言ったように、締める・鍛えるではなく「そこに骨盤底筋というものがある」「それは呼吸とつながっている」という認識を与えてあげるだけでいいんです。

じょさんしnavi柏村
呼吸というワードがでてきましたね。妊娠中や分娩中に呼吸は大事という認識はありましたが、産後においても呼吸は大事なのでしょうか。

山村
妊娠出産という特殊な状況を乗り越えた身体なので「妊娠前の身体に戻してあげる」という点を考えていくと、骨盤底筋を含めたインナーにアプローチする必要があります。


じょさんしnavi柏村
産後すぐにできる運動として骨盤底筋へのアプローチだけでいいのでしょうか?

山村
産後の身体を骨盤底筋単体で語ることは多いですが、周産期以外ではコアハウスやインナーユニットとして、4種類の筋肉の1つとして考えられることが多いです。4つの筋肉とは横隔膜、多裂筋、腹横筋、そして骨盤底筋です。
何度も繰り返しますが骨盤底筋は産後非常に疲労していますし、単体でトレーニングするものではありません。そもそも4つがセットで働く構造ですから、他の3つの部分と合わせてアプローチしてあげてほしいなと思います。

じょさんしnavi柏村
産後の入院中にもできるおすすめの運動などあれば、教えていただきたいです。

山村
産後1〜2日目は、まずとにかく深呼吸を繰り返すこと。この時、横隔膜を動かすことが大切なので、肋骨の動きを意識して呼吸の練習をしてほしいです。特に1日目のまだおっぱいが張っていないうちは、うつぶせでの深呼吸がおすすめです。背骨が圧迫されていない状態で呼吸をすることがすごく大切なんです。

じょさんしnavi柏村
そもそも産後に呼吸の練習をするという思考はなかったので、私にとってはうつぶせで深呼吸をするというのは斜め上をいく視点でした。

山村
ヨガでいうチャイルドポーズのように、うつぶせになって背中を解放した姿勢をとることで呼吸の練習をすることが有効です。これは横隔膜にアプローチしているようですが、結果的には骨盤底筋にも良い効果をもたらしてくれます。


じょさんしnavi柏村
なるほど。つまりケーゲル体操とか産褥体操というより、まずは呼吸筋、インナーマッスルなどを使ってみるということが、産後すぐの身体にとっては良いということですね。

山村
産後すぐの身体にとっては、運動やダイエットを始める以前に、まずは呼吸の機能を取り戻してあげるということが非常に大切です。
呼吸するだけであれば産後すごくクタクタの状態でも取り組みやすいので、何か動作を始めることよりもまずは呼吸の練習を始めてほしいです。
4つの筋肉のうちの残り2つは、背骨についている多裂筋と、お腹でコルセットの役割をしている腹横筋です。産後は背骨の状態も良い状態ではないので、いかに妊娠前の状態へ戻してあげられるかが産後のトラブルを防ぐポイントになります。

じょさんしnavi柏村
全てのアプローチの最初に呼吸の練習をするべき理由はズバリなんででしょうか?

山村
呼吸が正しくできていないと、インナーマッスルが使われにくくなり、アウターマッスルで頑張りすぎてしまいます。それが結果的に「痛み」や「体型の崩れ」につながってしまうからです。

じょさんしnavi柏村
なるほど。ケーゲル体操などをするにあたっても、インナーマッスルを使うことができないと最大限効果が発揮できないということですか?

山村
そういうことです。例えばケーゲル体操ってお尻を上げる動作に着目されると思うのですが、重要なのは動作ではなく「横隔膜や骨盤底筋が動いていることを意識して呼吸ができているかどうか」です。あくまでもおしりをあげる、ということは付属的なものだと考えてほしいです。

じょさんしnavi柏村
産後すぐに腰をあげることが難しい人も多いですよね。例えば産後1〜2日目は呼吸の練習をするとすれば、ケーゲル体操はいつ頃から始めるべきでしょうか。

山村
産後すぐの骨盤底筋訓練が尿漏れを防ぐという研究結果がありましたが、何か動作を行っての骨盤底筋群訓練ではなくただ仰向けになって呼吸の練習をしているという骨盤底筋訓練を指しています。実際に腰をあげる動作を含めた骨盤底筋訓練は産後2〜3週間経ってからでも良いとされています。
逆に言えば、そのくらいの期間をかけてしっかり呼吸の練習を行う価値があるということです。


じょさんしnavi柏村
山村さんは、具体的に産後の育児の合間、どの時間を使って骨盤底筋訓練を行っていましたか?

山村
私はよく寝る前の時間を使っていました。少しやるだけで自分の回復度が上がりますし、結果的に自分の体力が回復することにつながります。尿漏れなど不快な症状が出ないような身体を作るために、時間をかける価値はあると思います。

じょさんしnavi柏村
産後2〜5日目などの胸が張ってくるような時期には、うつ伏せ以外でどのようなポーズでの呼吸練習が有効でしょうか。

山村
チャイルドポーズがおすすめです。動ける方であれば「キャット&カウ」という四つん這いで背骨を反らしたり丸めたりする動きもおすすめしています。
産後のお母さんは育児で精一杯になるので、自分の身体のケアが後回しになりやすいですよね。助産師から、産後の身体をねぎらうことや簡単にできる方法を説明できることで、お母さん方も気づきやすく自分の身体に目を向けるきっかけになると思います。お母さんが自分の身体を大事にすることで、産後のトラブルを減らすことができますし、結果的にストレスの少ない育児へとつながります。助産師として、退院後も母児が笑顔で過ごせるようにサポートしていきたいですね。

.png)