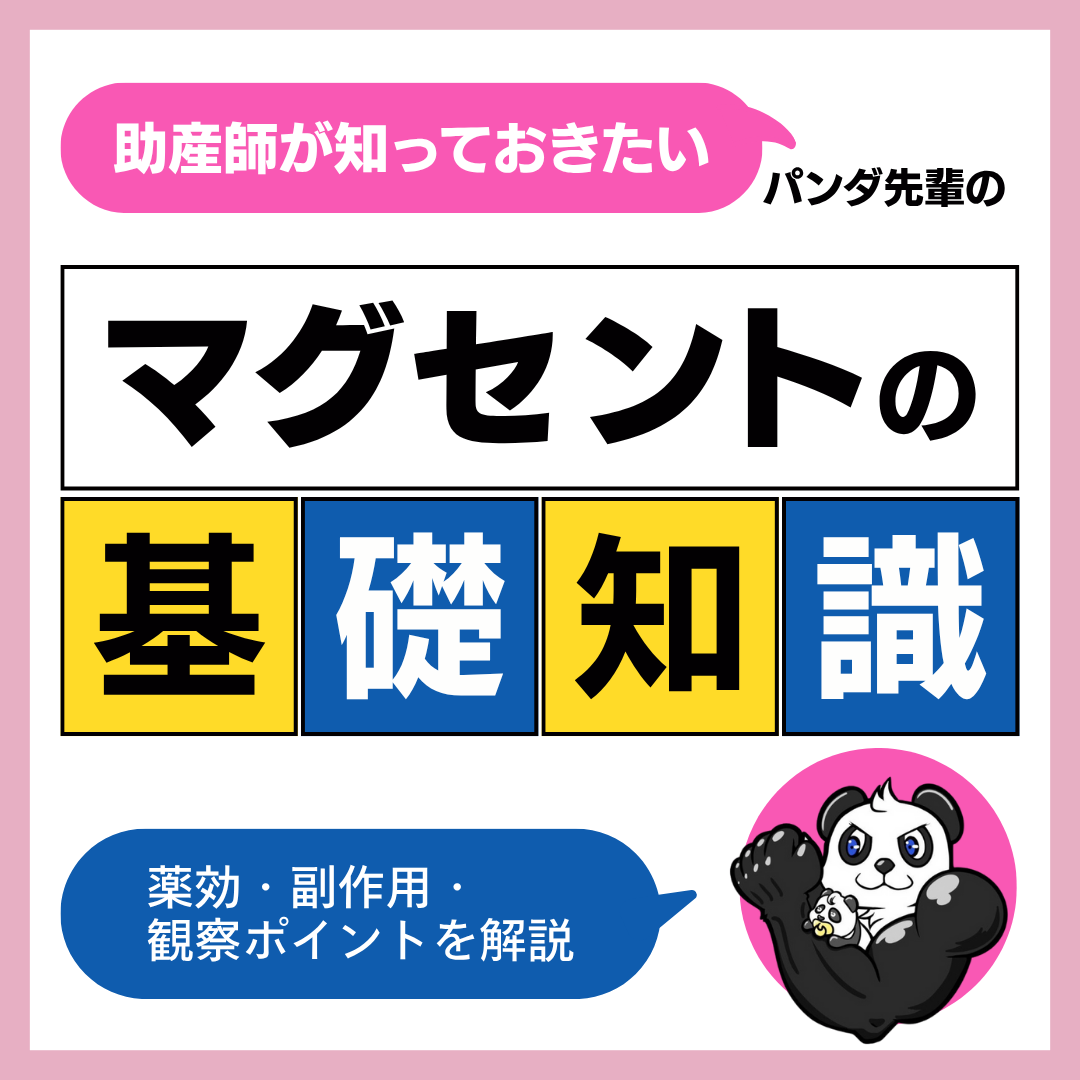
助産師が知っておきたいマグセントの基礎知識|薬効・副作用・観察ポイントを解説
- 切迫早産
- 妊娠高血圧症候群
- マグセント
1. マグセントとは
マグセント(商品名)は、成分名を「硫酸マグネシウム」といい、体内のマグネシウム濃度を高めることで中枢神経や筋肉の興奮を抑える薬です。産科領域では、主に以下のような場面で使われます。
- 妊娠高血圧症候群(とくに子癇発作の予防と治療)
- 切迫早産(子宮収縮の抑制)
- その他、マグネシウム不足の補正など
静脈から点滴で投与されることが多く、全身にゆっくりと作用します。
2. マグセントの薬効と作用のしくみ
マグセントが体にどのように作用するのかを理解するためには、マグネシウムという電解質の働きを知っておく必要があります。
①中枢神経を抑制する
マグネシウムは、神経細胞の興奮を抑える作用を持っています。カルシウムが神経の興奮伝達に関与しており、マグネシウムはカルシウムの流入をブロックすることで神経の過剰な興奮を抑制します。
この作用により、妊娠高血圧症候群でリスクとなる「子癇(けいれん発作)」を予防することができます。けいれんは神経が過剰に興奮し筋肉が一斉に収縮する現象です。マグネシウムを投与することで神経の過活動を抑え、子癇を防ぐことにつながります。
②子宮収縮を抑制する
マグネシウムは子宮の平滑筋にも作用します。カルシウムが筋収縮を促すのに対し、マグネシウムは筋細胞内へのカルシウムの流入を抑えることで、子宮の緊張を和らげます。
つまり、マグセントを使うと子宮がリラックスした状態になり、切迫早産などでの過剰な収縮を抑えることができます。ただし原則として、妊娠35週以前で推定胎児体重 2500g未満の切迫早産に使用することが望ましいとされています。また 妊娠22週未満の切迫流産における有効性及び安全性は確立していません。
③血管を拡張し血圧を安定させる
マグネシウムには血管を拡張する働きもあり、全身の血流を良くして血圧を安定させます。これは、マグネシウムが血管の平滑筋にも作用して、筋肉の緊張を緩めることによるものです。妊娠高血圧症候群では、血管の収縮によって高血圧が起こっていますが、マグセントを使用することで血圧を緩やかにコントロールする効果が期待できます。

3. 投与方法
マグセントは通常、静脈から点滴で投与されます。最初に「負荷投与」として短時間にある程度の量を入れ、その後は「維持投与」として一定の速度で持続的に点滴を続けることが多いです。投与方法を分けるには理由があります。まず負荷投与を行うことによって急速に血中マグネシウム濃度が上昇し、体内でカルシウムとのバランスが崩れます。その結果、中枢神経系の抑制と筋弛緩が起こります。この効果を目的として切迫早産における子宮収縮抑制や子癇の抑制、治療として使用されるのです。また維持投与は一定の血中濃度を保つためにを行います。マグセントの静脈内投与には必ず輸液ポンプやシリンジポンプを使用します。

パンダ先輩
負荷投与のことを「ローディング」というよ!
①妊娠高血圧症候群における子癇予防や治療で使用する場合
初回量として、40mLを20分以上かけて静脈内投与(負荷投与)した後、10mL/Hで持続静脈内投与(維持投与)を行います。症状に応じて5mL/Hずつ増量し、最大投与量は毎時20mL/Hまでと定められています。
②切迫早産で使用する場合
初回量として、40mLを20分以上かけて静脈内投与(負荷投与)した後、10mL/Hで持続静脈内投与(維持投与)を行います。それでも子宮収縮が抑制されない場合は5mL/Hずつ増量し、最大投与量は20mL/Hまでと定められています。子宮収縮抑制後は症状を観察しながら徐々に減量し、子宮収縮の増強がないと確認された場合には投与を中止します。
※基本的に投与は連続48時間までが原則とされています。その後も継続して投与する場合は、治療上のメリットが副作用などのリスクを上回ると判断される場合に限って投与が継続されます。上記は一般的な使用方法の例です。施設の方針や医師の判断により異なります。

パンダ先輩
副作用として血管痛がでることがあるよ!そのときは側管から補液を投与し濃度を薄くすることで改善することも
4. マグセントの副作用と使用上の注意点
マグセントは効果的な薬ですが、過剰に作用するといくつかの副作用が起こることがあります。これらの副作用の多くは、マグネシウムの濃度が高くなりすぎること(高マグネシウム血症)によって生じます。
①主な副作用と起こるしくみ
副作用 | 血中マグネシウム濃度 | 作用機序 |
呼吸停止・心停止 意識混濁・昏睡状態 | 10 mEq/L以上 | 心筋の刺激伝導が抑制される 横隔膜や呼吸筋が弛緩し呼吸が浅くなる |
呼吸抑制・筋力低下 心電図異常 | 7~10 mEq/L | 心筋の刺激伝導が抑制される 横隔膜や呼吸筋が弛緩し呼吸が浅くなる |
血圧低下・倦怠感 深部腱反射の低下 | 5~7 mEq/L | 神経筋接合部が抑制される 血管拡張作用 |
顔面紅潮・発汗・口渇 | 4~5 mEq/L | 血管拡張作用による体温調整の変化 |
②高マグネシウム血症のサイン
- 深部腱反射の減弱や消失
- 呼吸数の低下(12回/分以下)
- 尿量の減少(30mL/時以下)
- 意識のぼんやり感や反応の鈍さ
これらの症状が現れたら、すぐに医師へ報告しましょう。医師の判断で必要に応じてマグセントの中止や拮抗薬(カルシウム製剤)の投与が検討されます。

5. 助産師が行う観察とケア
マグセント投与中の妊婦さんは、副作用や合併症のリスクを抱えているため、助産師による継続的な観察が不可欠です。
- 呼吸状態:努力呼吸や浅い呼吸がないか
- 意識レベル:会話が成立するか、傾眠傾向がないか
- 深部腱反射(DTR):膝蓋腱反射を定期的に確認
- 尿量:30mL/時を下回っていないか
- バイタルサイン:血圧・脈拍の変動、徐脈に注意
- 血中マグネシウム濃度:4mEq/L以上になっていないか
- 筋力低下・倦怠感:転倒リスクが高くなるため歩行状態やADLを確認
- 子宮収縮:切迫早産の治療中は収縮の頻度を確認し効果判定を行う
- 胎児心拍:母体のバイタルサインの変動に伴い胎児の徐脈や変動の減少がないかも確認
6. 胎児や出生後の赤ちゃんへの影響
マグセントは胎盤を通過するため、胎児にも影響を及ぼすことがあります。分娩直前まで投与した場合、出生した新生児に高マグネシウム血症を起こすことがあるため、分娩前2時間は使用しないことが推奨されています。短期間の使用であれば基本的に大きな問題は起こらないとされていますが、出生後に新生児へのモニタリングや蘇生対応が必要となる場合もあります。リトドリンと併用している場合には特に注意が必要です。
胎児や児への影響
- 妊娠中に胎動減少となることがある
- 胎児の筋緊張が一時的に低下することがある
- 呼吸中枢が抑制され、新生児仮死(アプガースコア低下)になる
- 長期間の使用(数日以上)では、胎児の骨形成や電解質バランスに影響する可能性が報告されている
マグセントは妊婦さんの命を守る大切な薬ですが、効果が強い分副作用のリスクも高い薬剤です。そのため、正しい理解と根拠のある観察やケアが求められる薬でもあります。慣れないうちは使用することに不安も多いかと思いますが、仕組みを知ることで、観察の意味がぐっとわかりやすくなります。マグセントを使用する場面に立ち会うときは、ぜひこの記事を思い出して妊婦さんや家族だけでなく、自分自身を守る意味でも安全で安心なケアにつなげてください。
【参考文献】

【新人助産師と学生が押さえておきたい】CTG(NST)モニターの基礎知識|基線・基線細変動・一過性頻脈の見方をわかりやすく解説
- CTGモニター
- モニター判読
.png)
【助産師必見】超音波検査での胎児計測|基本項目と正しい計測方法を徹底解説
- 超音波検査
- 助産師によるエコー検査

“なんとなく”の指導はもう終わり。エビデデンスに基づく乳頭ケアの指導方法|妊婦さんの「やってみよう」を引き出す助産師の言葉は?
- 乳頭マッサージ
- 妊娠中

明日から使える!妊婦さんの不安を解消する「会陰マッサージ」指導のポイント|最新のエビデンスも解説
- 会陰部マッサージ
- 会陰部切開
- 経腟分娩
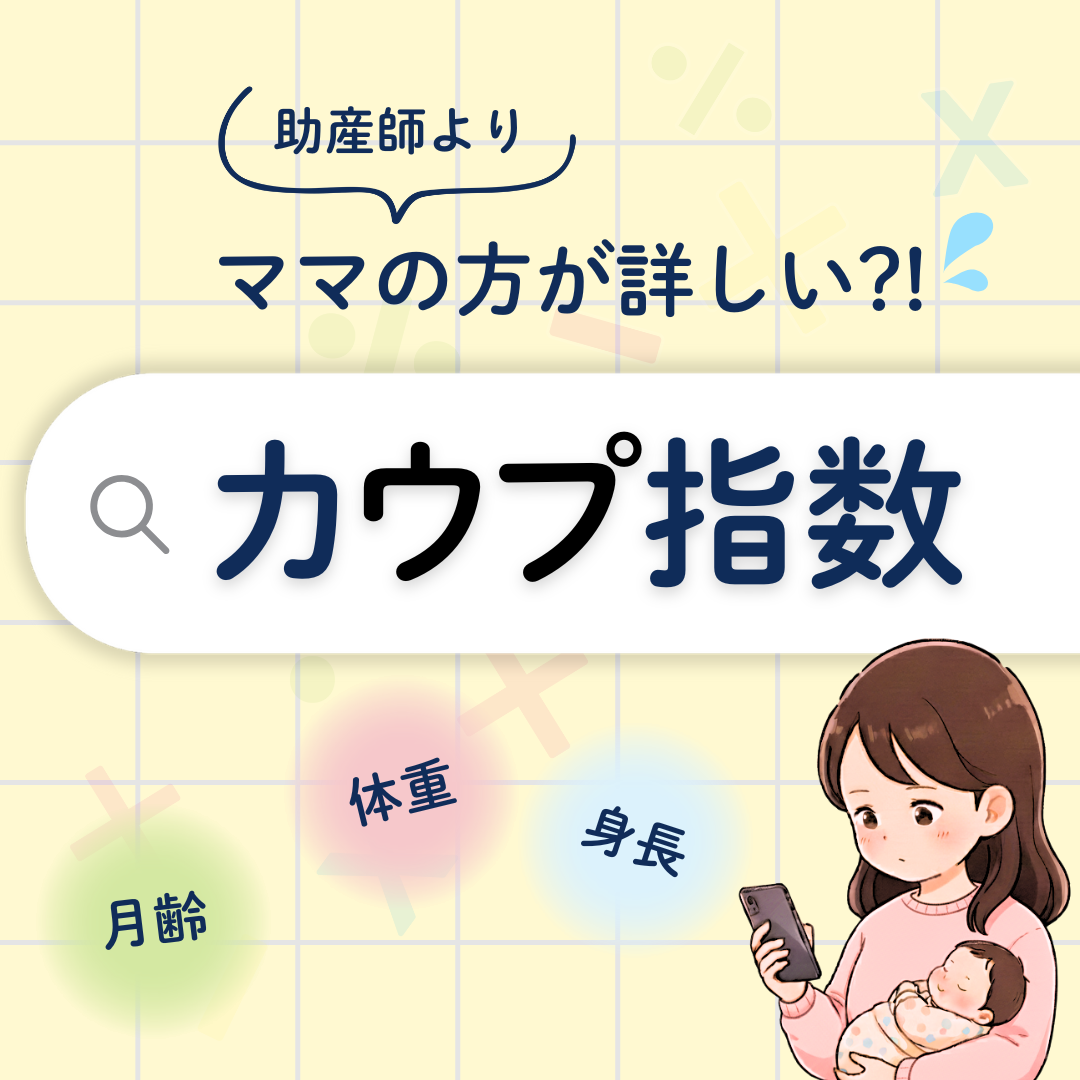
【月間3.8万検索の衝撃】ママの方が詳しいかも?助産師が知っておくべき“カウプ指数”の常識
- カウプ指数
- 月齢
- 乳幼児

Late Preterm児(後期早産児)とは?特徴・リスク・看護のポイントを徹底解説
- 早産
- Late Preterm児
- 後期早産児