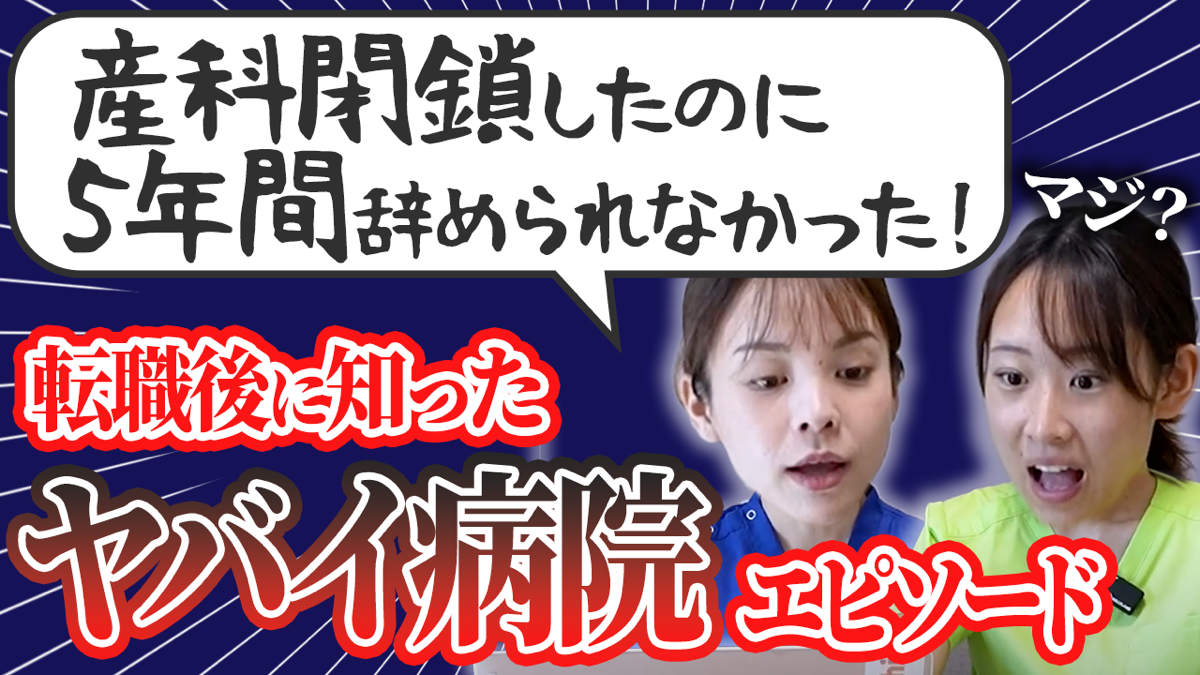.webp)
【例文あり】助産師の職務経歴書の書き方|スキル・経験を伝えるコツ
- 助産師の転職
- じょさんしcareer
- 転職準備
1. 職務経歴書と履歴書との違い
職務経歴書とは、これまでどのような業務に携わってきたかを詳しく伝える書類です。履歴書が経歴の「概要」を示すものだとすれば、職務経歴書は「中身」を具体的に伝える資料といえます。助産師としての職務経歴書では、以下のような情報を盛り込むことで、自分の経験やスキルを採用担当者に効果的に伝えることができます。
・担当してきた分娩件数や年間の分娩数
・経験してきた分娩方法(自然・無痛・帝王切開など)
・外来、母親学級、母乳指導などの関わり
・夜勤体制やオンコール対応の有無
・チーム内での役割(リーダー、プリセプター、教育担当など)
2. 職務経歴書の基本構成とフォーマット
職務経歴書は以下のような構成でまとめると、採用担当者に伝わりやすくなります。
職務経歴書の基本構成:
職務要約:3〜5行程度で経歴を簡潔にまとめます
職務経歴(勤務先ごとに記載):勤務期間・業務内容・分娩件数などを具体的に記載します
活かせるスキル・資格:業務に活かせる資格や経験(NCPR、IBCLCなど)を記載します。
自己PR(任意):応募先に合わせた強みや志向をアピールします。
フォーマットはWord形式(A4サイズ、1〜2枚)で作成し、箇条書きを用いて読みやすく仕上げましょう。

3. 助産師の職務経歴書でアピールすべきポイント
・経験年数と役割の変化
「何年働いたか」だけでなく、「どんな役割を担ってきたか」を書くことが大切です。たとえば、後輩や学生指導、リーダー業務、院内委員会への参加など、経験の深まりを具体的に記載しましょう。
・勤務先の特徴を伝える
「年間分娩件数800件の総合病院」「自然分娩中心の助産院」など、勤務施設の特徴を書くことで、あなたの経験の幅がより明確に伝わります。
・数字を使って実績を見せる
「母乳育児に力を入れていた」だけでなく、「母乳外来で1日平均6名を対応」「混合栄養から母乳育児へ移行した事例多数」など、数字を使って説得力を持たせるようにしましょう。
職務経歴書と一緒に整えておきたいのが「志望動機」
履歴書では志望動機が求められますが、職務経歴書と一貫性を持たせることで、より深い自己PRが可能になります。
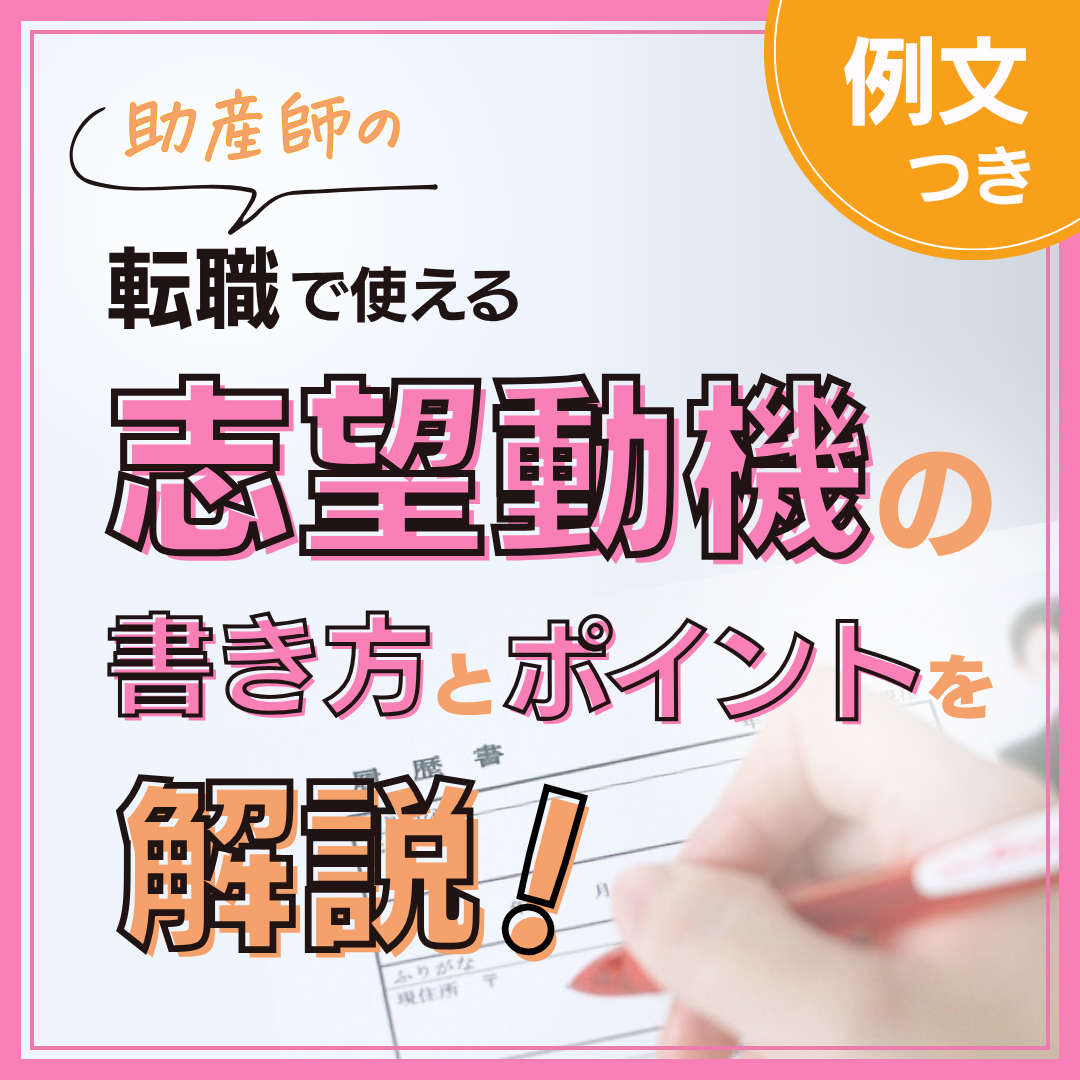
4. 書き方のコツと注意点
時系列を整理する:古い順または新しい順で統一しましょう
専門用語の多用を避ける:採用担当者が医療従事者とは限らないため、分かりやすい表現を意識します
誇張はNG:スキルや実績を正しく伝えることが信頼につながります
転職理由は前向きに:「成長したい」「学びを深めたい」など、前向きな意図を中心に記載しましょう
面接では、職務経歴書の内容に基づいた質問がされることが多いです。
職務経歴書に書いた内容を深掘りされても答えられるように、面接対策も並行して進めましょう。
➡ 助産師の面接でよく聞かれる質問と答え方のリンクを貼りたい場所

5. 職務経歴書の例文5選(シーン別)
【例文①】病院勤務の経験を活かしたい場合
職務要約:総合病院で助産師として6年間勤務し、分娩介助、母乳育児支援、母親学級の運営など幅広く担当してきました。
職務経歴:
勤務先:〇〇市民病院(2018年4月〜2024年3月)
年間分娩件数:850件
業務内容:LDRでの分娩介助、初期母乳指導、褥婦ケア、学生指導など
【例文②】助産院での自然分娩をアピールしたい場合
職務要約:助産院にて自然分娩や水中出産の介助を経験し、妊娠期から産後までの継続的なケアに携わってきました。
職務経歴:
勤務先:〇〇助産院(2021年4月〜2024年3月)
年間分娩件数:250件(自然分娩率100%)
業務内容:妊婦健診、分娩介助、産後ケア訪問、母乳相談
【例文③】復職・ブランク明けを目指す場合
職務要約:第一子出産後5年のブランクがありますが、復職に向けてNCPRの更新や各種研修に積極的に参加してきました。
職務経歴:
勤務先:〇〇大学病院(2015年4月〜2018年3月)
業務内容:ハイリスク妊産婦対応、帝王切開術前後のケア、NICUとの連携など
【例文④】夜勤専従や非常勤で働いていた場合
職務要約:家庭と両立しながら夜勤専従で勤務し、夜間の分娩対応や急変時の判断力を磨いてきました。
職務経歴:
勤務先:〇〇レディースクリニック(2020年4月〜現在)
業務内容:夜間分娩、褥婦観察、翌朝の申し送りなど
【例文⑤】教育・指導に関心がある場合
職務要約:10年間の助産師経験を通じて、学生指導やプリセプターとしての経験も多く、チームケアの向上にも努めてきました。
職務経歴:
勤務先:〇〇医療センター(2013年4月〜2023年3月)
業務内容:分娩・褥婦管理、実習生の指導、院内研修の運営など

職務経歴書は、助産師としての経験やスキルを言葉で丁寧に伝えるための大切なツールです。特別な資格やポジションがなくても、日々の業務の中で積み重ねてきたことを具体的に書くことで、あなたらしい魅力がきっと伝わります。志望動機や面接対策も併せて準備することで、転職活動をより自信を持って進めることができます。書類で伝える力を磨き、次の一歩へとつなげていきましょう。
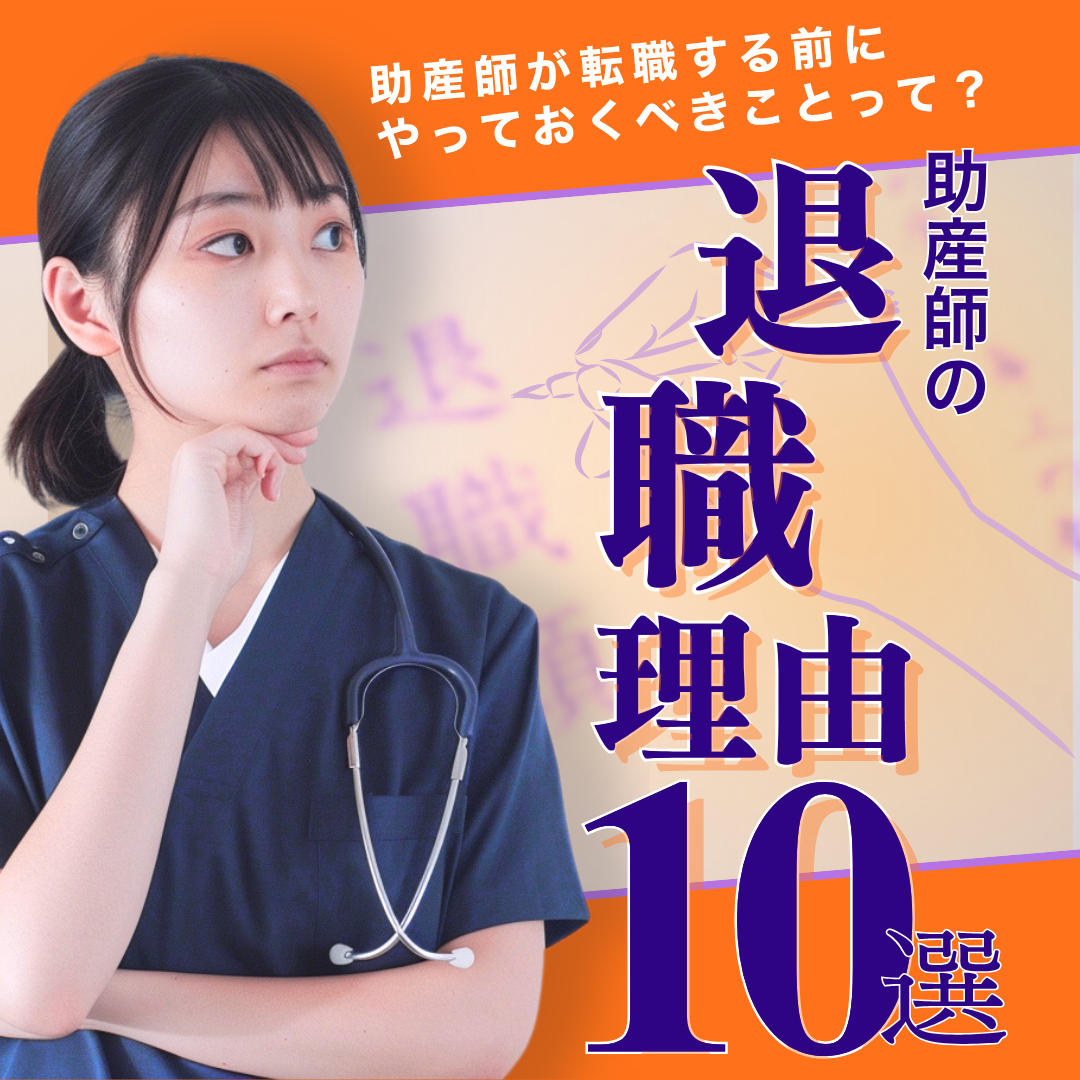
助産師の退職理由で多いこと10選|助産師が転職する前にやっておくべきことって?
- 助産師の転職
- 退職理由
- ワークライフバランス
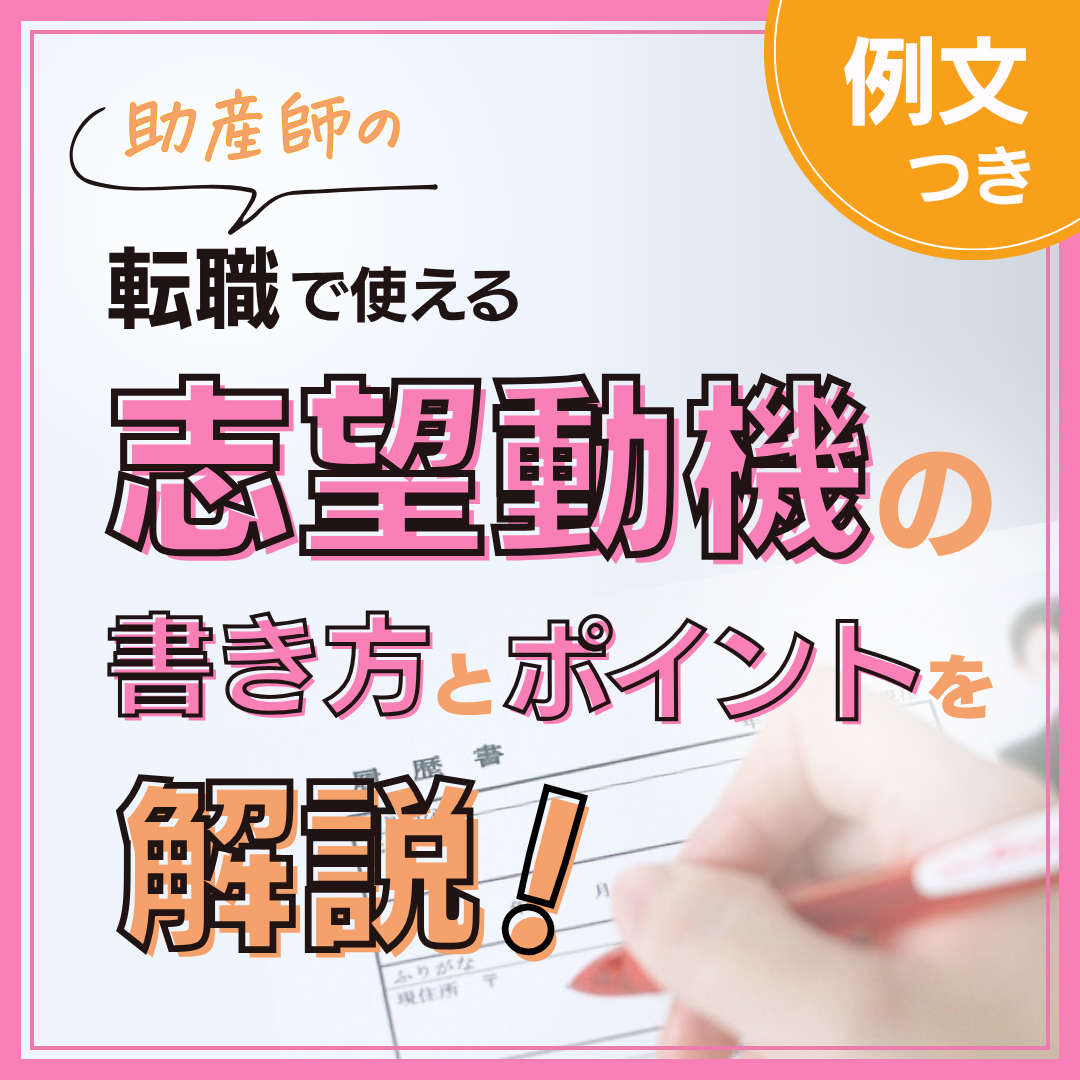
【例文つき】助産師の転職で使える志望動機の書き方とポイント解説!
- 助産師転職
- 志望動機
- 履歴書

助産師の転職面接を成功させるには? よくある質問&回答例も紹介
- じょさんしcareer
- 助産師の転職
- 中途採用
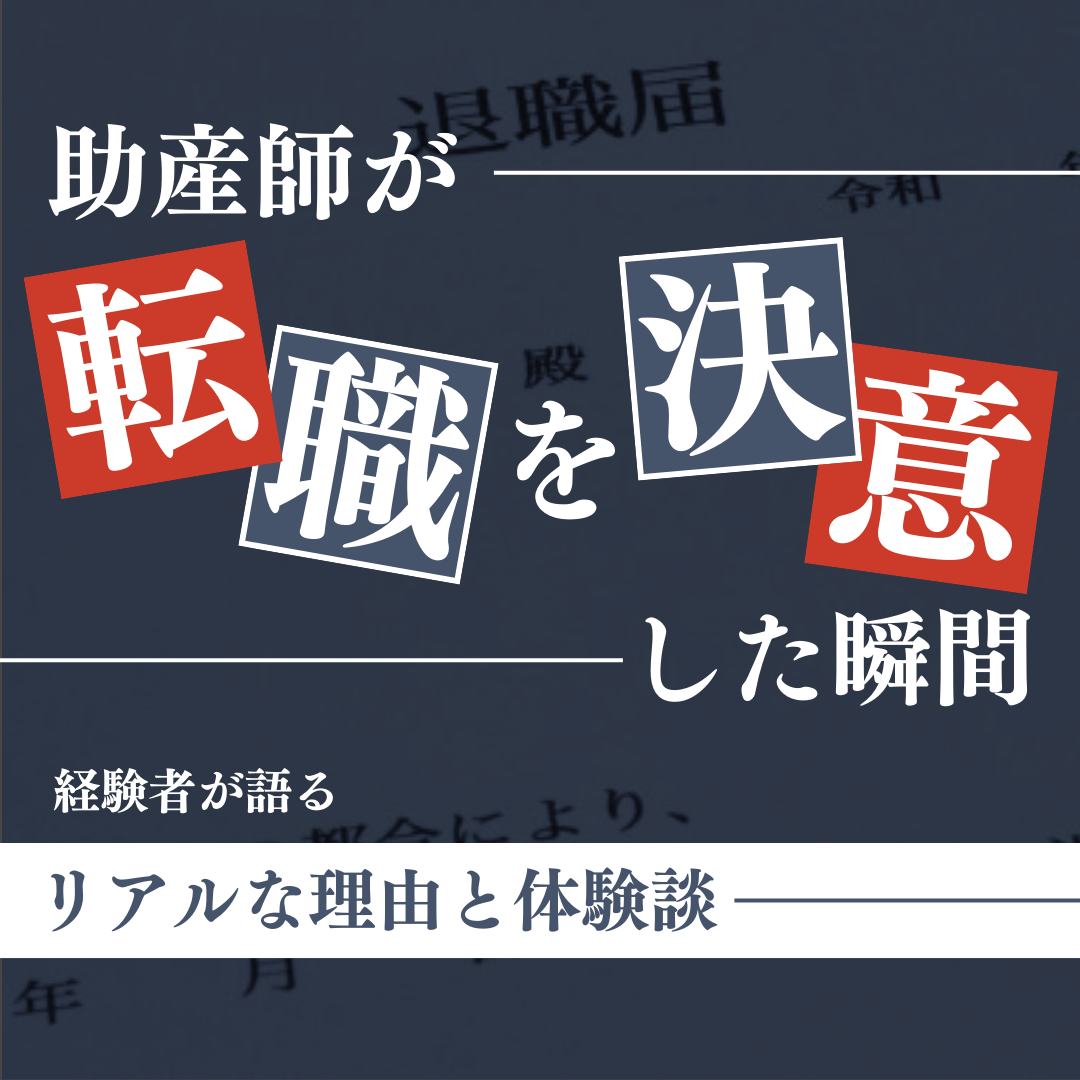
助産師が転職を決意した瞬間|現役助産師が語るリアルな理由と体験談
- じょさんしcareer
- 助産師の転職
- 経験談
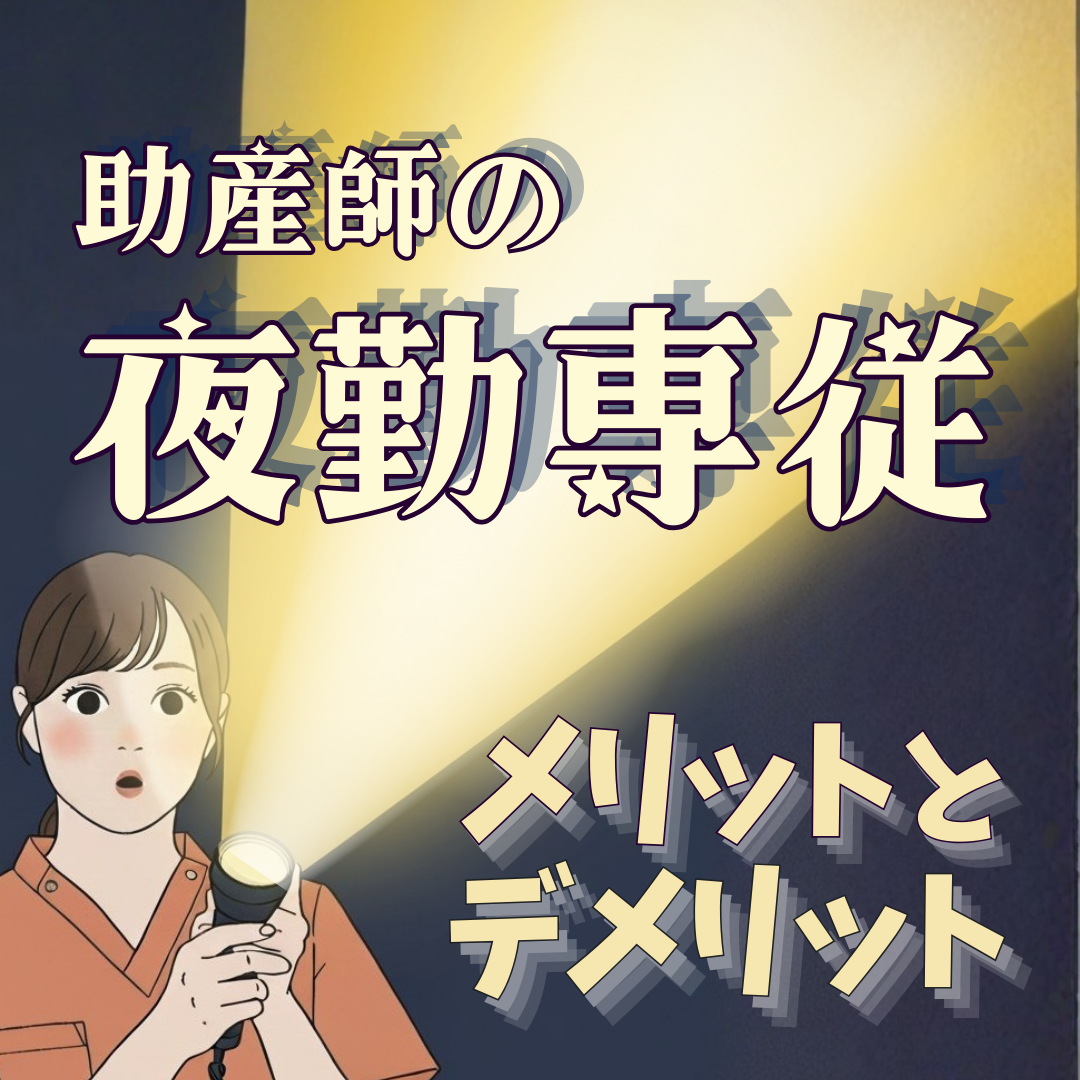
助産師の夜勤専従という働き方|メリット・デメリットと向いている人
- 夜勤
- 夜勤専従

助産師の給料事情|病院・クリニック・助産院での年収の違いとは?
- 助産師の給料
- 助産師の年収