.webp)
【出産のプロ】助産師自身が産むなら?分娩施設を選ぶ時の譲れないポイント
- 分娩施設
- 職場選び
- 助産師の出産
1. 知っている人に任せたい? 知られずに産みたい?
分娩施設を選ぶうえで、「誰にお産を任せたいか」ということはとても重要なポイントです。長年一緒に働いてきた同期や同僚助産師は、心から信頼できる存在になりますよね。価値観も、お産への思いも理解してくれているからこそ、「もし可能なら、同期にお産を取り上げてもらいたい」と感じている方が一定数いました。しかし反対に「誰も私が助産師だと知らない場所で、妊婦としてフラットに扱ってほしい」と感じている方もたくさんいました。自分の勤務先では産みたくないと考えている助産師はなんと7割もいます。勤務先や知人の多い施設では、どうしても「助産師さんだからわかりますよね?」という雰囲気や、気を遣われすぎる対応に直面することもあります。でも出産は、知識があっても不安になりますし、痛みや感情のゆれは誰にでもあるものです。だからこそ、あえて自分のことを何も知らない場所で、「一人の妊婦」として関わってもらいたいと考える助産師も少なくありません。信頼できる顔なじみに任せたいか、それとも完全にプライベートな環境で出産したいか…悩ましいポイントです。

執筆した助産師
私自身は1人目は自分の職場とは別のクリニック、2人目は自分の勤務先であるクリニックで出産しましたが、どちらが正解ということではなく、自分にとって心が落ち着く選択肢はどちらかを考えることが大切だと感じました。助産師と言えど初産婦です。沐浴や抱っこには慣れていても初めての授乳には苦戦しましたし、丁寧に指導をしてもらったり、「上手に出来ていますね」と褒めてもらうことで初めての育児の自信に繋がりました。2人目のお産はコロナ禍で夫や家族の面会も制限されていたため産後の入院中にスタッフさんとしか会えない可能性があったため勤務先で産むことを決めました。普段一緒に働いている同僚に陣痛中に迷惑をかけてしまわないか、お産とは言えプライベートゾーンを近しい人に見られる恥ずかしさなどはありましたが、それを除けば入院中のスケジュールや施設やサービスなど勝手が分かっている勤務先での入院生活はとても快適でした。
2. 小児科医が常駐している病院
出産における「安心」とは、何もトラブルが起こらないことではなく、「もし何かあってもすぐに対応できる体制があること」だと思っています。アンケートによると多くの助産師は出産する施設を選ぶ上で、小児科医が常駐またはオンコール体制にあることは重要なポイントでした。出生直後の赤ちゃんに何か問題があった場合、すぐに診てもらえる小児科医の存在は大きな安心になります。特に低出生体重児や仮死など、早期対応が命を左右するケースを、これまで何度も見てきました。助産師として、これまでいろいろなケースを目撃してきた経験から「医師がすぐに来られなかったらどうなるか」を知っているからこそ、自分の出産ではそうした不安要素が少ない施設を選びたいと感じました。

3. 緊急対応がスムーズな体制があること
出産がスムーズに進むことを願っていても、予期しない事態は起こり得ます。赤ちゃんの心拍が急に低下したり、大量出血が起きたり、妊婦本人が意識を失うようなケースにも、これまで実際に立ち会ってきました。そのたびに感じたのは、「緊急対応は1分1秒を争う」という現実です。だからこそ、自分の出産では緊急帝王切開や大量出血への対応が迅速に行える体制があるかどうかをしっかり確認したいと思いました。オペ室のすぐ近くに分娩室があるか、麻酔・外科・内科との連携が取れているか、スタッフ間の動きが訓練されているか、輸血ができるかなど、「何かあったら搬送します」ではなく、「ここで対応できます」という安心感が、私にとっては重要でした。私は普段、クリニックに勤務していて「緊急搬送をする側」として働いていますが、受け入れて下さる高次施設の医師、助産師、看護師のみなさんには感謝しかありません。1秒でも早く到着して欲しいと願いながら過ごす救急車内の緊迫した空気感は何度経験しても慣れません。
4. NICU(新生児集中治療室)があること
新生児にとって、出生直後の数時間~数日はとても大切な時間です。たとえば呼吸が不安定、体温調節ができない、血糖値が安定しないなど、ちょっとしたことが大きなトラブルにつながることもあります。そうしたときに、NICU(新生児集中治療室)が併設されている施設なら、すぐに適切なケアが受けられます。NICUに搬送するには時間がかかりますし、その間に赤ちゃんの状態が悪化するリスクもあります。だからこそ、「何かあったら対応できる場所で産む」という安心感は、母としても助産師としても非常に大きいと感じました。元気に産まれてくれるのが一番。でも、もしもの時に備えて選択肢を用意しておくことが、赤ちゃんを守るための大切な準備になると思います。赤ちゃんが搬送された後に母子分離で過ごすママの寂しさや不安、罪悪感でいっぱいになって涙する姿も目にして来ているからこそNICUがあることは優先度の高いポイントであると感じます。
5. ごはんが美味しいこと
「ごはんが美味しいこと」も私にとっては立派な譲れないポイントです。出産直後は体力も気力も使い果たしている状態。その中で、温かくて美味しいごはんが出てくることは、まさに「心と体を回復させる栄養」だと感じています。施設によっては、お祝い膳や産後のおやつ、個別対応のメニューなど、産後のママをねぎらう工夫がされているところもあります。私が働いてきた中でも、ごはんが美味しいと評判の施設では、お母さんたちの表情もどこか柔らかく、入院中の満足度も高い傾向にありました。お産は心も体もフル稼働する一大イベント。そのあとの入院生活で、「おいしい」と感じる時間があることは、それだけで癒しになると思います。

【番外編】「助産師だからこそ」感じる、こだわりたいポイント
「助産師だからこそ」こだわりたいポイントは他にもあります。1つは自分のバースプランを尊重してもらえるかどうかということです。たとえば「音楽を流したい」「アロマを使いたい」「産後は赤ちゃんとゆっくり過ごしたい」など、小さな希望も、妊婦にとっては大きな意味があります。ところが、病院によっては謎の“ローカルルール”が存在し、希望が通らなかったり、施設の方針を一方的に押しつけられてしまうこともあります。「うちではこうなってるので」の一言で、せっかく考えたプランが叶わないのは、悲しいことです。そしてもう1つ。私は助産師として、「助産師だから」という理由で、必要以上に管理されたくないという思いもありました。たとえば「起き上がってもいいですか?」「母乳のことは自分で調整したいです」など、多少自由に入院生活を送りたいという気持ちがあるのです。だからこそ、「バースプランを一緒に考えてくれる」「方針を押しつけない」「柔軟に対応してくれる」そんな施設が理想の場所だなと思いました。
助産師として働いてきた私は、お産に関するリスクや現場のリアルをよく知っています。だからこそ、自分が出産するとなったとき、何よりもまず「安全性」を重視したいと強く思いました。信頼できる人にお産を任せたい気持ちと、あえて知らない環境で妊婦として向き合いたい気持ち。小児科医や麻酔科医、NICUの有無、緊急時の体制。そして、体と心をいたわる入院中の食事まで、どれも私にとっては大切な視点でした。また、妊婦さんが施設を選ぶ理由は人それぞれで、「食事がおいしい」「快適な個室がある」などを重視するのも、もちろん大切な価値観だと思います。ただ、私の場合は助産師としてお産のリスクや緊急時の現実を日々見ているからこそ、より医療体制や対応力といった部分に目が向きやすくなっていると感じました。そうした違いも含めて、「自分は何を優先したいのか」を明確にしておくことが、後悔しない出産につながると思います。出産に「正解」はありません。でも、自分自身の気持ちや価値観に丁寧に向き合って選ぶことが、納得のいく出産への第一歩です。これから出産を迎えるすべての方が、自分らしく、安心して新しい命と出会える場所に出会えますように。心から願っています。
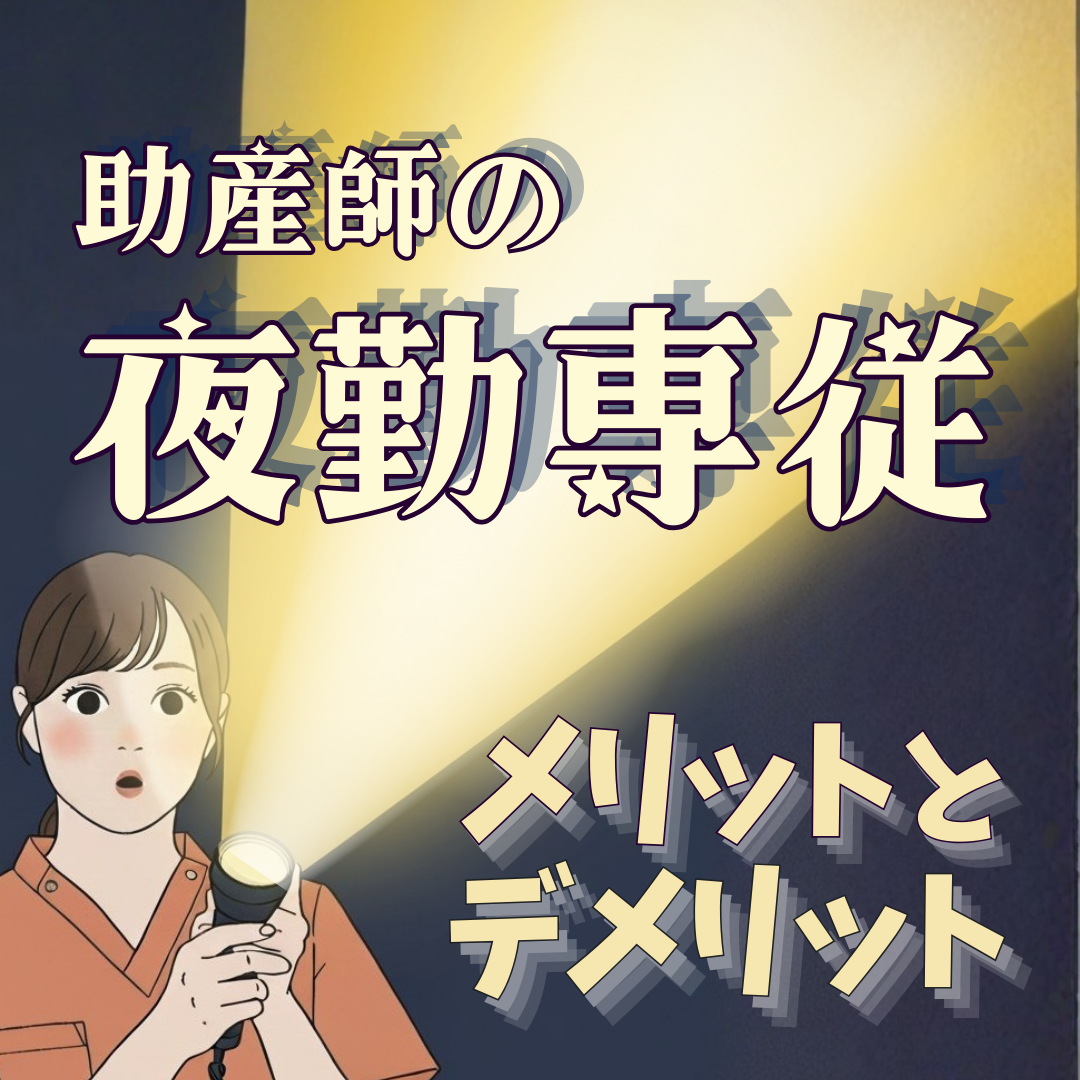



.png)
