
産後ケア事業とは?助産師が知っておきたい制度・対象者・事業内容をわかりやすく解説
- 産後ケア
- 産後ケア事業
1.産後ケア事業の概要
産後ケア事業は、母子保健法に基づいて産後ケア事業のガイドラインが制定されており、法整備されてまだ新しい事業です。自治体が実施主体となり、妊娠から出産後まで安心して子育てができる切れ目のない支援体制の確保を行うことを目的としています。産後ケア事業の実施は市町村の努力義務となっているため、地域社会全体で母子をサポートすることができます。
1)対象者
対象者は
①出産後1年以内の女性であって産後ケアを必要とする者
②自宅において養育が可能である乳児
とされており、以下のような理由で産後ケア事業を利用することができます。
<身体的側面>
授乳が困難。出産後の身体的な不調(眠れない、寝不足)や回復の遅れがあり、休養が必要。
<心理的側面>
産婦健康診査で実施したエジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)の結果等により心理的ケアが必要。
<社会的側面>
同居していても仕事などで家族等からの十分な育児、家事等の支援が受けられない。
産後ケア事業は、出産後の母子を幅広くサポートする制度です。感染症が疑われたり医療介入が必要な場合を除いて、全国どこにいても退院して自宅で生活している大抵のママと赤ちゃんが産後ケアを受けられるようになりました。令和6年度のガイドラインの改訂では、「里帰り出産をしている母親」や「流産や死産等を経験された方」も産後ケア事業の対象者として対応できるようになりました。

2)対象時期
産後ケア事業の対象時期は出産後1年以内です。改訂前の予算事業においては、出産直後から4か月頃までの時期が対象となっていました。「出産後1年以内」と改訂されたのは、低出生体重児等の場合に、入院期間の長期化で退院時期が出産後4か月を超える場合もあることや、産婦の自殺は出産後5か月以降にも認められるなど、出産後1年を通じてメンタルヘルスケアの重要性が高いことなどを踏まえて、「出産後1年以内」とされた背景があります。
3)実施担当者
産後ケア事業を実際に担当するスタッフについても、基準が定められています。安全で質の高いケアを提供するため、専門的な知識と技術を持った助産師、保健師、看護師のうち1名以上を配置するよう定められています。特に出産後4か月頃までの時期は、褥婦や新生児に対する専門的ケア(乳房ケアなど)を行うため、原則として助産師を中心とした実施体制が求められています。
4)産後ケア事業の形態
産後ケア事業には、利用者のニーズに応じて選択できる3つの実施形態があります。それぞれに特徴があり、ママの状況や希望に合わせて最適な形態を選ぶことができます。
① 宿泊型(ショートステイ)
病院、クリニック、助産院等の空きベッドを活用し、ママと赤ちゃんが施設に泊まってケアを受ける形態です。ゆっくりとケアを受けることができるのが最大の特徴です。
<特徴>
・24時間体制で1名以上の助産師、保健師又は看護師配置が必要
・時間が長く取れるため複数回の授乳育児指導が可能
・他の形態と比較して利用料が高い
・利用期間は原則7日以内(分割利用可能)
・兄弟姉妹も一緒に宿泊できる施設もある
経産婦の方にとって、上の子も一緒に宿泊できるのはとてもありがたいサービスです。2泊程度利用して、また間をおいて2泊といった分割利用により、目標を持ってしばらく育児を頑張れるという声も聞かれます。
②日帰り型(デイサービス)
個別・集団で支援を行える施設において、日中のみ施設でケアを提供する形態です。宿泊の必要がないため、気軽に利用できるのが特徴です。
<特徴>
・宿泊型と比較して利用料が安い
・グループワークなど集団活動による仲間づくりも可能
・利用時間に制限があり一度で十分なケアを提供することが困難な場合がある
グループでの活動がある場合、同じような状況のママたちとの出会いや情報交換ができ、仲間づくりの場としても機能します。
③訪問型(アウトリーチ)
実施担当者が利用者の自宅に赴いてケアを提供する形態です。ママの移動負担がなく、生活の場で指導を受けられるため、その後の生活に活かしやすいという利点があります。
<特徴>
・利用者の移動負担がない
・家族関係や住環境を直接確認でき生活全般の助言がしやすい
・生活の場での指導のため、家庭にあるもので実践でき、その後の生活に活かしやすい
「家を片付けないといけない」と自宅に来てもらうことに抵抗や負担を感じる方もいれば、「家事ができないから来てほしい」という方もおり、ニーズは様々です。

5)利用料金
まだモデル段階での平成29年のガイドラインにおける概況調査での利用料は、宿泊型は4,000円〜10,000円、日帰り型では1,000円~4,000円、訪問型では500円〜2,000円が多かったと報告されています。産後ケア事業の利用料金は自治体によって異なりますが、国からの補助と県・自治体の予算、出生数などのバランスから算出されるため、地域差があります。
生活保護世帯や低所得者世帯は、周囲から支援がもともと得られない等の社会的リスクが高いと考えられるため、利用料の減免措置が考慮されています。さらに、令和5年より全ての産婦に減免支援が導入されました。鳥取県や栃木市では無料化を実施していますが、その分利用許可の審査が厳しくなっているとの意見もあります。
6)利用回数
利用回数は原則として7回となっていますが、この制度も自治体によって大きく異なります。3つの事業形態(宿泊型・日帰り型・訪問型)を合わせて計7回まで利用できる自治体がある一方で、それぞれの形態ごとに7回ずつ、つまり合計21回まで利用可能な自治体もあります。近年では、産後ケア事業の推進を目的に、都道府県が主体となり複数の自治体と施設が連携する「集合契約」も導入されています。この制度では、県内であればどの地域の産後ケア施設も利用できるようになり、利用者の選択肢が大きく広がります。
2.産後ケアで助産師が行う具体的なケア
産後ケア事業で提供するケア内容は、事業形態にかかわらず基本は同じです。
①母親の身体的ケア及び保健指導、栄養指導
・産後の身体の回復状況の観察(子宮復古状況、悪露の量や色のチェック)
・産後の体調管理(赤ちゃんを預かり休息時間の確保、疲労回復のケア、栄養バランスの 整った食事提供)
②母親の心理的ケア
・ママのメンタルチェック(エジンバラチェック表からリスク評価)
・家族関係の調整(夫や実母との関係性、家族への期待とズレの調整)
③適切な授乳が実施できるためのケア
・授乳相談・指導(授乳方法、母乳量測定、母乳分泌とミルクとのバランス)
・母乳トラブルのケア(乳房ケア、乳腺炎予防、母乳分泌促進のための母乳ケア)
④育児の手技についての具体的な指導及び相談
・新生児の発育状況の確認(排泄回数、色・身体計測・運動知的発達状況)
・新生児のお世話(ママが休息をしている間赤ちゃんを預かり、お世話をする)
・育児全般の相談(沐浴、泣きへの対応、寝かしつけ、抱っこの仕方、補完食・離乳食のすすめ方)
⑤生活の相談、支援
・食事提供(手作りの食事や希望のお弁当などを提供、帰宅後の生活の参考になる食事を提 供)
・社会資源の情報提供(ファミリーサポートセンター、子育て支援センター、保育園入園の 手続きなど)
・市町村、医療機関への連絡(連絡票を用いたり事業利用後の報告を行い、連携を図る)
乳房ケアや授乳育児指導の他にも、オプションとして鍼灸、アロママッサージ、骨盤軸整体のようなサービスを提供することも可能です。事業の趣旨と内容をよく理解し、ママの要望に合わせて支援することが重要です。

4.産後ケア事業で働きたい!
産後ケア事業は、病院で行う産後〜生後1か月までのケアとは異なり、生後1年まで母子を長期的に支える事業です。出産直後の体調回復や授乳支援だけでなく、生後1年までの発達や育児の相談にも対応します。そのため、幅広い時期と課題に対応できる知識と技術が求められます。身体的・心理的な不安やストレスを抱える方に寄り添いながら支援する力を身につけ、従来の助産師業務や病棟業務とは異なるスキルや、新たな学びも必須になります。
<知識面>
子どもの成長発達に関する質問も多く、幅広い知識が求められます。特に地域の社会資源や子育て支援制度については、ママたちに具体的な情報提供ができるレベルまで理解を深める必要があります。
・産後・生後1年までの母子の発達や変化の理解
・離乳食に関する知識
・社会資源に関する知識
・地域の子育て支援制度の理解
<技術面>
基本的な助産師の技術に加えて、家庭環境に応じた柔軟な指導技術が求められます。病院とは異なる環境での指導になるため、その場に応じた工夫が必要です。
・乳房ケア技術
・授乳育児指導技術
・新生児・乳児のケア技術
・家庭環境に応じた生活指導技術
<コミュニケーション面>
産後ケア事業で最も重要なのは、コミュニケーション能力かもしれません。ママが答えを求めていることもありますが、まずはママが自分の不安や思いを安心して話せるような関係性を築くことが重要です。身体的・心理的にストレスを抱えているママたちに寄り添い、安心して話せる環境を作ることが何より大切です。
・ママが安心して話せる傾聴スキル
・家族関係の調整能力
・自治体や医療機関との連携スキル
産後ケア事業は年々予算が増額され、国からも大きな期待を寄せられている重要な事業です。利用率も着実に上昇しており、今後も需要の拡大が見込まれます。産後ケア事業における助産師のニーズは高く、専門性を存分に発揮できる魅力的な仕事であり、新たなキャリアの選択肢としても注目が高い分野です。一人ひとりの母子に手厚いケアを提供できる産後ケア事業は、少子化が進む中でも成長が期待できる数少ない仕事と言えるでしょう。
母子が安心して子育てできる社会の実現には、まず地域や近隣地域の産後ケア事業の現状を知ることが大切です。各自治体のホームページでは、実施している事業形態、自己負担額、利用可能回数、利用時間などの詳細を確認できます。制度の存在を知らない母親も多いため、助産師が正確な知識を持ち、退院指導などで適切に情報提供することが重要です。助産師一人ひとりの小さな一歩が、すべての母子の幸せな未来へとつながっていきます。

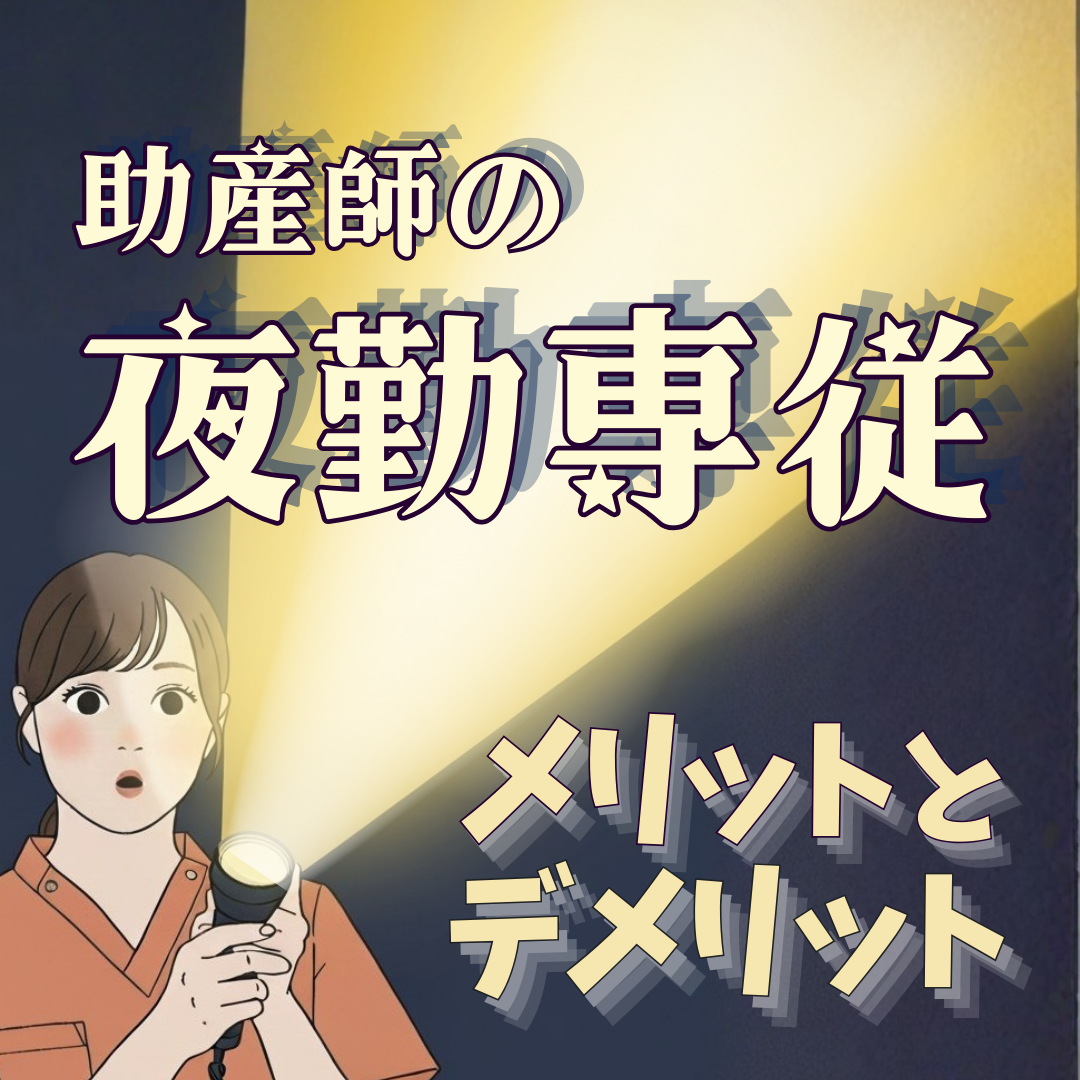



.png)
