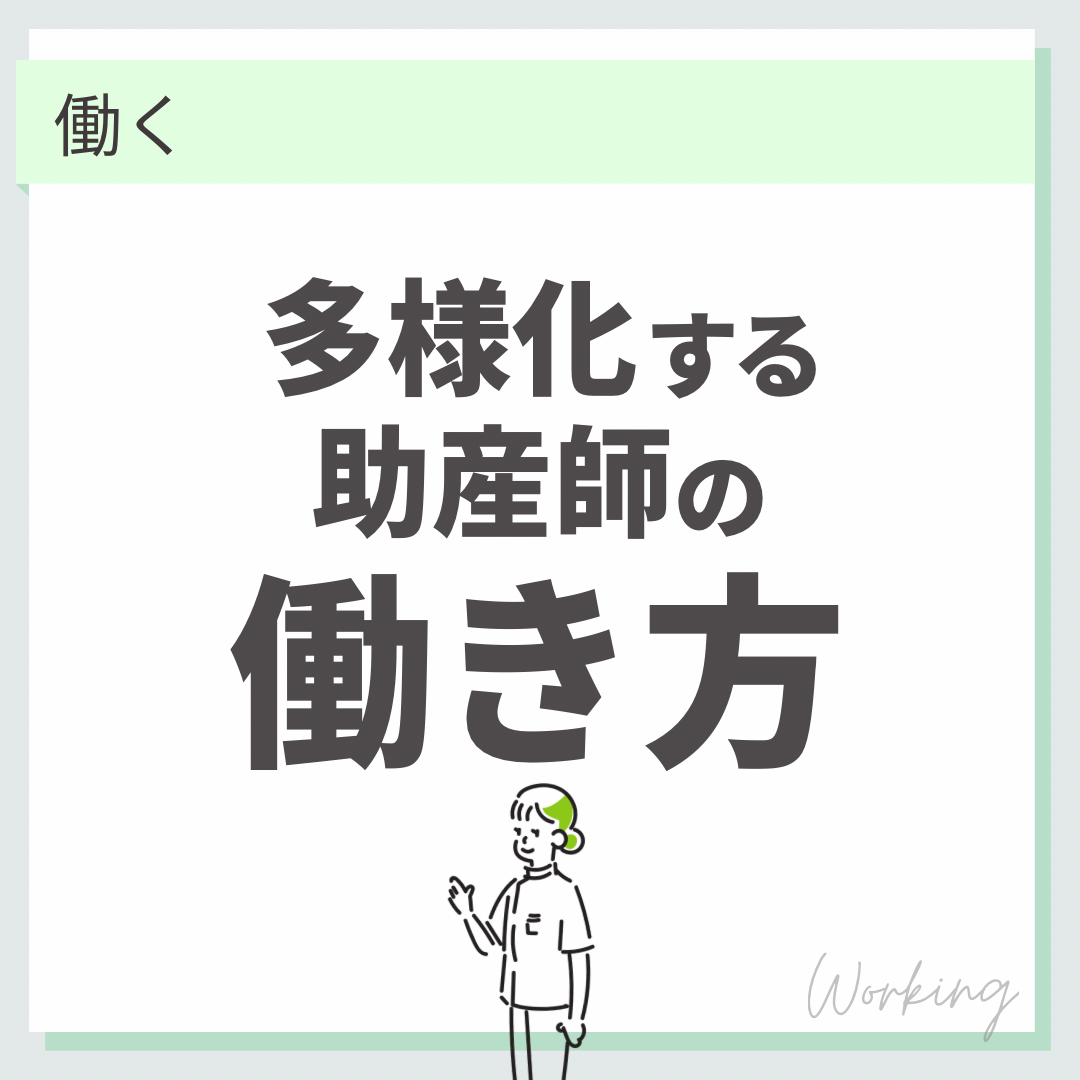
【最新】多様化する助産師の働き方
- キャリアアップ
- 助産師の未来
- いろんな所に助産師
助産師の職場といえば、多くの人が病院・クリニック・助産院での働き方を想像しますよね。もちろん出産の現場や産後直接的に育児指導や相談にのる臨床での業務は、どの時代においても必要不可欠な母子へのケアです。
今回はこれ以外の働き方について、深掘りしていきます。
臨床で働く
一つの職場にこだわらない臨床での働き方として、応援助産師や派遣助産師があります。これは人材不足である地方の病院へ派遣として出向するシステムで、数ヶ月〜1年程度と短期間での採用が多いです。全国各地での募集があり、地方や離島などでも募集しているため、旅行や観光気分を味わえることが魅力です。
また、他国の助産師免許を取得して勤務したり、青年海外協力隊など海外で助産師として働く方法もあります。国によって文化の違い、出産・育児への考え方の違い、医療技術の違いなど新しい学びがたくさんありそうですね。言語の壁もあるため、同時に語学力も身に付きます。

行政で働く
行政での働き方としては地域の母子保健訪問業務があります。保健所や区役所の職員として働く方法と、市区町村と契約し依頼を受けて働く方法があります。どちらの働き方でも、産後のママたちの育児・母乳相談にのったり、ママの心身の健康を観察、新生児の発育状況の観察などが主な業務になります。地域に出向いてそれぞれの家庭に合った育児を一緒に考えるため、臨床とは違って思考の柔軟性が求められます。また直接産後のママ達と関わる業務の中では、比較的自分のQOLを大切にした働き方です。
一般企業で働く
一般企業での働き方として、メディカルコールセンター業務があります。トリアージや医療機関と医療機関をつないだり、医療機器メーカーや製薬会社の問い合わせ窓口、また保険会社など一般の人から相談を受ける場合もあります。健康状態や薬剤に関する問い合わせなど、専門的な知識を活かしたコールセンター業務です。
また治験コーディネーターとしての働き方もあります。治験コーディネーターとは薬治験を実施する医療機関において、治験のスムーズな進行をサポートする業務です。医療機関への提案とコーディネート、協力してもらう被験者への説明に始まり実施中〜実施後の業務全般を担うため多くの知識やノウハウを必要とします。プレゼンテーション能力やコミュニケーション能力が磨かれる仕事です。
保育園や幼稚園、病児保育で働くこともできます。子どもの健康管理や怪我の手当がメインで、医療行為を行う場面は多くはないです。園内の衛生管理などの業務を担うことも多いので、感染対策についての指導が必要になってきます。

他にも、看護や助産の教員としての働き方もできます。学校の教員や実習指導者として学生指導をすることで自分自身の学びの再確認にもなりますし、学生の発想により新たな刺激を受けられたりします。自分自身の指導技術の学びにもなりますね。
フリーランス
最近ではフリーランス助産師が増えてきた印象です。助産院として開業届を出している場合もありますが、助産師の知識や経験を活かして、講習や講演会、情報発信、妊産褥婦や助産師向けの講座を販売するという開業方法もあります。最近ではベビーマッサージ、マタニティヨガ、ニューボーンフォトなどを主軸に仕事をしたり、SNSやオンライン上での業務で在宅ワークを叶えている助産師もいて、助産師の働き方が大きく変化してきていると感じます。
本記事で見てきたように、助産師の働き方は非常に多種多様です。それぞれの選択が個人のキャリアアップや人生の目標・やりがいへ続く道になります。どの道を選んでも、助産師として考え方が深まるはずです。また自分の助産師としての道だけではなく、自身のライフスタイルやライフステージに合った職場・働き方を選ぶことも必要だと思います。自分の可能性を狭めず、広い視野でこれからの働き方・生き方へのヒントを探してください。
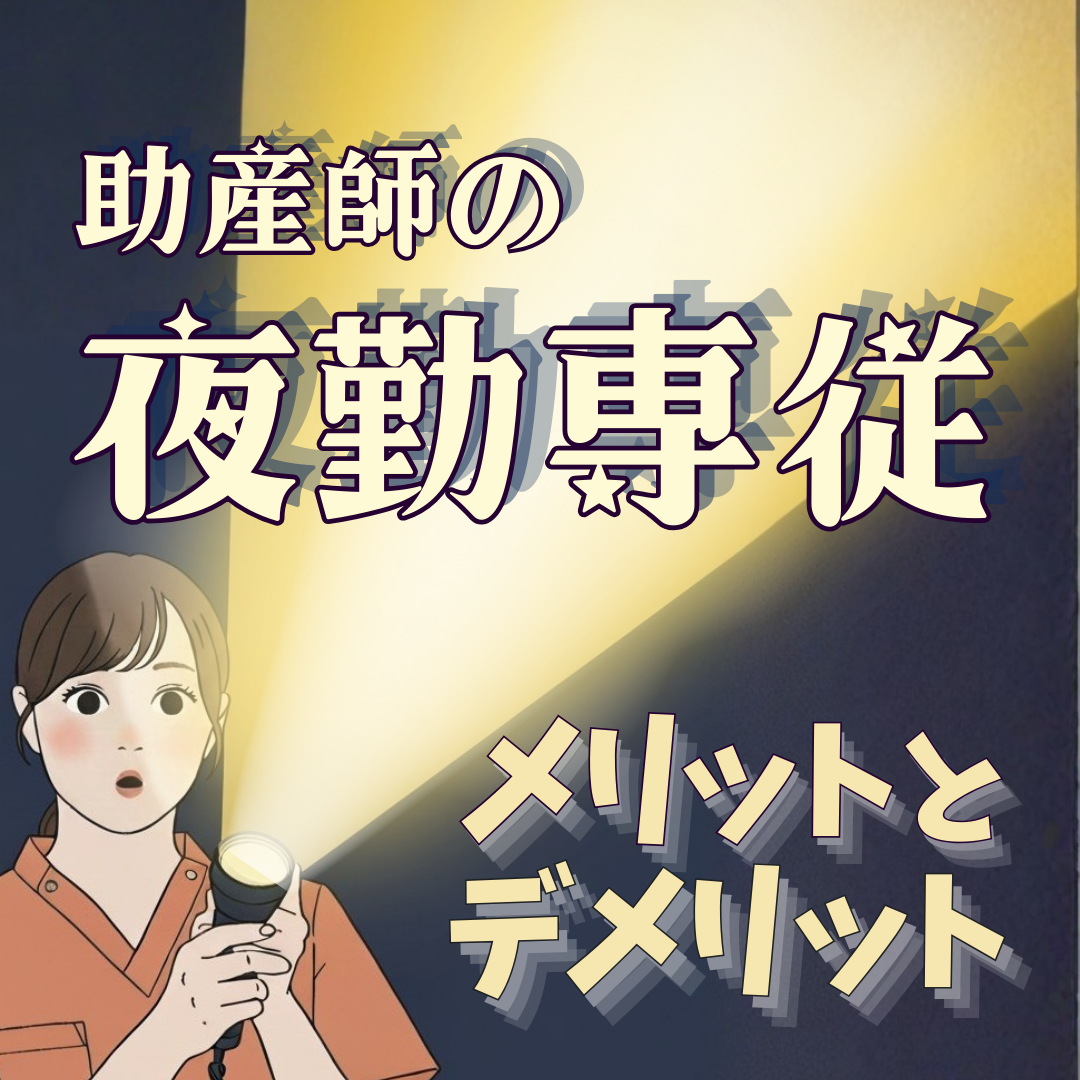



.png)
