
【助産師なら知っておきたい】過期産のリスクとは|合併症のリスクと注意すべきポイント
- 妊娠週数
- 予定日超過
- 助産師の判断とケア
正期産といわれる時期は妊娠37週0日から妊娠41週6日までの分娩を指します。妊娠42週以降の妊娠を過期妊娠、妊娠42週以降での分娩を過期産と呼びます。
産院によって管理方法は多少異なりますが、出産予定日(妊娠40週0日)を過ぎても出産に至らない場合は、妊娠週数が適切であるかを再度見直しを行います。また、数日間隔で妊婦健診を行い、慎重に妊娠や胎児の管理を行います。
産院によっては、予定日前後や、予定日を超過した段階、分娩誘発の計画や内診で卵膜剥離を行う場合もあります。
このように過期産を予防し、そのリスクを避けるために慎重な周産期管理が行われています。実際に2023年には全出生数727,288人のうち718人が過期産での出生となっており、全体の約1%という現状があります。
過期産を避けるため徹底的に管理されているからこそ、過期産のリスクについて正しく理解しておきましょう。
リスク① 羊水過少
胎盤の寿命は一般的に出産予定日から2週間程度とされています。そのため、出産予定日を過ぎると、胎盤の機能が衰退します。胎盤機能が低下すると、循環が悪くなるため、胎児への血流循環も悪化します。その結果、胎児の腎血流量が減少し、胎児の尿産生も減少するため、羊水過少のリスクが高くなります。
羊水過少になると、子宮壁や胎児によって臍帯圧迫を起こすリスクも高まります。臍帯が圧迫されることで胎児に充分な酸素が行き渡らなくなるため、胎児の低酸素血症やアシドーシスが進行し、胎児機能不全のリスクにもつながりかねません。
また胎児機能不全となれば、それもまた胎児にストレスがかかってしまいます。そのため、羊水混濁やそれによる胎便吸引症候群の発生リスクを高めることにもつながります。
さらに胎盤機能不全の状態が続くと、胎児に充分な栄養が行き渡らなくなります。そうすると、胎児は自分の蓄えていたグリコーゲンを分解し、栄養に変えていきます。その結果、胎児は胎脂が減少して、しわの多い老人のような顔貌、皮膚の乾燥やひび割れが起こります。また栄養不足のため、低体温、低血糖、体重減少などの合併症を誘発する可能性も考えられます。
対策・ケア
対策として予定日を超えた妊婦では、週に1-2回の頻度で妊婦健診を行います。エコーで羊水量を確認し、CTGを装着して、胎児のwell-beingを確認しておくことが重要です。羊水過少や胎児機能不全の兆候が認められる場合には、早めに分娩誘発を計画する必要があります。

リスク② 羊水混濁
胎盤機能が低下することによって、子宮内環境が悪化したり、胎児機能不全が起こります。このような状況は胎児にとってストレスがかかるため、胎内で胎便を排出することがあります。胎便によって羊水が汚れることを羊水混濁と言います。
羊水混濁が起こると、児が出生する際にその胎便を吸い込んでしまい、気道閉塞や炎症、肺サーファクタントの不活化が起こります。その結果、全身チアノーゼとともに無気肺や肺気腫、化学性肺炎を引き起こす可能性があります。このような胎便による呼吸器障害を胎便吸引症候群と言います。特に胎児機能不全を合併していると、児が出生児にあえぎ呼吸となり、さらに胎便を吸引する可能性が高まります。
胎便吸引症候群による呼吸障害が続くと、児にとっては低酸素血症状態が続くことになります。そのため、新生児遷延性肺高血圧症(PPHN)や肺の過膨張部分からの空気漏れによる緊張性気胸などの合併症につながるリスクもあります。
対策・ケア
羊水混濁は破水したり、胎胞内の羊水の色を確認することで初めて確認することができます。そのため、羊水を確認できるようになるまでは、CTGを装着し胎児機能不全の有無やその兆候をこまめに確認しておく必要があります。
また羊水混濁がある場合には、児が出生した後すぐに鼻腔や口腔周囲から羊水をぬぐいます。児の啼泣時に咽頭でゴロゴロと音が聞こえる場合には、口腔内、鼻腔内の順で吸引を行うこともあります。重篤であれば気管挿管や人工呼吸器の対応が必要となる場合もあるため、NICUへの搬送や転院も考慮しておきましょう。

リスク③ 巨大児
出産予定日を過ぎても胎盤機能が低下せず順調に妊娠が継続できる場合があります。その場合、今までの妊娠経過と同様に児は胎内で順調に成長を続けていくことができます。その結果、巨大児(出生体重4,000g以上)となる場合があります。
巨大児となると、分娩第1期には微弱陣痛となって分娩遷延や分娩停止に陥る可能性が考えられます。また、分娩第2期には肩甲難産や分娩時外傷や損傷を負う場合もあります。外傷や損傷としては頭血腫、骨折、神経麻痺が多いとされていますが、時に脊椎や脊髄損傷や臓器損傷など重篤な合併症となるリスクもあります。さらに産後は産道裂傷が大きくなったり、弛緩出血を起こす可能性も高いと考えられます。
さらに巨大児は、出生後に低血糖となるリスクが高まります。これは、児のグルコース消費が増大し、自分で蓄えているグリコーゲンが不足することや、母体の影響によってインスリン分泌亢進状態が出生後も継続している場合に起こることがあります。
対策・ケア
妊婦健診時に推定体重を計測し、巨大児が予測される場合には早めの分娩誘発を検討することがあります。また、分娩時には内診やエコーで、胎児の回旋や児頭下降を確認し、経腟分娩が危険だと判断される場合には帝王切開へ切り替える場合もあります。
出生後に低血糖を認める場合には、ミルク哺乳を行いますが、それで改善がない場合にはNICUに入院し輸液管理を行うことがあります。
また妊娠中から適切な食事管理や体重コントロールを行うことも重要です。

過期産になることで様々な母体や胎児へのリスク、合併症を伴う可能性が高まります。そのため、過期産やそれに伴う合併症を予防するためには、医師と連携しながら、妊婦健診やCTGでその兆候がないかを丁寧に観察していく必要があります。
また、実際に妊婦や家族へ過期産や分娩誘発の説明を行う場合には、過剰に不安を煽らないように、母児の安全に配慮した方針や手段をとることを具体的に説明しましょう。
中には自然分娩にこだわりがあり、分娩誘発や帝王切開には否定的な考え方を持っている妊婦や家族もいます。そのような妊婦と家族の気持ちを受け止め、安全を守りつつできる限り希望に寄り添った分娩方法を検討できると良いですね。
正期産に入る前から適切な食事や運動、体重コントロールを行うことや、乳頭マッサージを行うことで予定日超過や巨大児のリスク軽減につながることもあります。妊娠中の保健指導や助産師外来で、日頃の生活で予防できるリスクや合併症があることを伝えておきましょう。
【参考文献】
1.岡庭豊ら. 病気がみえるvol.10 産科 第4版. メディカ出版
3. 予定日を過ぎているのに、生まれない!(予定日超過)|東京・世田谷での出産・分娩なら国立成育医療研究センター 産科
4. 赤ちゃんが大きすぎる(巨大児)といわれたら? - 産科医療LABO
5.人口動態調査 人口動態統計 確定数 出生上巻 4-24 妊娠期間(4週区分・早期-正期-過期再掲)別にみた年次別出生数及び百分率 | 統計表・グラフ表示 | 政府統計の総合窓口

【新人助産師と学生が押さえておきたい】CTG(NST)モニターの基礎知識|基線・基線細変動・一過性頻脈の見方をわかりやすく解説
- CTGモニター
- モニター判読
.png)
【助産師必見】超音波検査での胎児計測|基本項目と正しい計測方法を徹底解説
- 超音波検査
- 助産師によるエコー検査

“なんとなく”の指導はもう終わり。エビデデンスに基づく乳頭ケアの指導方法|妊婦さんの「やってみよう」を引き出す助産師の言葉は?
- 乳頭マッサージ
- 妊娠中

明日から使える!妊婦さんの不安を解消する「会陰マッサージ」指導のポイント|最新のエビデンスも解説
- 会陰部マッサージ
- 会陰部切開
- 経腟分娩
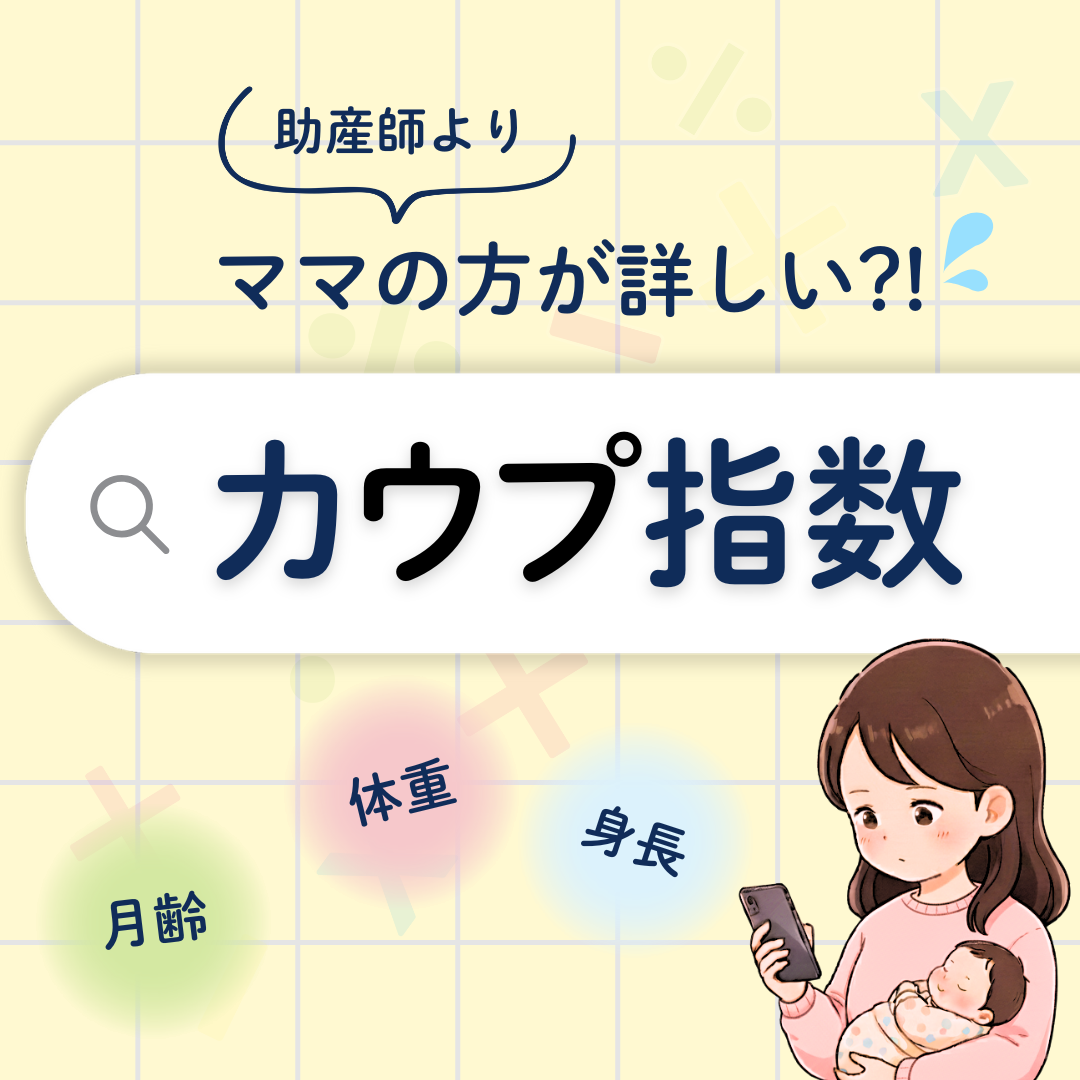
【月間3.8万検索の衝撃】ママの方が詳しいかも?助産師が知っておくべき“カウプ指数”の常識
- カウプ指数
- 月齢
- 乳幼児

Late Preterm児(後期早産児)とは?特徴・リスク・看護のポイントを徹底解説
- 早産
- Late Preterm児
- 後期早産児