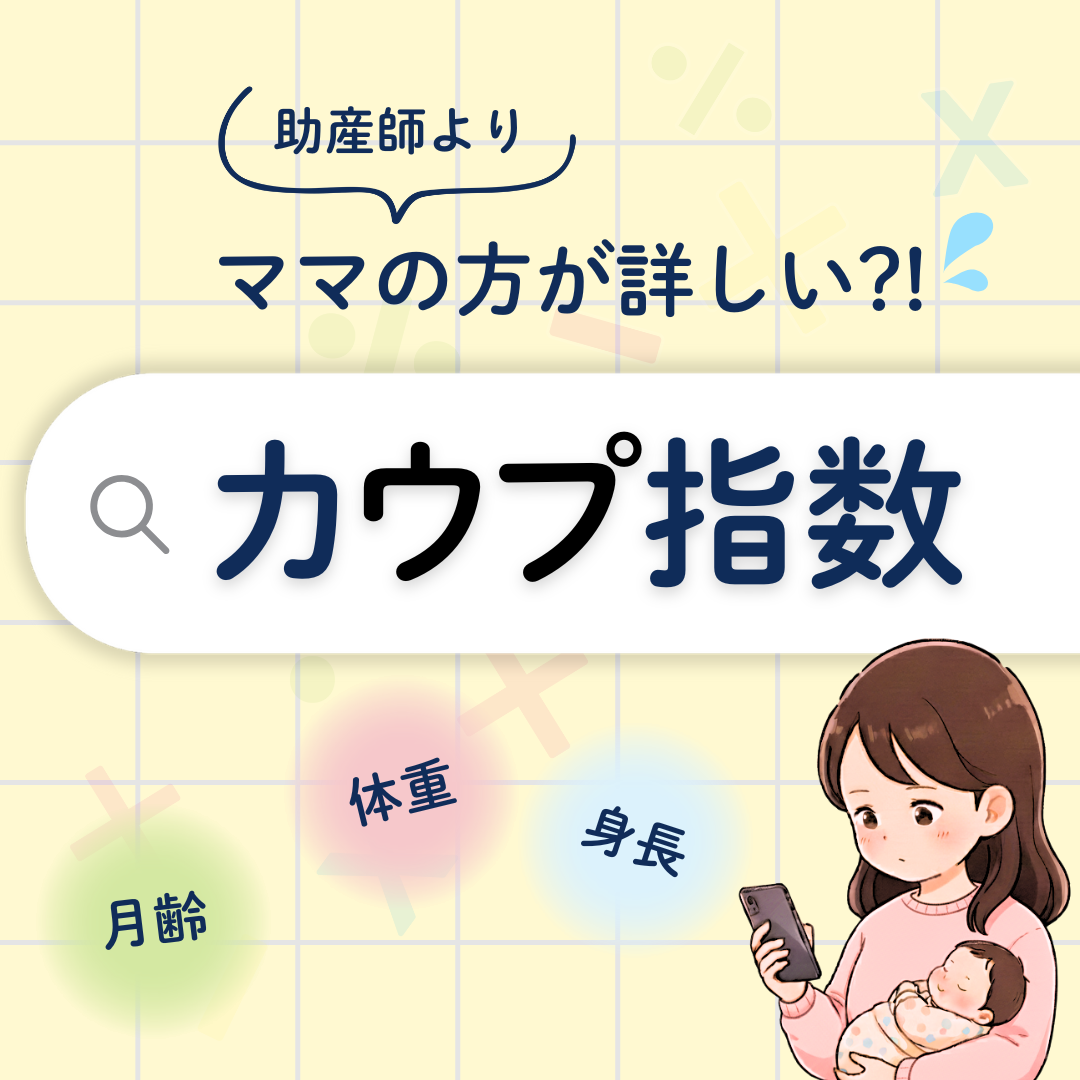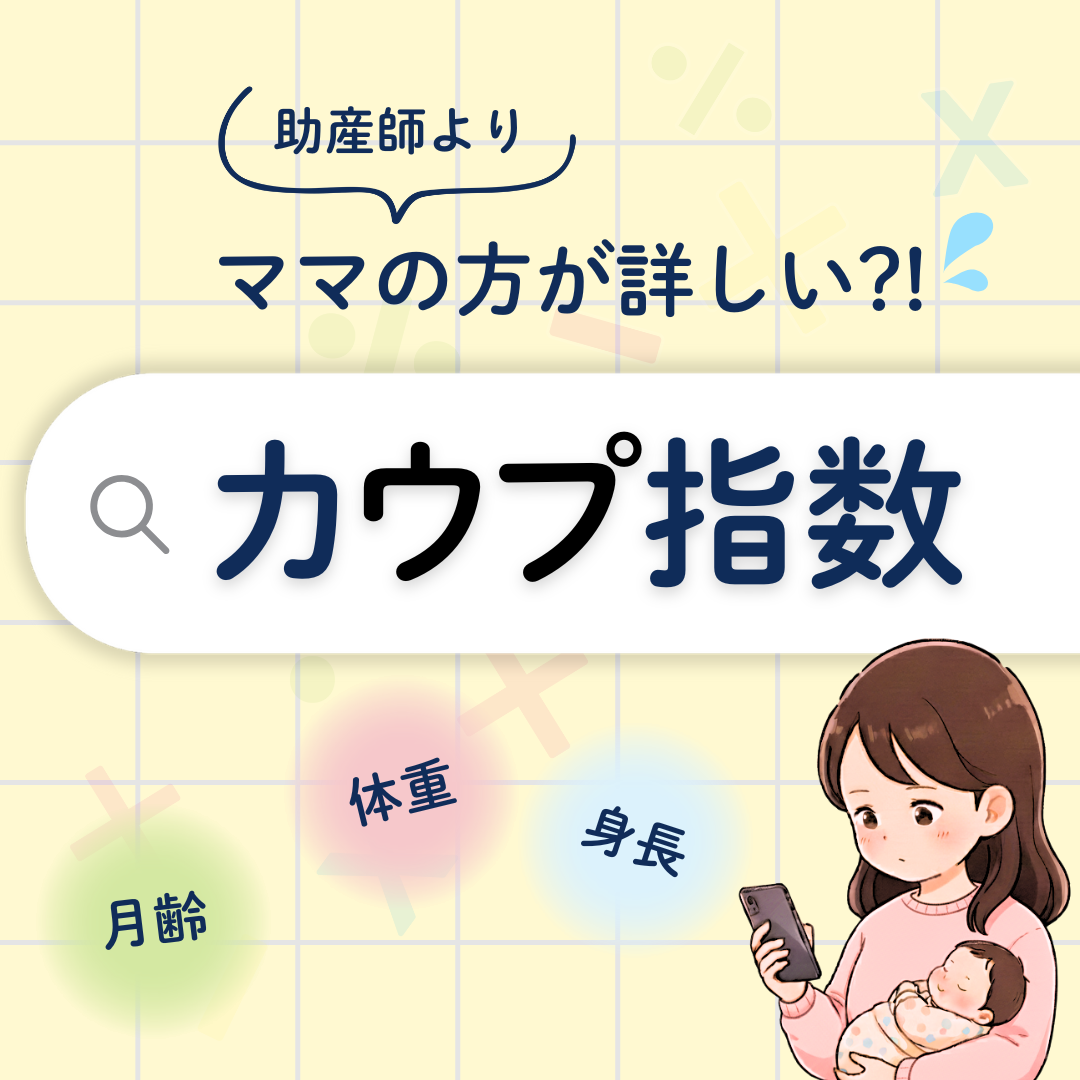
カウプ指数(Kaup Index)は、乳幼児の体格(身長と体重のバランス)を数値で表すための指標です。おおむね1〜5歳の子どもを対象に使われ、主に乳幼児健診や栄養指導などで活用されています。考案者はドイツの小児科医フリードリヒ・カウプ博士で、小児保健分野に導入されてから日本中に広く普及しました。文部科学省の成長評価基準や日本小児科学会の資料にも記載されており、国内では「乳幼児のBMI」として扱われています。
カウプ指数=体重(g)÷身長(cm)2×10
たとえば、体重10kg(=10,000g)、身長80cmなら、10,000 ÷ (80×80) ×10 = 15.6 です。この計算で求めた数値を基準表と照らし合わせて体格の状態を確認します。乳幼児では体水分量や脂肪の割合が年齢によって大きく変わるため、成人のBMI(体重kg ÷ 身長m²)では適切に評価できません。カウプ指数は、その変化の大きい時期でも体格を把握しやすいように工夫された指標です。
カウプ指数 | 判定区分 |
13.0未満 | やせすぎ |
13.0〜14.4 | やせ気味 |
14.5〜16.4 | 標準 |
16.5〜18.4 | 太り気味 |
18.5以上 | 太りすぎ |
多くの子どもは15前後に分布しますが、「15なら正常」ではなく、「14.5〜16.4が標準範囲」で、この範囲内にあっても、体重や身長の増え方がゆるやかすぎる、あるいは急に変化している場合は注意が必要です。たとえば同じ「14.0」でも、前回よりも順調に増加しているなら問題なしと判断できますが、急に数値が低下した場合は栄養や疾患の影響を考慮するなどこれまでの経過を踏まえて判断する必要があります。つまり、カウプ指数は1回の数値で良し悪しを決めるものではなく、発育の“傾向”を見ていくための指標です。

カウプ指数の主な対象は1〜5歳ですが、日本では乳幼児健診や保育現場で生後3か月以降から参考値として活用されています。この時期になると体水分率が安定し、体重の増減も緩やかになってくるためです。一方で、新生児〜生後2か月ごろまでは体重変動が大きく、授乳量・排便・体調などで数百グラム単位の差が出ることもあります。そのため、カウプ指数を用いて評価しても信頼性は低く、適切ではありません。生後3か月を過ぎてからの健診や産後ケアでは、「今のお子さんの体格のバランスを知るひとつの目安として使えます」と説明した上で使用すると良いです。
カウプ指数を使う目的は、数値で「安心」を届けることです。「カウプ指数では標準範囲に入っていますよ」と伝えるだけでも、ママがほっとすることがあります。また、説明のときは「なぜ大丈夫なのか」を根拠とともに伝えると、さらに信頼につながります。たとえば「少し体重は軽めですが、身長も順調に伸びているので問題ありません。」「この数値は標準範囲内です。今のペースで大丈夫ですよ。」「ぽっちゃりしているように見えるかもしれませんが、カウプ指数で見ると標準の範囲ですね。」など、ママが不安に思っている部分が解決できるような説明を心がけましょう。
ママたちは、インターネット上の情報を読んで「数値=良し悪し」と受け止めがちです。助産師は「その数字には幅がある」「お子さんの発育ペースを見ていくことが大事」という視点を加えることで、過度な不安を和らげることができます。また、「標準です」という一言よりも、「カウプ指数を計算してみると標準ですし、成長曲線に沿っていて順調ですよ」「この子らしいペースで育っていますね」と伝える方が安心感を与えます。ママにとって“数値の正解”よりも、“この子は大丈夫”という実感の方が重要です。カウプ指数は、その安心をサポートするための道具として使うと良いでしょう。
カウプ指数は便利な指標ですが、使い方を誤ると誤解を招いてしまいます。助産師として意識しておきたいポイントがいくつかあります。
発育曲線・栄養・生活習慣・発達の状態など、総合的に子どもの成長を見ることが大切です。「標準範囲外=異常」ではなく、どうしてそうなっているのか「その理由を探る」姿勢を持つようにします。
服やオムツの重さ、測定の時間帯、直前の授乳などで数値が変わることがあります。身体測定の際には測定条件を一定にしておくことで経過の比較がしやすくなります。
子どもの成長には波があります。寝返りやひとり歩きなど活動量が一気に多くなる時期は体重の増加が緩やかになることもあります。体調不良で一時的に体重が減少してしまうこともあります。体調不良が原因であれば「少し減っても翌月戻る」ということもよくあります。乳幼児の成長は1回の測定で判断するのは難しいです。数回分のデータで判断するようにしましょう。
数値が大きく外れている場合や、成長の停滞がある場合は、小児科医・栄養士などと連携して評価することが重要です。成長を阻害している疾患などの有無やミルクの量、離乳食の進み方など必要な情報を細かく丁寧にママから聞き取りましょう。
カウプ指数を扱うとき、助産師がつまずきやすいポイントを整理しておきましょう。
14.5〜16.4が標準範囲ですが「範囲の中でどう変化しているか」が大切です。15は標準範囲ですが、前回と比較して数値が大きく変動している場合には注意が必要です。
食欲旺盛・活動的であれば、多少高めでも問題ないことが多いです。むしろ極端にやせている場合の方がリスクが高いこともあります。これまでの経過と合わせて判断しましょう。
小柄な体質や、測定誤差、体調の一時的な変化で低く出ることもあります。「一度低めに出た=異常」ではないと伝えることが大切です。
「体重の増え方が少ない気がして心配です」と話すママに、「カウプ指数では標準範囲です。身長も順調なので大丈夫ですよ」と伝えられると、安心感が生まれます。
乳幼児健診で「やせ気味」と判定された家庭に対し、生活習慣・食事内容を一緒に見直す際のきっかけとして使えます。
新人助産師や看護師に対して、体格評価の基礎としてカウプ指数を教えると、成長評価の全体像を理解しやすくなります。
カウプ指数は、乳幼児の体格を客観的に把握するための基本的な指標です。1〜5歳の子どもを中心に使われますが、生後3か月以降の赤ちゃんにも参考値として活用できます。助産師が正しい知識を持っていれば、ママの不安に根拠をもって寄り添うことができます。「標準です」「この範囲なら大丈夫ですよ」と数字で安心を伝えることはもちろん、「この子らしいペースで成長していますね」と伝えることが大切です。ママたちが検索している言葉を、助産師が“自分の言葉”で説明できることが信頼を育てる第一歩です。数字を伝えるだけでなく、その意味を一緒に読み解ける助産師を目指していきましょう。

.png)