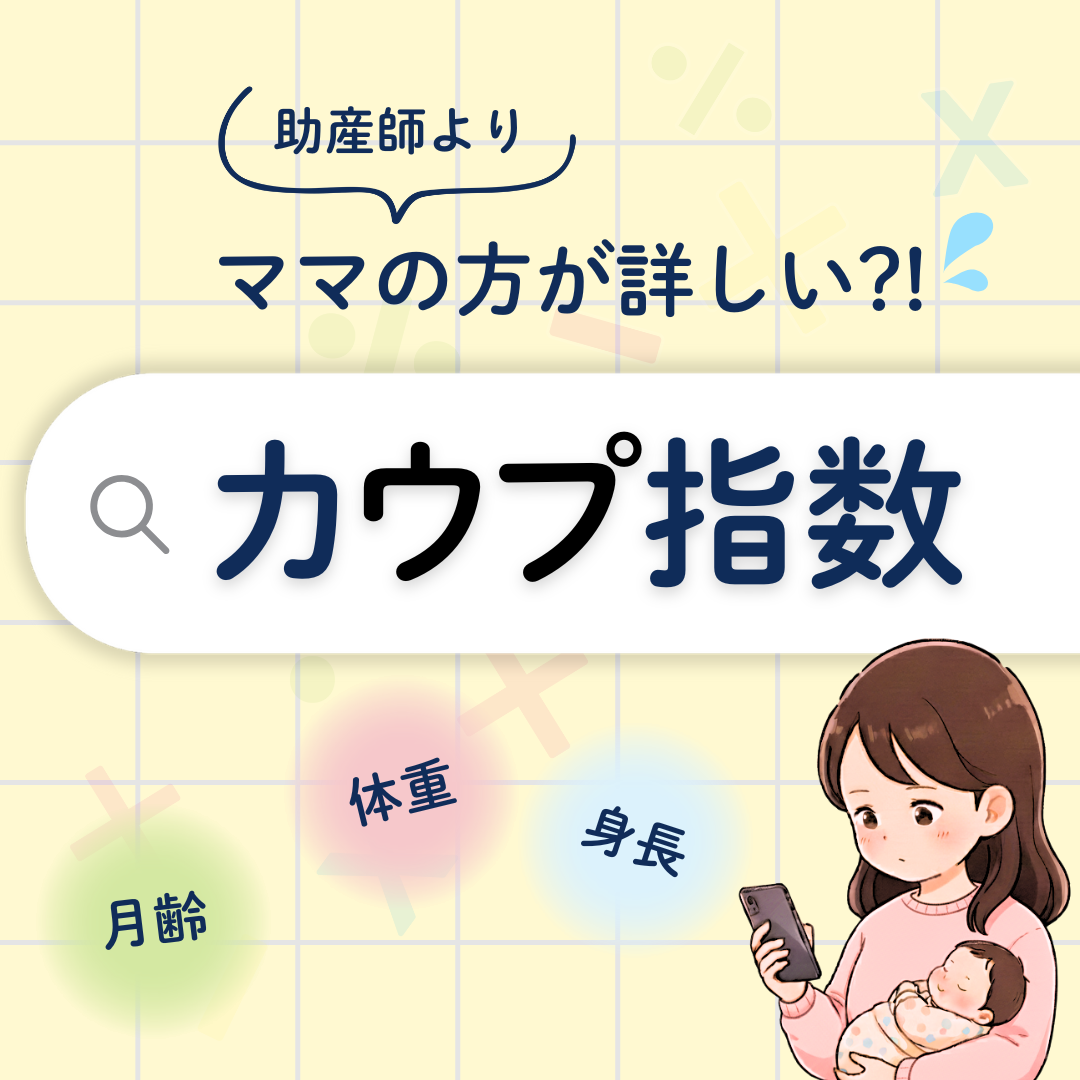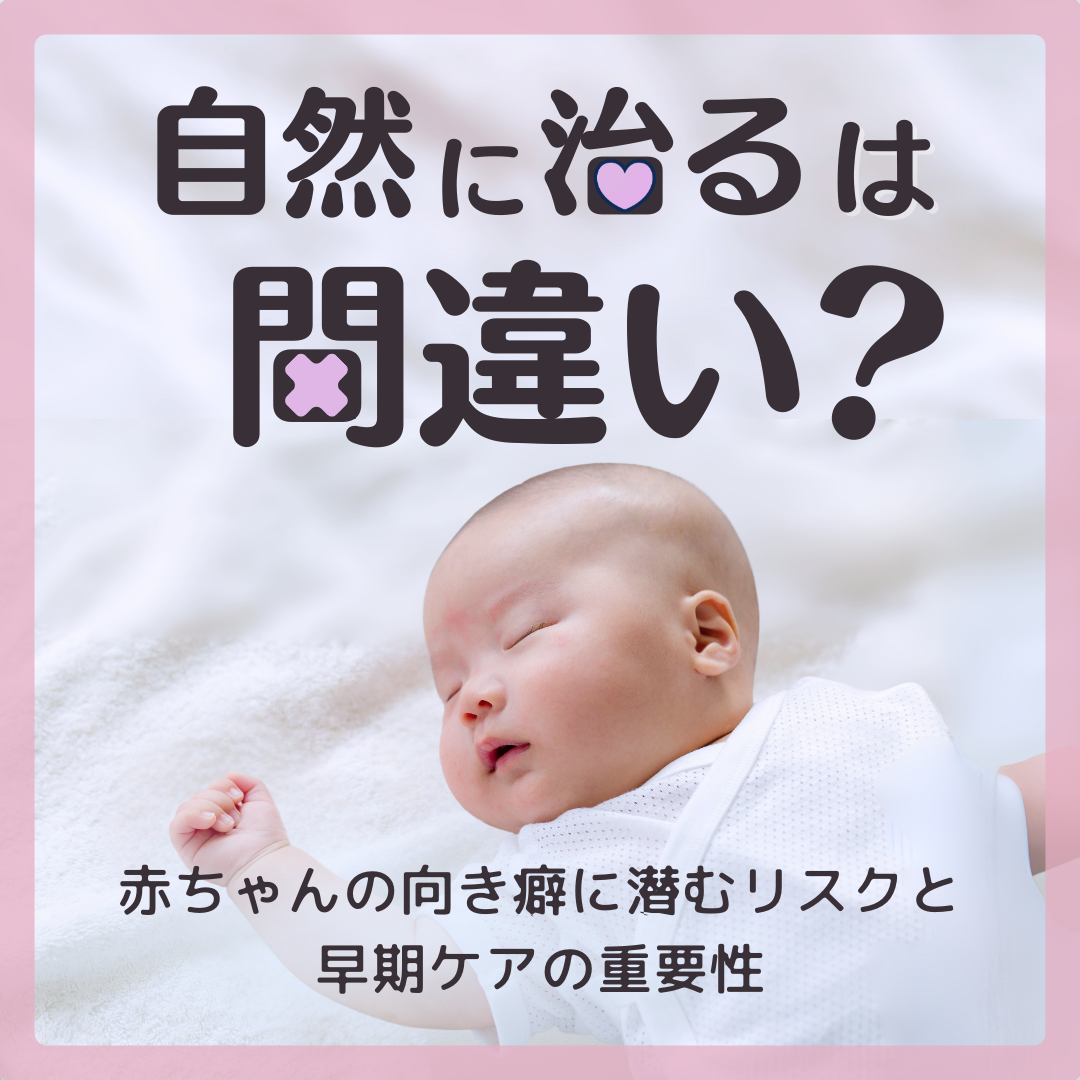
向き癖とは仰向けに寝ている赤ちゃんが、特定の方向ばかりに頭を向ける傾向を指します。出産時の体位、子宮内での姿勢、筋緊張の左右差、哺乳や抱っこの習慣などが関係しています。
同じ側に頭を向け続けることで、後頭部の骨が扁平になる「斜頭症」や、頭全体が横に広がる「短頭症」が起こります。見た目の問題だけでなく、次のような影響が生じることがあります。
・表情筋の左右差(目の大きさ、口角、頬のふくらみ)
・顎の非対称な成長による噛み合わせ不良
・耳や眼球の位置のずれ、視覚・聴覚刺激の偏り
・将来的な歯列不正や咀嚼機能の低下
赤ちゃんが一方向ばかりを見ていると、世界の半分しか認識できないような状態になります。その結果、次のような運動発達への影響が見られることがあります。
・寝返りが片側にしか打てない
・ズリバイやハイハイで左右非対称な動きになる
・体幹のバランスが崩れ、姿勢保持が不安定になる
・回旋運動が苦手になる
・歩行時や就学期に不器用さとして現れることも
・骨盤や股関節への影響
常に同じ側に体重がかかることで、股関節や骨盤の柔軟性・可動域に左右差が出てきます。これは、将来的な歩行時の姿勢やスポーツ時のバランス感覚などにも影響を及ぼす可能性があります。
産まれてすぐ〜生後1か月頃までには介入を開始するのが理想です。首がすわる前のこの時期に対応することで、後頭部の変形や筋肉の左右差を最小限にとどめることができます。
6か月以降になると頭蓋骨の可塑性が低下し、自然な改善が難しくなります。著しい頭蓋変形がある場合には、頭蓋形状矯正ヘルメットを用いる治療が検討されることもありますが、費用や装着への負担を考慮すると、できる限り予防的なケアが望まれます。
産後の入院中や1か月健診、新生児訪問、産後ケア外など助産師は赤ちゃんの姿勢や抱っこの様子を間近で観察することができます。「いつも右を向いて寝ている気がする」「写真を撮るといつも同じ向き」などのママの声も重要なヒントになります。向き癖に早く気づき、ケアの方法を具体的に伝えられるのが、助産師の強みです。

対策:毎回左右交互の腕で授乳・抱っこをする習慣をつける。特に片側からの哺乳が続かないように意識づけを行う。
根拠:同じ腕での抱っこは赤ちゃんの首や体の向きを固定しやすく、筋緊張の偏りを助長します。交互のポジショニングで左右の筋肉をバランスよく刺激できます。
注意点:反対側に無理に向けようとせず、赤ちゃんが自然にそちらに興味を持てるように導くことが大切です。
対策:おもちゃを置く位置や声をかける方向を、向き癖とは反対側に設定する。授乳やオムツ替えも、意識的に反対側から行う。
根拠:赤ちゃんは音や光、人の顔に反応して頭を動かします。感覚入力のある方向へ自然に向く性質を活かして、首回旋の誘導ができます。
注意点:左右どちらかに過剰な刺激を与えすぎると、今度は反対側に新たな癖がつくこともあるため、日替わり・時間交替などでバランスを取るのがおすすめです。
対策:ベビーベッドの配置や寝る方向を変えて、ママの顔や光のある方向が自然と反対側になるようにする。必要に応じて、向き癖と反対側にタオルや布をあててサポートする。
根拠:赤ちゃんは自然と関心のある方向を向くため、生活環境の工夫で無理なく向きを調整できます。
注意点:サポート用のタオルは必ず硬めで小さめのものを使い、口や鼻が埋もれないように注意。夜間や無人時には避け、目の届く昼間に限定しましょう。
対策:1日2〜3回、1回数分からスタートし、慣れてきたら5〜10分へと時間を増やす。ママの胸の上で行うのも有効。
根拠:首・背中・体幹の筋力をバランスよく刺激でき、仰向け時の頭部圧迫を避けることができます。首すわりや寝返りの促進にもつながります。
注意点:満腹時や眠いときは避け、吐き戻しに注意。赤ちゃんの嫌がる様子があれば無理せず中断し、楽しい雰囲気で行うことが大切です。
対策:首や肩周囲、股関節など、左右の筋緊張を整えるやさしいマッサージを日常に取り入れる。
根拠:筋肉の柔軟性が向上すると、自然な動きが出やすくなり、向き癖の矯正もスムーズになります。
注意点:施術は赤ちゃんの体調や機嫌の良い時間に行い、力を入れすぎず、心地よい刺激を意識しましょう。専門職による指導のもと、ママが継続的に行えるよう支援することが望ましいです。
対策:赤ちゃんの頭や体が偏らないように設計された抱っこひもを選び、正しい使い方をママに伝えましょう。
根拠:長時間使用する育児用品が不適切な姿勢を助長することがあるため、育児環境全体を見直すことが大切です。
注意点:ママの身体への負担も考慮し、負担が少ない抱き方やサイズ調整もサポートしましょう。

・頭の変形が著しく、見た目でも明らかな左右差がある
・哺乳や授乳に影響するレベルの首の緊張や傾きがある
・生後6か月以降も改善傾向がみられない
・寝返り、ズリバイ、ハイハイが一方向のみで進む
・表情に左右差があり、目や口の開き方が違う
このような場合には、小児科や頭の形外来などへの紹介を検討します。保護者へは「責める」のではなく、「専門家と一緒にケアしていきましょう」と優しく伝えることが重要です。
向き癖は決して珍しいものではありませんが、そのまま放置すると、見た目の変化だけでなく、運動機能や感覚の発達にも影響することがあります。助産師は、ママと赤ちゃんに最も近い専門職です。早い段階でのアセスメントとケアの提案は、赤ちゃんの発達を支える大きな力になります。ママが無理せず、できる範囲で安心して取り組めるケアを提案し、「様子をみる」ではなく「ちょっとだけ工夫する」を日常に届けていきましょう。
参考文献
新生児訪問の実践ガイド(東京都保健医療局)
写真と図から学ぶ 赤ちゃんの姿勢運動発達
斜頭症・短頭症ガイドライン作成委員会(2020)『乳児の変形性頭蓋症 診療ガイドライン 2020』
日本頭蓋顔面外科学会「頭のかたちと変形性斜頭症
「様子を見ましょう」という言葉で、ママの不安を先送りにしていませんか?
退院後のママたちが本当に求めているのは、曖昧な励ましではなく、プロとしての「現場の正解」です。
じょさんしcampusでは、医学的根拠に基づいた産後ケアスキルを学べる産後ケアコース 無料体験会を開催します。1回だけのご参加も、3回全ての参加も大歓迎です。
今回、無料体験会にご参加いただいた方には、現場でよく聞かれる質問に自信を持って答えられるようになる「退院指導から活かせる 助産師のための産後ケア7大特典」をプレゼントします。

ママたちの「困った」に寄り添い、「ありがとう」と言われる支援へ。 そのヒントを、ぜひこの体験会で持ち帰ってください。
\ 無料で受けられるのはこの機会だけ! /


.png)