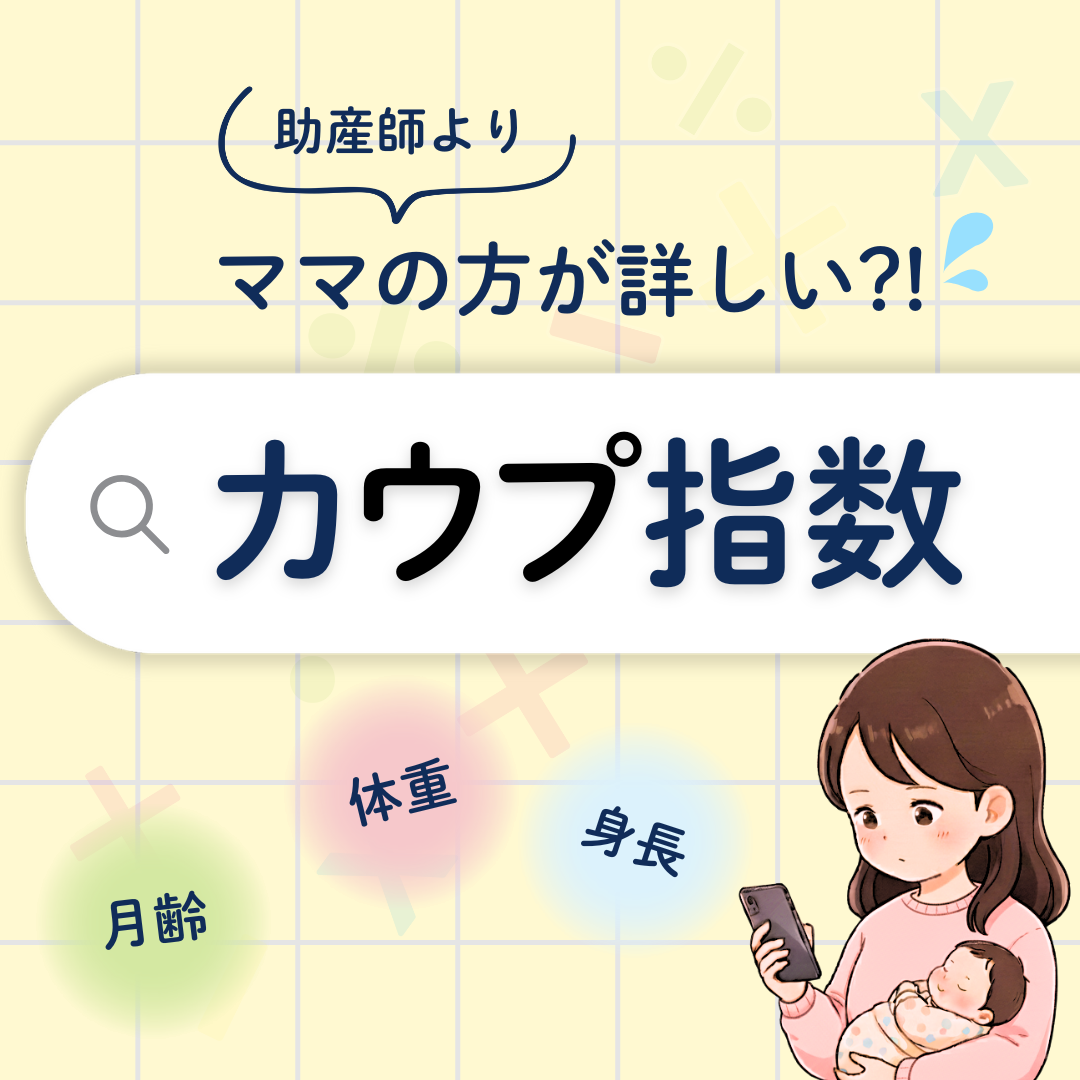厚生労働省の「授乳・離乳の支援ガイド(2019年改訂版)」では、離乳食は単に「食べる練習」ではなく、母乳やミルクでは不足する栄養を補う食事=補完食と定義されています。特に、生後6か月以降の乳児は鉄、亜鉛、タンパク質、ビタミンA・Dといった栄養素が不足しやすくなると指摘されています。
赤ちゃんは胎内で貯めた鉄を使いながら成長しますが、生後6か月ごろから急速に鉄が不足してくることがわかっています。厚生労働省の「授乳・離乳の支援ガイド(2019)」には「生後6か月以降は、母乳だけでは鉄が不足しやすく、適切な補完食の開始が必要である」と記載されています。鉄不足は運動発達や認知機能、情緒面にも影響を与える可能性があり、母乳育児を継続している赤ちゃんほどリスクが高いと言われています。
開始する時期は「生後5〜6か月ごろ」が基本で、赤ちゃんに以下のようなサインが見られたら離乳食スタートの目安とされています。
早すぎる開始(生後4か月未満)は赤ちゃんの消化器への負担やアレルギーリスクを高めるため推奨されていません。WHO・UNICEFの「補完食に関するガイドライン(2001)」には「補完食は生後6か月ごろから開始するのが望ましい」と記載されています。
以前は「10倍粥(米1:水10)」からのスタートが定番でしたが、現在はつぶしがゆからの開始も選択肢として注目されています。10倍粥は水分が多すぎて必要な栄養素やカロリーを補うことが難しいためです。
「お粥=必ず10倍」という固定観念から離れ、赤ちゃんの発達や栄養状態に合わせて粥の形態を選択する必要があります。
BLW(Baby-Led Weaning)=赤ちゃん主導の離乳のことを指します。イギリス発祥の食事スタイルで、最近は日本でも関心が高まっています。
日本の離乳食は「大人が食べさせる」スタイルが主流でした。BLWでは赤ちゃん自身が自分で選択して自分で食べるスタイルであるため大人とともに食卓を囲むこともできます。その反面、10倍粥から徐々に形態を変化させていく従来の日本の離乳食と比較して最初から固型を食べるBLWは窒息のリスクが高いとされています。万が一に備えて窒息の対応方法を学んでおくなど知識と配慮が必要です。手づかみ食べは食への意欲や口腔機能の発達に繋がるとされています。現時点で、BLWは日本のガイドラインに明確に位置づけられてはいませんが、「赤ちゃんが自ら口に運びやすい形で提供する」ことは発達支援の観点からも重要です。
助産師は離乳食に関する相談を受ける機会が少なからずあります。保護者が混乱しやすいポイントと、指導例を紹介します。
保護者からのQ | 最新の考え方 | 指導例A |
離乳食はいつから始める? | 生後5〜6か月ごろから 発達のサインを見て | 発達のサイン ・首がすわっている |
何から始めればいいの? | 栄養重視なら5倍粥+たんぱく源(豆腐など) | お粥だけじゃなく、鉄やたんぱく質も早めに取り入れてみましょう |
手づかみ食べさせてもいいの? | 安全に配慮すれば◎。自律性を育てる | 最初から手づかみに挑戦しても良いです。 窒息の危険はあるので食べやすい姿勢にしてあげること、見守りが必要です |
母乳だけで足りないの? | 鉄・亜鉛などが不足しがち | 6か月以降は母乳だけでは足りない栄養素も出てくるので、不足しやすい栄養素を補うために離乳食が必要です。 |
厚生労働省の「授乳・離乳の支援ガイド(2019)」によるとアレルギー予防のために離乳を遅らせることは推奨されないとされています。
「安定した姿勢」で食べることは、赤ちゃんの口腔発達や安全な嚥下の基本です。ぐらぐらした体勢では、舌や唇の動きも不安定になり、誤嚥・拒否・食べムラなどにつながりやすくなります。これらの悩みはイスや座る際の姿勢を見直すことで解決できる場合もあります。理想の座位姿勢は「90°・90°・90°」です。股関節・膝関節・足首が90°になるイスを選ぶことで安定した座位が保て、手や口の動きがスムーズになり手づかみ食べがしやすくなります。また正しい姿勢は噛みやすく、飲み込みやすいため誤嚥のリスクを下げることもできます。
イス選びのポイント
ポイント | 理由 |
足がしっかり床または足台につく | 足がぶらぶらすると体幹が安定しない |
背もたれがある | 腰が据わっていない時期は特に必要 |
座面の高さ調整ができる | 成長に合わせて正しい姿勢を維持できる |
テーブルが外せる・引き寄せ可能 | 食事の準備や介助がしやすい |
赤ちゃんの「食べたい!」「自分でやってみたい!」という意欲を引き出すには、口のサイズや動きに合ったスプーンを使うことが大切です。
【素材】柔らかいシリコン素材が安心
【形状】先が細くて平ら、口に入りやすい
【柄】親が握りやすい長めの柄(赤ちゃんはまだ持たない)
【例】リッチェル、ピジョン、オクソートットなどの「離乳初期用スプーン」
【素材】柔らかすぎず、少しコシがあるもの
【サイズ】赤ちゃんの口に合う大きさで、すくいやすさも重視
【持ち手】赤ちゃんが握りやすい短め・太めの柄もOK(自分で持たせる練習に)
【例】エジソンのお箸シリーズ(スプーン付き)、オクソートットの自分で食べる練習セット など
保護者の疑問 | アドバイス例 |
膝の上であげてもいいですか? | 姿勢が安定しないので、できれば専用のイスがおすすめです。足がしっかりつくイスだと噛みやすさも向上します。腰すわりが完了していない時期ならママやパパの膝の上で支えてあげて食べるもの良いです。 |
バンボで食べさせています | 足が浮いてぶらぶらしていると噛みにくく、飲み込みもうまくいかないことがあるので離乳食にはあまり向かないかもしれません。正しい姿勢で噛むことができると口腔機能の発達にも良いので足がしっかりつくイスに変更してみると良いと思います。 |
どんなスプーンを選べばいい? | 初期は小さくて平たいもの、中期からは赤ちゃんが自分で持てるスプーンも試してみてくださいね。 |
時期 | 回数 | 主食 | 野菜・果物 | たんぱく質(豆腐・魚など) |
初期(5〜6か月) | 1回/日 | 10倍粥:小さじ1〜5→大さじ2(30g) | 小さじ1〜2(5〜10g) | 小さじ1(豆腐など) |
中期(7〜8か月) | 2回/日 | 7倍粥:50〜80g | 20〜30g | 豆腐30〜40g、魚5〜15g |
後期(9〜11か月) | 3回/日 | 軟飯90g〜 | 30〜40g | 豆腐40〜50g、魚15〜20g、肉15g |
完了期(12〜18か月) | 3回/日+おやつ2回 | ごはん90〜120g | 40〜50g | 肉・魚30g程度 |
◯目安量食べられないor目安量では足りない
◯丸飲みしてしまう子への対処
赤ちゃんは「噛む」「舌でつぶす」という動きが発達途中です。丸飲みはよくあることで、以下の対応が有効です。
食事の形態の見直し
食べ方を見せる
自分で食べられる工夫
◯食べるのをすぐやめてしまう、飽きやすい子への対処
食べる環境の工夫
食事時間を短く設定
盛り付けを工夫してみる
◯好き嫌いが多い子への対処
無理に食べさせない
離乳食は“練習”ではなく、“栄養を補う”補完食としての考え方が少しずつ浸透してきています。母乳・ミルクだけでは足りない栄養(鉄・亜鉛など)を意識してスタートは5倍粥+たんぱく源が主流になりつつあります。月齢だけでなく、赤ちゃんの発達に合わせてBLWなど赤ちゃん主導の食べ方を選択することも「間違い」ではありません。アレルギーを恐れ離乳食がなかなか進まない、食べたがらない、丸飲みしてしまうなど離乳食には悩みがつきものです。保護者は「これで良いのか?」と悩んだり、不安になったりしながら赤ちゃんの離乳食に取り組んでいます。「そのうち食べるようになるよ」ではなく、「今、食べないことに悩んでいる」保護者へ科学的根拠に基づいて支援していくことが必要です。
引用参考文献:
厚生労働省「授乳・離乳の支援ガイド(2019)」
WHO・UNICEF「補完食に関するガイドライン(2001)」
日本小児科学会「乳幼児の食事に関するQ&A」
「様子を見ましょう」という言葉で、ママの不安を先送りにしていませんか?
退院後のママたちが本当に求めているのは、曖昧な励ましではなく、プロとしての「現場の正解」です。
じょさんしcampusでは、医学的根拠に基づいた産後ケアスキルを学べる産後ケアコース 無料体験会を開催します。1回だけのご参加も、3回全ての参加も大歓迎です。
今回、無料体験会にご参加いただいた方には、現場でよく聞かれる質問に自信を持って答えられるようになる「退院指導から活かせる 助産師のための産後ケア7大特典」をプレゼントします。

ママたちの「困った」に寄り添い、「ありがとう」と言われる支援へ。 そのヒントを、ぜひこの体験会で持ち帰ってください。
\ 無料で受けられるのはこの機会だけ! /


.png)