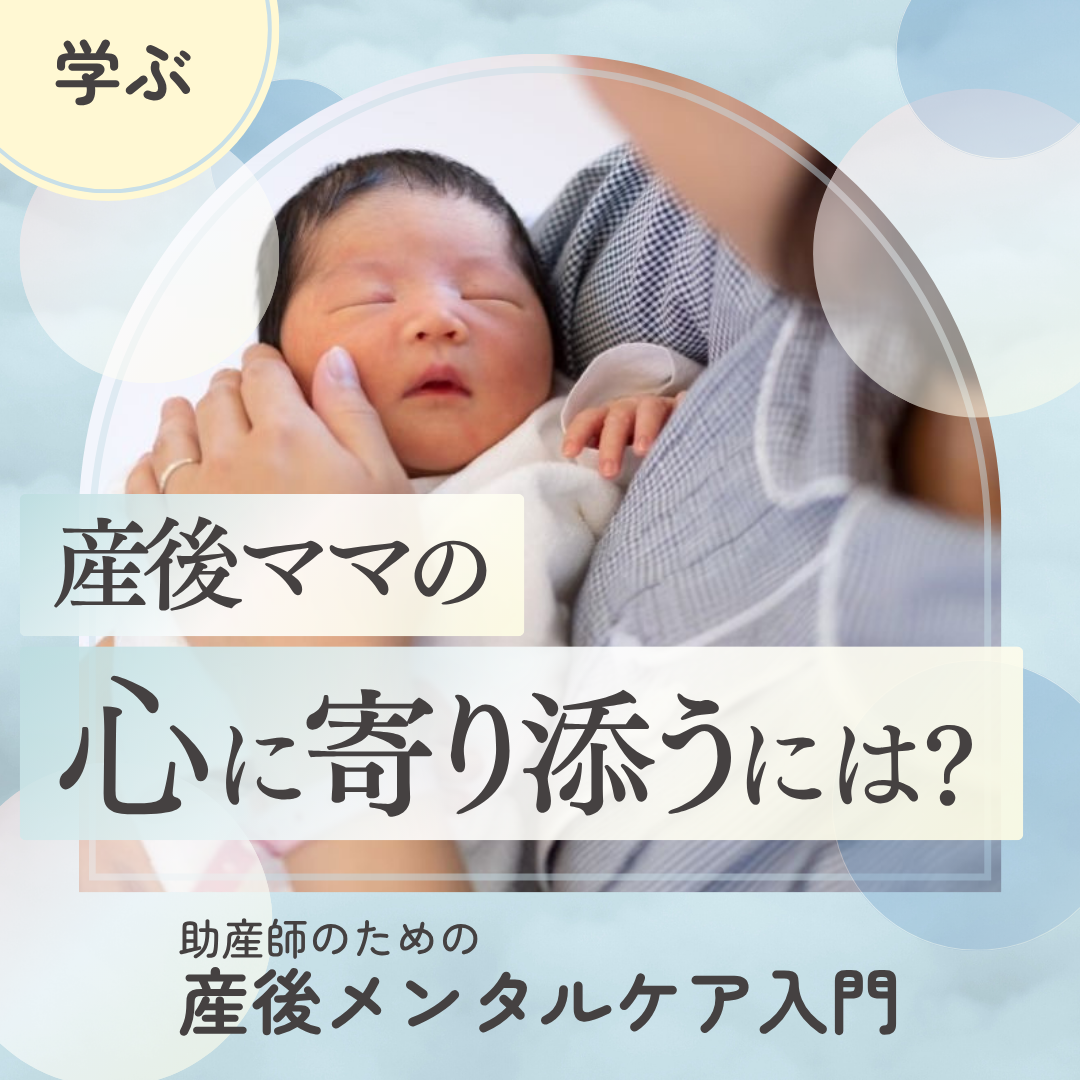
産後ママの心に寄り添うには?|助産師のための産後メンタルケア入門
- メンタルケア
- 産後のメンタルヘルス
- 産後うつ
産後のママは、身体的な回復と同時に、新しい命を迎えた喜びと責任の重さ、そして日々の育児に対する不安や戸惑いを抱えています。そのようなママたちの心に寄り添い、適切なメンタルケアを提供することは、産後うつの予防や早期発見につながります。健やかな母子関係を構築できるように支援することは助産師の役割です。しかし、心理的に危機的な状況は、簡単に解決できるものではなく、どのように介入したらいいのか、この関わりでよかったのかと助産師自身も答えを見出せず困難を感じる場面もあるのではないでしょうか。ここでは、その悩みのヒントになる技術をお伝えしていきます。

1.メンタルヘルスケアの基本姿勢
1)ケアを開始する前に
ケアを開始する前に、まずは話ができる環境を整えることが必要です。プライバシーが守られ、リラックスして話しやすい空間を作りましょう。開始する際は、終了時間を明確にします。目安がわかることで安心感が得られ、ママも見通しを立てて話すことが可能になります。充実した1回の面談やコミュニケーションの方が効果的なこともありますが、初回の段階で全てを解決しようとせず、ママのペースに合わせて関係性を築いていくことを心がけます。話したくないことは話さなくてもいいことを保証し、急がず、焦らず、ママが自分の気持ちを表現できるような環境を整えることが、効果的な支援の基盤となります。
2)信頼関係(ラポール)を築くために
いくら面談をしても、相手が「話をしたい」「この人に聞いてほしい」と思えるような関係性を築けないと面談によるメンタルケアの効果が得られません。ママに安心感を持ってもらい、心を開いて相談してもらうための基本姿勢があります。
1つ目は自然体でいることです。 聴き手の心理状態が安定していて、率直な気持ちと態度で話し手に向き合えることです。相手に対して、防衛的になったり、虚勢的になっていると相手もそれを感じとってしまいます。
2つ目は受け入れる姿勢です。 親しみやすい雰囲気で、相手のペースに合わせ、最後まで話を聞きます。表情や仕草など非言語的コミュニケーションにも注意しながら聞くことが大事です。
3つ目は相手の立場に立つことです。自分の人生観や価値観ではなく、相手の見方・考え方を理解します。全ての気持ちを同じように共感することは難しいですが、理解しようとしているという姿勢がポイントになります。

2.心理援助の実践
心理援助は「かかわり」「傾聴」「共感」「プローブ」といった4つの基本的な技法があります。
「かかわり」は相手に体を向け視線を合わせるなど、「あなたの話を聞いています。」という姿勢、態度です。
「傾聴」は、共感ができるように現在の状況や感情などを丁寧に聞き取り、把握することです。
「共感」は、傾聴して得られた内容を相手にフィードバックして、相手の気持ちを理解しようと努めることです。
「プローブ」は、より詳しい情報を引き出したり、話を促進するテクニックです。話の中から具体的な状況や感情の詳細確認をします。
これらの順で援助することで、お母さんは自分自身の状況を客観的に見つめ、解決の糸口を見つけることができるようになります。様々な感情が混在していることが多いため、一つ一つの感情に丁寧に向き合う必要があります。
3.防衛と抵抗への対応
心理援助は無意識に一旦追いやられた感情を、一旦意識化して「こころの整理」をする作業のため、辛い感情から自分を守ろうとすることがあります。予定を突然キャンセルしたり、途中で話すことが辛くなり黙ってしまう、話題を変えて終結する、などはその例です。一見すると当たり前のような行動や、反対に激しい情動を表す方もいますが、それらには必ずその人なりの理由があり、自然な反応でもあります。心理的な防衛機制に直面したときは、その背景にある感情や理由を理解することが重要です。問題を含んだ行動も、その人なりの適応としての側面を持っています。決して否定的に判断せず、その行動の背景にある気持ちを理解しようとする姿勢が大切です。
言ってはいけない言葉
「頑張りましょう」「しっかりしないとね」などの言葉は、頑張りたくてもすでに頑張れない状態の場合もあり、さらに追い詰められてしまうことがあるので、安易に励ましの言葉は使わないようにします。また、「『死にたい』など考えてはダメ」と、SOSを出して援助を求めている相手へ否定的な言葉を使うと、自分を批判、否定されているように感じてしまうため、その気持ちを理解したことを伝えるようにします。そして、その行動はとらないことを約束できるといいでしょう。
4.専門家へ紹介するときのコミュニケーション
受診を勧める際の適切なタイミングを見極めることは、助産師の重要なスキルです。ママが受診を拒否したり、「自分の責任で何とかしたい」と考えている場合でも、その気持ちを受け止めつつ、必要に応じて専門家への相談を促すことが大切です。
そのためには、ママの状況について本人がどう考えているのかを十分に聞き取り、その上で「一緒に考えてみませんか」という姿勢で接することが重要です。強制的な指導ではなくママの意思を尊重しながら、最善の選択肢を一緒に探っていく姿勢が求められます。
参考文献
産後のママの心に寄り添うメンタルケアは、技術的なスキルだけでなく、人間としての温かさや深い共感力も求められます。助産師は、ママの心の声に耳を傾け、その人らしい子育てを支えることで、健やかな母子関係の構築に貢献することができます。

助産師のための“今どき離乳食”入門|補完食としての考え方と便利グッズの選び方
- 離乳食
- BLW
- アレルギー

助産師が知っておきたい|0歳児によくある肌トラブル7選と基本ケア
- 肌トラブル
- 新生児
- スキンケア
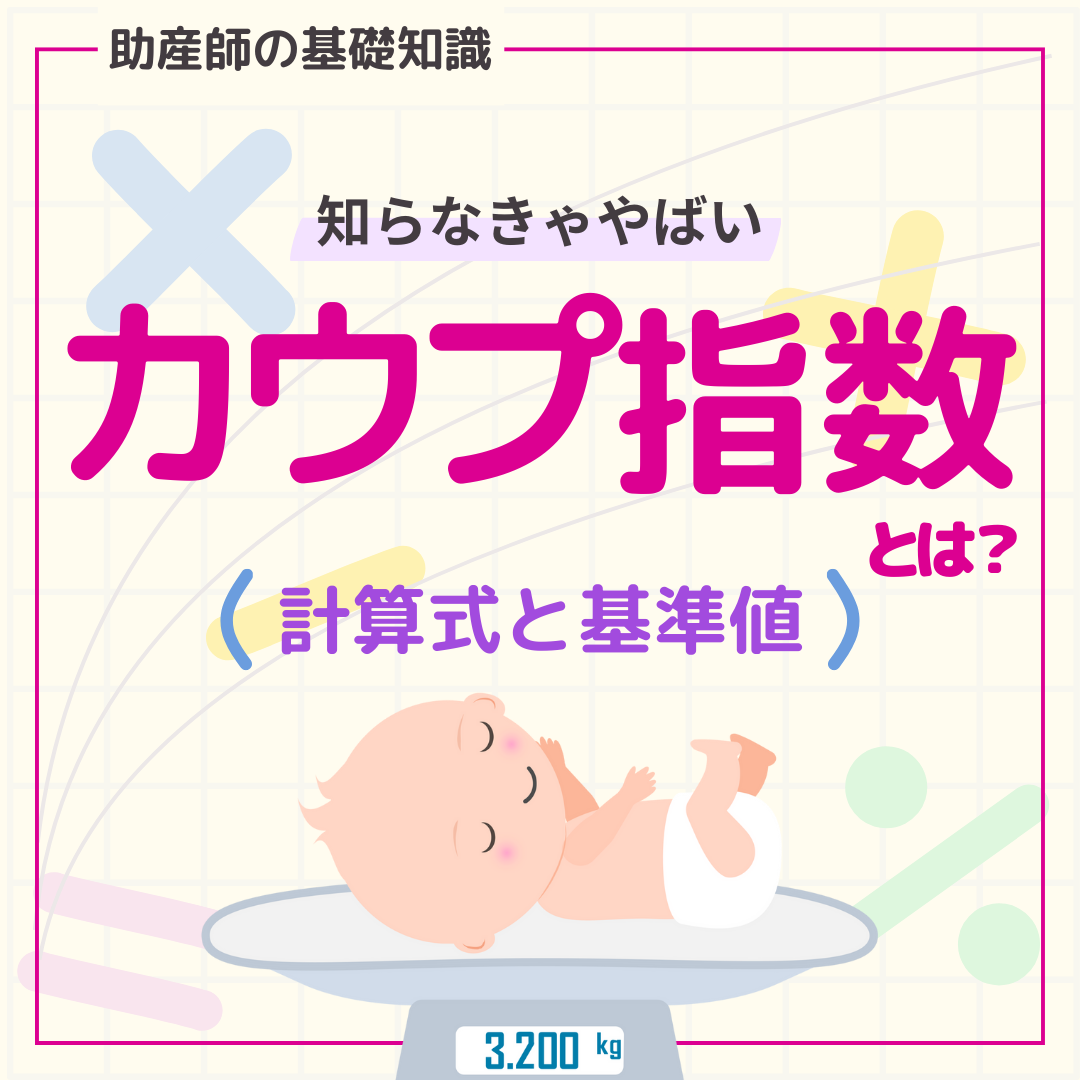
【知らなきゃやばい】カウプ指数とは?計算式と基準値|助産師の基礎知識
- 産後ケア
- 赤ちゃんの発育
- 育児相談

【新人助産師と学生が押さえておきたい】CTG(NST)モニターの基礎知識|基線・基線細変動・一過性頻脈の見方をわかりやすく解説
- CTGモニター
- モニター判読
.png)
【助産師必見】超音波検査での胎児計測|基本項目と正しい計測方法を徹底解説
- 超音波検査
- 助産師によるエコー検査

“なんとなく”の指導はもう終わり。エビデデンスに基づく乳頭ケアの指導方法|妊婦さんの「やってみよう」を引き出す助産師の言葉は?
- 乳頭マッサージ
- 妊娠中
