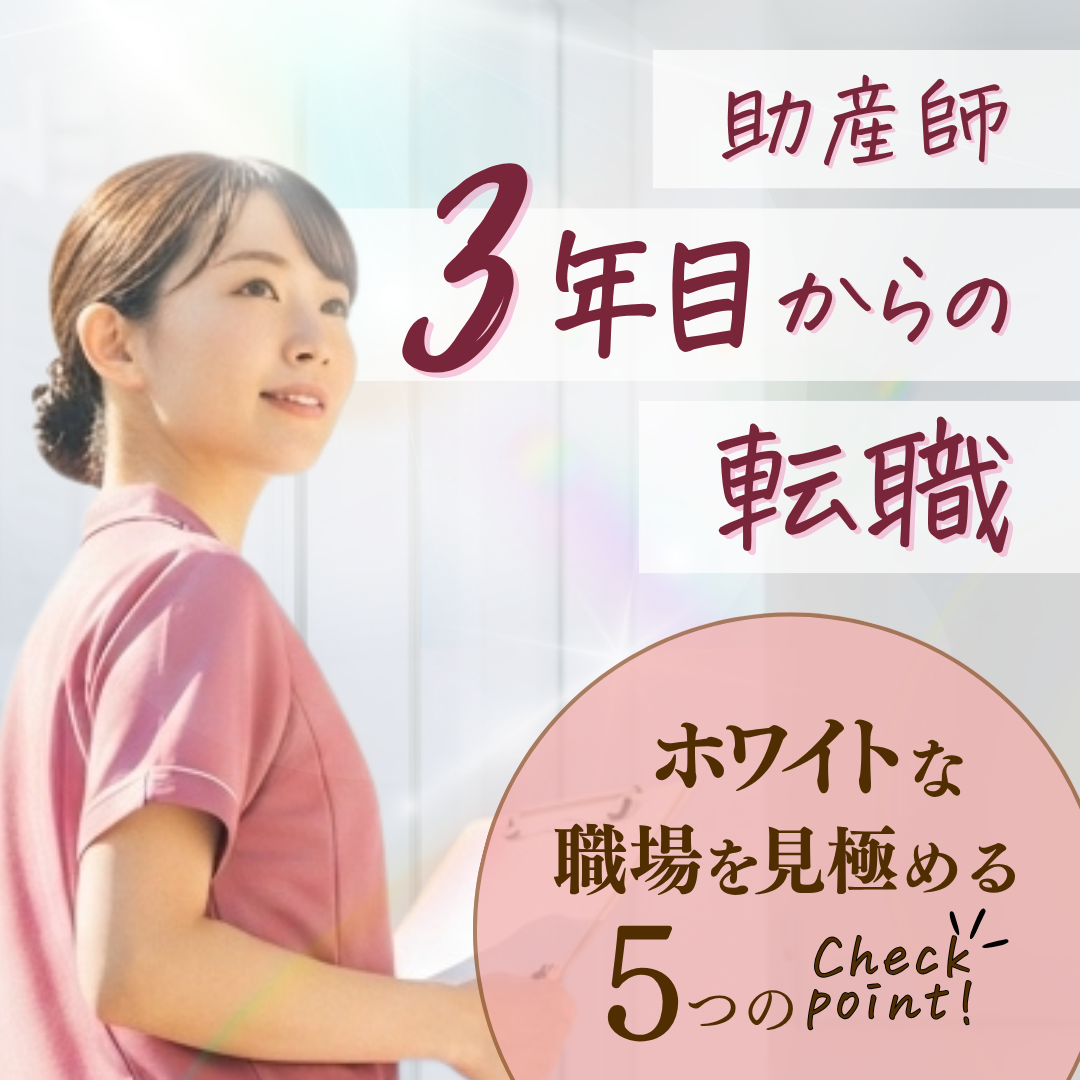
助産師3年目からの転職|ホワイトな職場を見極める5つのチェックポイント
- 転職
- ホワイト病院
- 助産師3年目
助産師になって3年目、日々お産に立ち会い、新しい命の誕生をサポートする喜びを感じる一方で、「理想のケアとのギャップにモヤモヤする…」「日々の忙しさで心身ボロボロ、このままここで働き続けられるのかな?」と悩んでいませんか?
最初は覚えることや日々の業務についていくことだけで精一杯だったのが、今では一人で分娩介助や外来業務もできるようになって、少し余裕が出てきた時期かもしれません。だからこそ職場の人間関係、働き方、自分が理想とするケアとのギャップなど気になっていることが浮き彫りになってくる時期です。
「私って助産師に向いてないのかも」「責任は重いのに給料は全然上がらない」「毎日残業続きで疲れた」そんな風に感じているなら、それは決してあなただけの悩みではありません。実は、3年目は転職を考える人がとても多い時期です。一方で「どこに行っても忙しい」「あなたの経験じゃ転職は難しい」と言われることもあり、転職はまだ早いと思う方もいるかもしれません。しかし実際、助産師3年目は転職するにあたってベストタイミングであることもあります。
1.3年目からの転職がチャンスな理由
①即戦力になれるから
助産師3年目は、もう立派な戦力です。基本的な助産や看護技術は身についており、緊急時の対応もある程度は自分で考え判断し、行動できるはずです。だからこそ転職先の病院からも「即戦力として欲しい人材」として見てもらえます。新人教育にかける手間も少ないので、採用されやすくなります。
②自分の大事にしたい理想や考えが明確になるから
「もっと妊婦さんの気持ちに寄り添いたい」「自然なお産をサポートしたい」「予防的なケアにも力を入れたい」など、自分なりの理想とする助産師像や助産観、特に深めたい分野が見えてくるようになる時期でもあります。新人時代はとにかく知識や技術を覚えるため日々精一杯だったかもしれませんが、この時期になると自分の価値観を大切にして職場を選べるようになってきます。
③適応力があるから
長年に渡って同じ職場環境や職場仲間の中にいると、新しい環境や雰囲気へのギャップが大きくなり慣れることが難しく感じられます。しかし3年目なら、まだ新しい職場環境や人間関係に適応していく柔軟性があります。違う病院のやり方や文化にも順応しやすいし、キャリアチェンジも様々な選択肢から選ぶことが可能です。

2.ホワイトな職場を見極める5つのポイント
転職を考えるのであれば、自分を大切にしながらステップアップができる、長く働きやすい職場を見つけたいところです。しかし求人票だけでは分からないことも多くあります。ここでは、本当にホワイトな職場かどうかを見極めるポイントをお伝えします。
① 「建前」と「本音」のギャップがないか
- 「残業はほとんどありません」と言われたけど、実際はどうなの?
- 「有給は取りやすいです」って言うけど、本当に取れてるの?
- 勤務時間前に来て情報収集するのが当たり前になってない?
- 勤務交代の時間なのに「この分娩が終わるまで」って言われたりしない?
面接で遠慮は禁物です。「実際の残業時間ってどのくらいですか?」「有給って本当に取りやすいんですか?」と聞いてみましょう。具体的な数字で答えてくれるところは信頼できます。曖昧にはぐらかされるようであれば要注意かもしれません。
②ギスギスしてないか人間関係をチェック
- スタッフ同士、自然に笑顔で話している?
- 困ったとき、すぐに相談し合えてる雰囲気?
- 先輩の指導方法は建設的?人格否定していない?
- 陰口や無視、変な空気感はない?
面接の際に院内見学ができるようであればそこで働いているスタッフの雰囲気ややり取りもチェックしてみましょう。助産師の職場は、どうしても閉鎖的になりがちなところが多いです。人間関係で悩んで辞める人は実際かなり多い現状があります。職場見学のときは、スタッフ同士がどんな風に関わっているか、よく観察してみてください。「なんだか雰囲気が重いな」と感じたら、あなたの直感は正しいかもしれません。
③一人で抱え込まされてない?業務量と安全体制
- 一人の助産師が何人の妊婦さんを受け持っているの?
- 一人夜勤のとき、緊急事態になったらちゃんとサポートしてもらえる?
- 人手不足で「とりあえずあなたがやって」みたいな無茶振りはない?
- 何かあったとき、個人の責任にされちゃうような空気はない?
- プリセプターはつけてもらえるの?
母子の命を預かる責任が重いのは当然ですが、一人で全てを背負う必要はありません。特に夜勤時や休日などに適切な人員配置と、チーム全体でサポートする体制があるかを確認しましょう。
④頑張りに見合った対価がもらえてる?
- 基本給や手当、同じ地域の他の病院と比べてどう?
- 昇給やボーナス、ちゃんと実績がある?
- 病院の経営状況は安定している?
- 頑張りを評価してもらえる仕組みはある?
やりがいがあるから給料は我慢などと思う必要はありません。助産師という専門性と責任の重さに見合った対価をもらうことは当然の権利です。安く使われている、捨て駒にされていると感じるのであれば、もっと適正に評価してくれる職場があるはずです。
⑤成長できる環境?それとも現状維持?
- 研修や勉強会、充実している?
- 外部の研修にも参加させてもらえる?
- 研修や資格取得の費用補助はある?
- 先輩たちは専門性を伸ばせている?
- 自分が興味のある分野(地域保健、性教育、自然分娩など)を伸ばせそうか?
毎日同じことの繰り返しで成長してる気がしないと感じていませんか?せっかく転職をするのであれば、自分がもっと成長できる環境に身を置きたいですよね。スタッフの教育に力を入れているかどうかは、その職場の本気度が分かるポイントの1つです。
3.転職前に立ち止まって考えてみて
転職活動を始める前に、一度自分の考えや気持ちを整理してみましょう。「なんとなく嫌だから」で転職すると、また同じような悩みで転職を繰り返すことになるかもしれません。
①あなたが一番大切にしたいことは何?
次のような項目から、自分が重視するものを考えてみましょう。大切にしたいことに優先順位をつけることで、本当に自分に合った職場が見えてきます。
- 夜勤なしで安定した生活リズム
- 今より良い給料や待遇
- プライベートが大切にできる働き方
- ギスギスしない、風通しの良い人間関係
- 自分の価値観にあった病院の方針
- 患者に寄り添ったケアができる環境やマンパワー体制
- 基礎から学びフォローが得られる教育体制
- キャリアアップのために自分の学びたい専門分野が学べる職場
②今の職場の「好きなところ」も思い出してみる
不満ばかりに目を向けがちだけど、この職場のここは好きだな、この部分はやりがいがあるなということもあるかもしれません。それを書き出してみると、次の転職先を選ぶ上で大切にしたい部分を考慮しながら選ぶヒントになります。
③一人で悩まない
転職は人生の大きな決断です。一人で抱え込まずに誰かに相談してみてください。助産師の仕事を理解してくれる先輩や同期に話せるのであれば経験をもとにアドバイスがもらえるかもしれません。また医療職ではない友人、家族であっても誰かに話して自分の気持ちや考えを言葉にすることで自分の中での整理になるかもしれません。さらに助産師専門の転職サイトじょさんしcareerでは助産師であるアドバイザーが、キャリアや転職相談を行っています。転職の検討や情報収集段階でも気軽に相談を行うことができます。
4.転職活動のコツ
①職場見学をさせてもらう
分娩件数や実際の勤務体制など求人票や面接だけでは分からない情報も多いです。実際に職場内の雰囲気や働くスタッフの様子見させてもらって、働いている人たちの表情や雰囲気を感じ取ってみると良いでしょう。「なんか違うな」と思ったら、その直感が正しいかもしれません。
②遠慮しないで質問する
これから長く働くかもしれない職場です。気になることは小さなことであっても何でも聞いておきましょう。むしろ、質問に嫌な顔をするような職場は避けた方が無難です。
③助産師専門の転職サポートじょさんしcareerを使ってみる
じょさんしcareerは一般的な看護師の転職サイトと違い、助産師の仕事をいちばん理解している助産師がアドバイザーです。同じ助産師として悩みや不安を詳細まで理解し、自分の悩みに寄り添った客観的な視点でアドバイスをもらうことができます。また無理に転職を勧められることはありませんので「相談だけ」でも大丈夫です。
またじょさんしcareerのクチコミサイトでは、過去5年以内にその職場で実際に働いていた助産師からのクチコミを確認することができます。たとえば求人票や面接には載っていない、「分娩スタイル」や「夜勤の人数」「院内助産」、「産後ケア」、「両親学級」、「母乳育児推奨かどうか」といった項目があります。助産師ならではの気になるケアや深めたい分野がその職場で叶えられるのかという視点で職場のクチコミを見ることができます。さらにワークライフバランスや給与、福利厚生、待遇面も実際にそこで働いている助産師からの最新情報を確認することができるため、自分の理想とする働き方が叶えられるのかクチコミからも情報を収集し検討することが可能です。
3年目の助産師のあなたなら、きっと素敵な職場に出会えます。「今の職場がすべて」じゃないし、「我慢するしかない」わけでもありません。あなたが助産師としてだけではなく、1人の人間として幸せに働ける場所は必ずあります。自分の気持ちに正直になって、理想の働き方を追求してみてください。
転職するかどうか迷っているなら、まずは自分の気持ちを整理することから始めてみませんか?そして一人で悩まず、信頼できる人に相談してみてくださいね。あなたの助産師人生が、もっと輝くものになることを心から願っています。
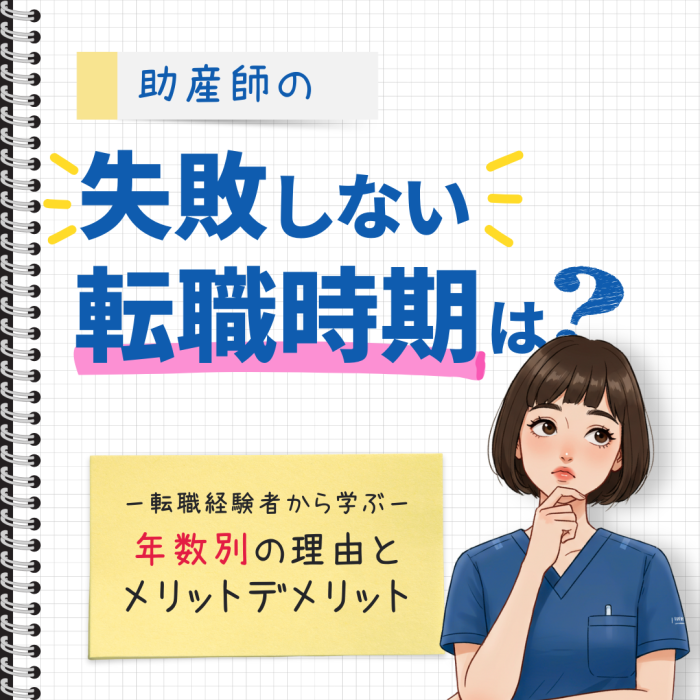
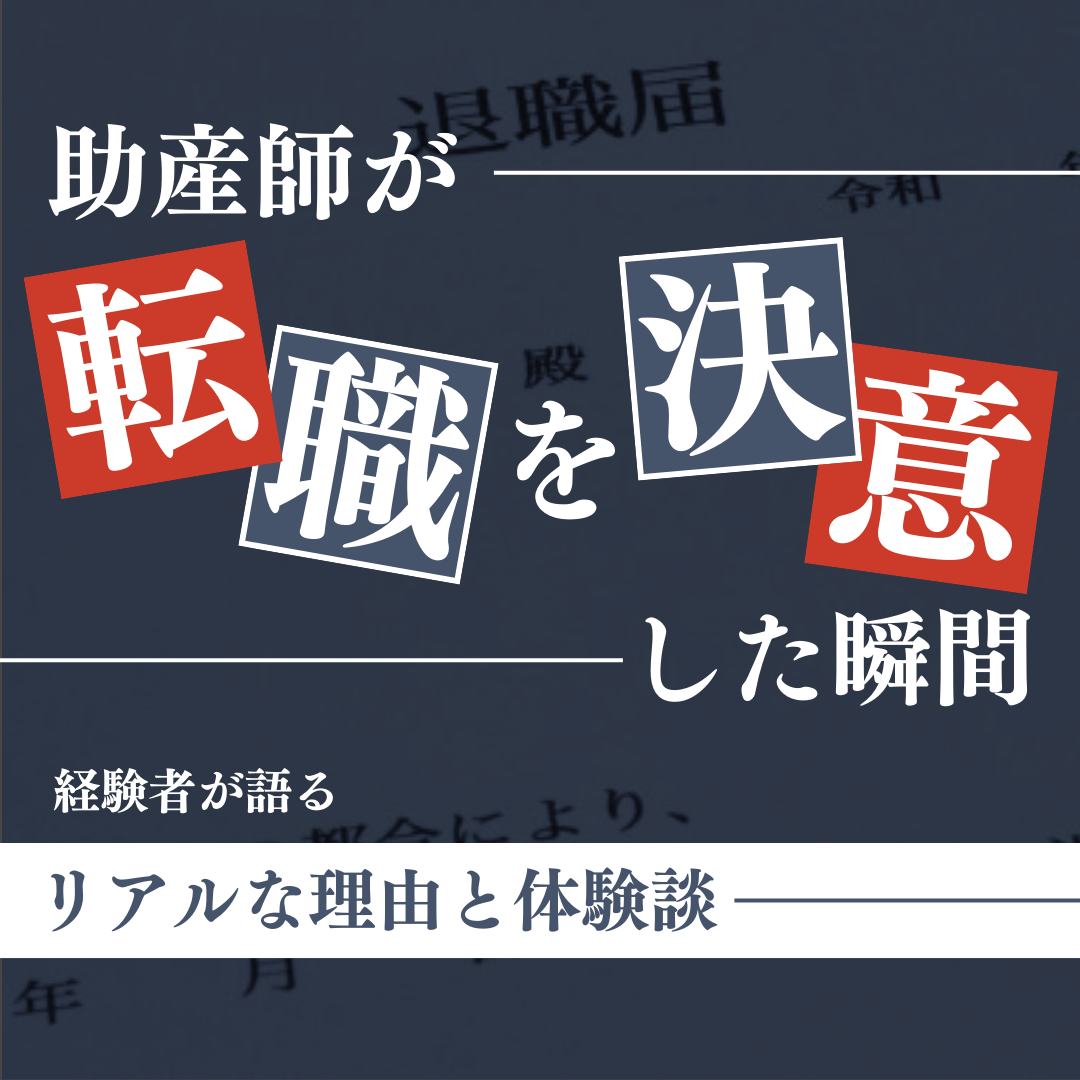
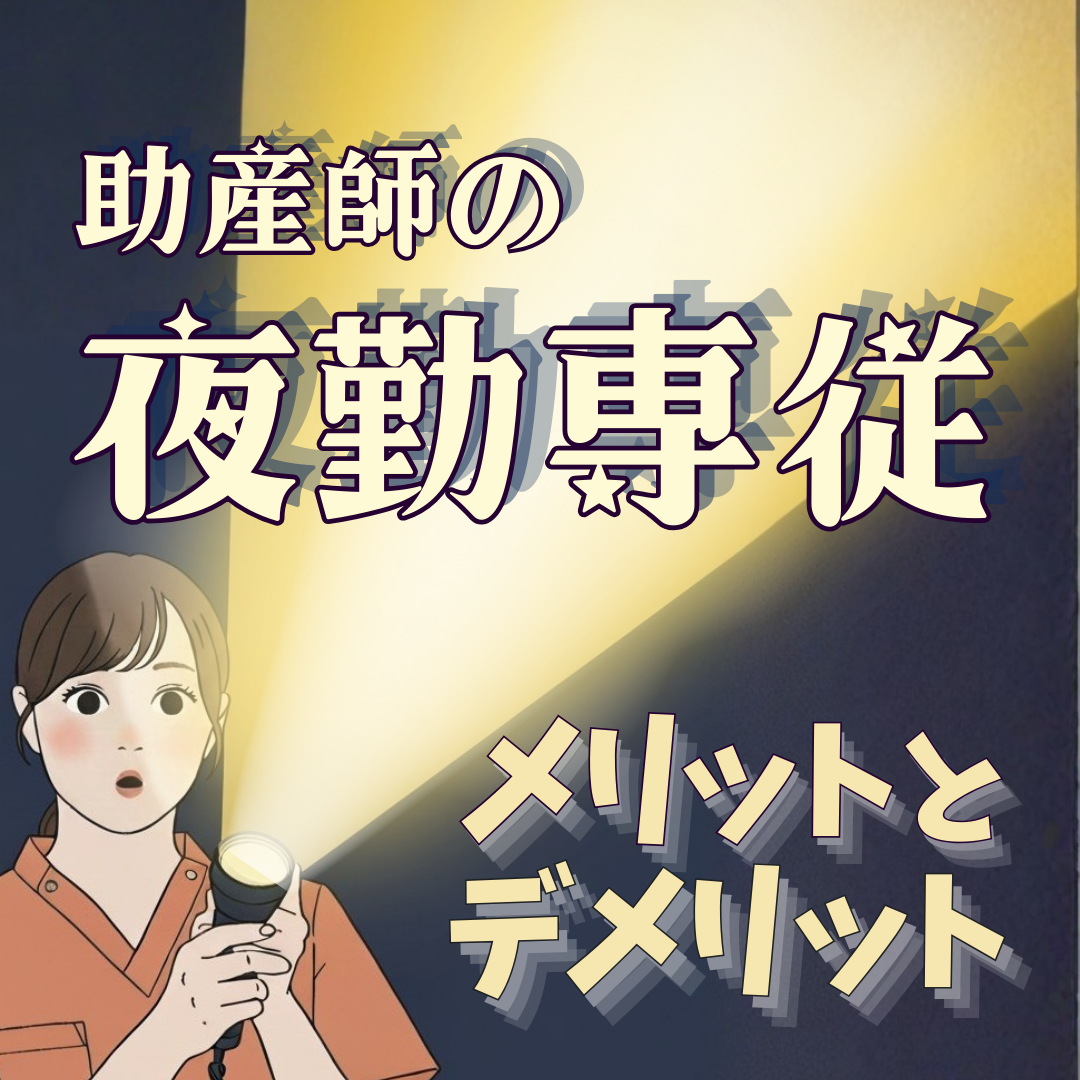



.png)
